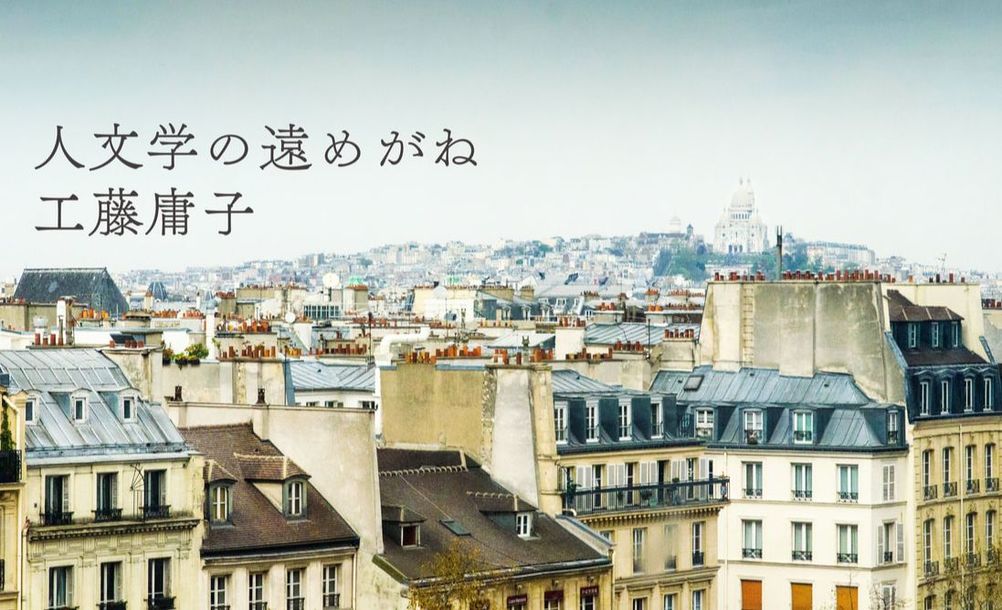|
In our time Proust was wholly androgynous, if not perhaps a little too much of a woman. (現代でいえば、プルーストは完璧な両性具有、女性の割合がやや勝ちすぎているかもしれないけれど)――こんな名台詞を読むと、じんわりと嬉しくなりません? 出典は、わが愛読書ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』ですが、この一言がジェンダーの歴史において画期をなすことの理由は、「近代的=二元論的」な性差の概念を、いとも軽やかに廃絶してしまったから。そこで、引用をもうひとつ。
The best woman (is) intellectually the inferior of the worst man.(いちばん出来のいい女子でも、知性としては、いちばん出来のわるい男子に劣る)――これも同じエッセイのなかの台詞。といっても発話者はもちろん著者本人ではなく、ケンブリッジのさる大物教授だとか。こんな話がウルフにあるのよ、と友人の若い女性編集者に紹介すると、屈託のない笑いが返ってくるのだけれど、そしてウルフ自身もユーモアと皮肉がはじけるような文体でこれを書いているのだけれど、でもね、わたしとしては身に覚えがあるのです。 「プルーストが女にわかるか?」という、昔々、わたしが学生だったころ、雑談のなかで男子学生たちが得意気に口にしていた台詞。くり返し紹介しているのは、恨みがあるからでは全然なくて、その論理構造が客観的に興味深いから。そもそも女性は芸術の鑑賞者であるべきで文学や詩の創造という主題はあまりに高踏的で理解できまいという、今日でも解消されたわけではない古色蒼然たる紋切型が透けて見えるのだけれど、それだけではない。なにしろ『失われた時を求めて』は「男性同性愛者」の書いた「芸術家小説」なのであり、したがって女性は性と知性において二重に排除されている、という理屈。つまり「男性同性愛」というのは二重に「純化」された男性性? プルーストは男のなかの男? 問題の男子学生たちが無意識に依拠していたと思われる見取り図を、とりあえず「排除的性差」×「序列的性差」によるジェンダー概念と定式化しておきましょう。 ウルフは多少とも両性具有的でない人間は、ダメだと言っているのですよ。「偉大な精神は両性具有」という表現は、コールリッジからの借用だそうですが、そのコールリッジを含め、人間と世界を理解した両性具有の王者はシェイクスピア。一方でワーズワースとトルストイは「男性の割合がやや勝ちすぎている」とのこと。ここで、ウルフさま、よくぞ言ってくださいました、という感じの、三つめの引用を。 It is fatal to be a man or woman pure and simple; one must be woman-manly or man-womanly(男でしかない男、女でしかない女は救いようがない。だから男っぽい女、女っぽい男になりましょう!) 女性作家の軽いジョークを紹介しているわけではありません。『自分だけの部屋』が刊行されたのは1929年。イタリアではムッソリーニがファシズム体制を着々と築いており、ヒットラーの大統領選出馬とナチ党の躍進は3年後。テクスト上でもヨーロッパの政治的な緊張を横目で睨んだエピソードとして「両性具有」という話題が導入されているのです。著者にとって女性排除の二大巨頭はナポレオンとムッソリーニ。個人の性格や特質ではなくて、二元論的な近代を構築した人物とその延長上で人類の災厄を招こうとしている人物という位置づけです。「文学」に身をおく者として、男性中心的な「政治」と「歴史」をいかに批判し、相対化して、プルーストの体現する「文学」の尖鋭な革新性をいかに際立たせるか。ウルフの称揚する創造的な「両性具有」とは、そのための戦略的キーワードにほかなりません。 ためしに「排除的性差」×「序列的性差」という定式の語彙を一部入れ替えて「排除的エスニシティ」×「序列的エスニシティ」としてみましょう。同じ論理、同じ力学によって、ヨーロッパが国民国家の内部からユダヤ人という他者性を析出したことが想像できるはず。さて唐突ながら、ここで読みおえたばかりの樋口陽一『抑止力としての憲法』(*1)からカール・シュミットにかかわる段落を抜書きしてみます。 若い女性編集者と仕事をするのは楽しいもの。打ち解けたところで、かならず質問するのは――「ところで男性と女性に能力差はないと思っている?」――「もちろんです!」と大抵は明るい微笑が返される。つづいて「わたしはねぇ、東大出版会からヨーロッパ批判三部作の2冊目を刊行して、初めて能力差という呪縛への疑念を抱き、スタール夫人に出逢って、初めて解放された」と述懐すれば「ふーん、そうなんですかぁ」という顔。たしかに今なら、男女の能力差など絶対にありません、むしろのびやかで創造的な女性こそ将来が楽しみ、と断言できるような気もするのです。これは二十代の若者たちを見て痛感することであり、同じような感想をもらす年長の人間は、男女を問わず少なからずいるわけです。
それにしても「呪縛」の源にある隠然たる「序列的性差」の力学が、わたしの個人的な妄想であろうはずはない。などと考えていたところで「日弁連、副会長に女性2人以上 「クオータ制」導入へ」「最高裁判事で初の旧姓使用へ 来月就任の宮崎氏『当然』」という並んだ見出しが目に留まりました(朝日新聞12月9日朝刊)。女性副会長については、何人中2人かというと、男女同数を前提とする「4人中」でもなく、指導的地位の女性比率達成目標30%を想定した「6人中」でもなく、なんと「15人中」であり、しかも、この「クオータ制」による女性枠確保のために新たに2人の増員を定めてのこと。ちなみに現在、弁護士の女性比率は18.4%だそうです。この現状を「クオータ制」と名づけることが許されるわけ? と批判的に見ている若い世代の弁護士は、男女を問わず少なからずいるのだろうと想像します。新任の最高裁女性判事が戸籍名と旧姓の併記ではなく「旧姓での報道を強く求め」、旧姓使用を「当然だと思っています」と述べたという話は、まさに「当然です」と強く賛同しておきましょう。それにしても、このケースが「初の旧姓使用」だとは・・・・・・。両性の平等を謳った憲法のもとで、男女の能力差は「自然的」には全く存在しないという一般的な承認と、これだけ歴然たる「社会的」な格差とを、平然と共存させている日本とは、いったい如何なる国なのか。将来の世代のことを考えれば、ここで沈黙するわけにはゆかないのであります。 「序列的性差」とわたしが呼ぶのは、先回に紹介した人類学者フランソワーズ・エリチエによる「二本のネクタイ」の言い換えです。男性と女性は対等な選択肢として並置されているように見えるかもしれないが、じつはあらゆる二項対立的思考を貫く「序列化」の力学が作動して、女性は常に負の側に位置づけられるというのが、その要点(「3. 二本のネクタイあるいは男女格差について」)。エリチエによれば、これは特定の社会というより人類全体に当てはまる一般法則であるとのこと。この指摘に寄り添うかたちで、みずからの実感にもとづく「性差のゆらぎ」という概念を素描してみたいと思います。 今回の衆議院選挙においても言語道断な女性比率は相変わらず。その結果に怒り、その怒りがメディアにしかるべく反映されぬことにも、ふつふつと怒りを覚えている女性たちが、はたしてどのぐらいいるか。少なからずいるはず、と信じることにします。
なにしろ内閣府男女共同参画局には「各分野における指導的地位」の女性比率について「2020年30%の目標の実現に向けて」というサイトが麗々しく立ちあがっているのに(2020年までにあと2年!)、政権与党である自民党の当選者の女性比率は、なんと7.7%なのであります。しかも、政権担当者たちは努力目標ですらない空手形の公約など、すっかり忘れたかのように、恥じる気配もありません。興味深い数字は、分裂した野党二党に関するもの。女性が代表を務めていた希望の党は47名の女性候補者を立てながら当選はわずか2名、にわかづくりの立憲民主党は19名の女性立候補者のうち12名が当選(『朝日新聞』10月25日)。この奇妙な歪みは何を意味するか。まっとうな市民生活から政党政治があられもなく乖離しているとしかいいようがありません。 結果として、女性の意志や知性や生活条件を反映する議席が1割しか与えられなかった。じつは政治の世界と知の世界には、もし適正に数値化することが可能であれば、ほぼ同等の男女格差がある、日本では「ガラスの天井」どころか、はるかに低いところに「1割の壁」があって道を塞いでいる、と経験的に感じています(*1)。ともかくこれでは「パリテ法」(男女同数への権利)を発議したくともできない。「代議制民主主義」の大原則からしても、すべての個人に政治的自由を保障すべき「人権」の理念に照らしても、日本の現状は、明らかに不整合なのではありませんか。ここは「指導的地位」におられる9割の男性の方々に、つよく求めておきましょう――「異性の問題」としてではなく「政治の問題」「社会の問題」として、この格差の由来を考え、それぞれの立ち位置から発言していただきたい、と。 さて本日とりあげるのは「二本のネクタイ」という寓話。二本のネクタイのうち好きな一本を選ぶように、自由に男か女かを選べるという解説はまやかし、誤魔化されてはダメ、という厳しいお話です。女性への聖職授与を認めぬカトリック教会の論理構造を批判して、ある人類学者いわく――神さまは二本のネクタイの好きな方を選んだわけではない、社会の鋳型から考えて、それ以外にはありえぬ一本を選んだだけであり、社会は啓示宗教が登場する以前から、男性を上位においてきた。神の子たるものが、性の混乱を象徴する両性具有に生まれてくるわけにはいかなかったのであり、かりに神の子が、規範に反して二本のネクタイを首に巻くような具合に、両性具有に生まれていたら、聖職者の選択の可能性は大いに狭められたことだろう、とユーモアをまじえた考察がつづきます。 スタール夫人のテクストで巧みに使われる雷と電位差のメタファーがきっかけで「パリのアメリカ人」のことを考えはじめたのだった。革命前のフランスのサロンには、フランクリン・ブームと呼べるものがあったにちがいない。
1776年7月4日、アメリカ13州の独立宣言が採択された。一方的に「国家」を名乗った若々しい政治勢力を代表し、ベンジャミン・フランクリンがフランスに向けて発ったのは、その年の暮れ。イギリス軍と植民地軍との武力衝突は容易に決着が着きそうにない情勢下、3名の使節団に託された喫緊の課題は、独立軍に対する物資や資金の援助をとりつけ、旗幟を鮮明にした軍人や義勇兵の個人的な参戦を促すことだった。フランスにしてみれば、7年戦争に敗退して植民地を奪われたばかりの英国に荷担するのは非現実的な選択だったけれど、ただでさえ逼迫した国庫に負担をかけてまで他国の争いに介入する必要はないし、そもそも君主制の国家が共和制をめざす反乱軍の味方になれば自国の不安定化を招く、という主張は正論だった。ただし、かりに英国が勝利して北アメリカを傘下に収めれば、目前に世界帝国という脅威が出現することになる。 正攻法で国家間の交渉を提案する正統性をもたぬフランクリンは、アメリカの「革命」に共鳴する「世論」を形成し、搦め手からも外交に働きかけようと考える。手品のような早業でサロンの寵児になることは、短期決戦の戦略的要請でもあった。赫々たる成果は年譜で確認できる。1778年、米仏同盟条約に調印。1779年、駐仏全権公使となり、1781年、対英講和会議代表、1783年、米英の戦争終結にかかわるパリ講和条約締結。宗主国イギリスをはじめ、ヨーロッパ諸国との折衝においても、フランクリンの外交的手腕と人格的な信望は圧倒的なものだった。アメリカに帰国して5年後の1790年、訃報が伝わるとフランスの国民議会は3日間の喪に服した。 それにしたってサロンの寵児などというものは、なろうと思ってなれるものではない。ここで参照するのは、マルク・フュマロリの『ヨーロッパがフランス語を話していたころ(*1)』という著作。タイトルを見ただけで、所詮はグローバル言語幻想だろうと敬遠したくなるけれど、やはり碩学は信頼できる。フランクリンは到着後ただちにルイ16世の外務大臣ヴェルジェンヌ、マルゼルブなどの開明的な貴族、その他、要所要所の重鎮に面会を求め、気むずかしいデファン夫人のサロンを表敬訪問し、フリーメイソンの人脈をつてにパリの郊外だったパシーに居を構え、科学アカデミーを定期的に訪れては議論や実験に参加して、わかりやすいフランクリン・ブームの熱気をかき立てた。 アメリカが国家として承認される以前に「アメリカ人」なるものは存在しないはずなのだが、フランクリンはいわば先取りの「国民性」を造形してみせた。明朗、誠実、謙遜、勤勉、知的好奇心・・・・・・、旧大陸の疲弊した国民が、若き新大陸の国民に期待する美徳やイメージを、さりげなく、完璧に演じてスタール夫人のいう「ソシエテ」を魅了したのだとわたしは思う。服装などもアメリカ式を押しとおした。国交樹立と同盟条約調印を機に、ルイ16世から謁見を賜るという一生の晴れ舞台にも、あの禿頭のまま、鬘なしでヴェルサイユ宮殿にあらわれた。「フランクリンさまは、おつむが大きすぎてフランス製の鬘に入らない」という噂は、いかにもサロン向き、恰好の話題になった。そして、女心をくすぐるエピソードの極めつきは、エルヴェシウス未亡人へのプロポーズ。 啓蒙思想家エルヴェシウスは冨と名声、美しい妻、世紀最高の知的人脈にめぐまれながら1771年に他界した。しかしサロンを主宰する女性にとって夫は必需品とはかぎらない。機転が利いて財力があれば威光は陰らないのである。フランクリンは目ざとく状況を見てとって、文明の都パリで進歩思想の温床とみなされる一流サロンの常連となり、その女主人に恋を仕掛けたのだった。問題の恋文、というより正確にはプロポーズを断られた直後の手紙だが、さすがに全文を律儀に翻訳するいとまはない。おおよそのところは、こんな感じである。 「人文学の遠めがね」というタイトルで、ブログを開設することになりました。どうぞ宜しく。お隣さんである「憲法学の虫眼鏡」にあやかろうというさもしい魂胆がないとはいい切れませんけれど、ただのパロディというわけでもありません。 発想の源はプルースト。『失われた時を求めて』の大団円『見出された時』の終幕にある語り手の述懐を、わかりやすくまとめておけば、こんな具合です。――書きためた作品のエスキスを人に見せても誰もわかってくれない。私が聖堂に刻みつけようと考えている真実については、それなりに理解してくれる人でも、よくぞ「顕微鏡」でそんなものを発見したと褒めるだけ。だが、じつのところ、私は「望遠鏡」を使っているのである。なるほど私が捉えているのは、とても小さな物体のようではあるが、それはとてつもなく遠いところにあるせいで、じつはそれぞれがひとつの世界をなしている。つまり私は「望遠鏡」を使って大きな法則を探し求めているのだが、にもかかわらず、どうやら手元の細部をほじくり返す人間とみなされているらしい。 というわけで、わたしの「遠めがね」が向けられている先は、とりあえず革命期のフランスです。でも、なぜフランス革命なのか? 現代日本の国会議員の女性比率が189カ国中147位(世界・国会の女性議員割合ランキング:2015IPU版)などという言語道断な数字を見るにつけ、深刻に考えこんでしまうのです。「戦後民主主義」を謳歌して育ったはずの世代は――今や現役を退いて10年以上になるわたし自身をふくめ――これまで何をしてきたのだろう? 国会や政党だけの話ではない。企業にせよ、研究機関にせよ、そもそも女性がしかるべきポストにしかるべき比率で配置されていない組織において、男女共同参画社会にふさわしい「民主主義」が機能するでしょうか? 求められているのは大きな展望にもとづくラディカルな決意です。 さて「黄泉の国の会話」というアプローチが「遠めがね」の比喩にふさわしかどうかは定かではありませんが、以下はフランス革命とナポレオン独裁を生きぬいたスタール夫人と架空のわたし自身であるKYとのおしゃべりであります。ちなみに死者との対話という設定は、ヨーロッパでは伝統ある文芸のジャンル。ダンテもそうだし、プルーストには、少女たちが作文の課題で「ソフォクレスが黄泉の国からラシーヌに送った手紙」を考案するという微笑ましい話がありました。 *
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.