|
デレク・パーフィットによると、われわれが日常的に想起し、従おうと心がける義務の多くは、自分と特別な関係にある人々に対する義務、つまり家族や友人、恩人や同志、同僚などに対する義務である。こうした濃密な人間関係における義務は、希薄な関係しかない人一般に対する義務に優越する(Derek Parfit, Reasons and Persons (OUP 1984), p. 95)。 10年以上前になるが、筆者は基本権保障に関する内国人・外国人の区別は、濃密か希薄かという違いで説明できるかという問題を検討したことがある(拙著『憲法の理性』(東京大学出版会、2006)第8章)。結論はこの違いでは説明できないというものであった。各国政府が自国民の基本権保護を第一義的に任務とするのは、それが地球全体として人権保障をはかるための効果的手段だからである。あくまで人一般を対象とする希薄な義務を実現しようとしている。 濃密か希薄かというこの問題をもう少し考えてみよう。議論を単純化するために、濃密な人間関係で当てはまる義務を倫理(ethics)、希薄な人間関係で当てはまる義務を道徳(morality)と呼ぶことにする。つまり、倫理は道徳に優先する(Avishai Margalit, On Betrayal (Harvard University Press, 2017)の言葉遣いを借用しています)。 日本の民事訴訟法・刑事訴訟法は、証人尋問において、近親者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができるとする(民訴196条、刑訴147条)。人一般としては証言すべき義務がある。しかし、近親者が罪に問われるおそれがあるときは別である。 教科書類では、こうした場合でも証言を強制するのは情において忍びないし、強制しても真実を語る保証がないからという説明がされている。つまり、本当は人一般の義務に従って真実を語るべきなのだが、こうした特殊な事情の下では、非合理的な「情」に支配されるために、人としての本来の義務を果たすことができないから、というのが根拠だということになっている。法の観点から見れば、そうなのかも知れない。しかし、親兄弟が罪を問われることになっても、必ず真実を述べることが人としての本来のあり方と言えるのだろうか。 いざというとき、仲間を助けるために、人は嘘をつくことが許されるのかという問題について、カントとバンジャマン・コンスタンが交わした論争が知られている。仲間を殺害するためにやってきた者に「あなたの友達はお宅にいますか?」と問われたとき、カントは嘘をつくべきではないという。これでは、人一般に妥当する道徳を硬直的に適用しすぎているとコンスタンは批判する。
カントはあくまで人一般に妥当する普遍的道徳原則──嘘をつくべきではない──について語っているかのようであるが、果たしてそうなのだろうか。2人が念頭に置いていたのは、フランス革命のさなか、恐怖政治が猛威をふるっていた状況である。根底的に異なる政治体制の建設を目指す党派が暴力的に対立し、市民同士の密告を通じて「反革命分子」が即決裁判で死刑を宣告され、ギロチンで次々に処刑されていた状況である。コンスタンは、こうした状況で「密告」を認めることがいかに反倫理的かを糾弾する。カントは、いずれが正義とも見極めがたい状況で、各人が党派ごとに法を私物化することの危険性を指摘する。公権力をどこまで信用することができるかが、二人の立場を分けている(拙著『憲法の論理』(有斐閣、2017)第6章)。 カントも道徳と倫理とが衝突する場面で、つねに道徳を優先させるべきだと主張したわけではない。道徳的判断主体そのものの破壊を意味する自殺は、普遍的道徳原則に反するとした後で、カントは、フリードリヒ大王が戦場に赴く際、戦い利あらず捕虜となって領土の割譲を迫られる場合に備えて、自殺薬を携行していたことを指摘する(『人倫の形而上学』A423)。濃密な関係にある我が臣民への義務を遂行するためには、普遍的道徳原則に反する選択も止むを得ない場合がある。 倫理は、弁護士と依頼人の関係のように、濃密でないドライな関係においても議論されることがある。しかし、それは類比に基づく派生的な用法である。あたかも濃密な関係があるかのように擬制した上で、弁護士に守秘義務を課す。そうすることが、依頼人の利益にもなり、当事者間の効果的な攻撃防御を通じて、より公正な帰結を導くことにもなる。究極的に弁護士の義務を支えているのは、希薄な関係にある社会全体の利益であって、依頼人との濃密な関係の維持ではない。同じことは、医者や薬剤師と患者、ジャーナリストと取材源の関係についても言える。 濃密な関係で妥当する本来の倫理は、社会全体の利益とは無関係であろうか。大部分の人が身近な人との倫理を大切にする社会は、そうでない社会と比べれば善い社会であろう。関係を大事にしてもらえる人は、そうでない人に比べればより幸福であるはずである。そうした少しずつの幸福が積み重なれば、社会全体としても大きな幸福となる。そうした意味では、社会全体の利益と無関係ではない。しかし、社会全体の利益を実現するためにこそ身近な人との倫理を守るべきだという言い方は、倫理の意義を歪める。人が濃密な関係を取り結ぶのは、プラス・マイナスの計算上、プラスになる蓋然性が高いから、という利己的な理由に基づくわけではないはずだからである。 もちろん、一方当事者にとって大幅なマイナスがきわめて長期に及ぶような関係であれば、持続可能性は乏しい。しかし、ときにはプラス、ときにはマイナスとなっても、深い絆が維持されること、それ自体が善(good)であるからこそ、人は濃密な関係を取り結ぶ。幸運に恵まれるときも、逆境に置かれるときも、絆を大事にする。 親子関係のように、自身が選択し得ない関係であっても、人は絆の濃淡を選ぶことができる。実の親子関係が必ず濃密だというわけではない。自己情報コントロール権としてのプライバシーが生きる上で持つ重要性も、こうした絆を取り結ぶ(または取り結ばない)人の能力を支えていることにある。 類比に基づく派生的な用法は、本来とは反転した意味合いを持つこともある。政治家の倫理や公務員の倫理がそうである。 政治家も公務員も、選挙で選ばれるか否かの違いはあれ、社会全体の公益に貢献することが求められる。希薄な関係しかない国民一般への貢献が求められる。身近な家族や親友のために行動すること、濃密な関係を取り結んだ人々のために政治権力や法的権限を行使することは、「反倫理」的である。自分自身の出世や保身のために政治権力や法的権限を行使するのと同じ程度に倫理に反する。優先すべきなのは社会全体におよぶ希薄な関係であって、濃密な関係であってはならない。 政治家や公務員について、公と私との整理・区分が強く求められるのは、そのためである。「私」の領域では、彼らであっても、濃密な関係が希薄な関係に優先するであろう。「公」については違う。優先すべきなのは、あくまで社会全体の利益であり、法(の文面だけでなく精神)に即した権力の行使である。こうした道徳と倫理の関係は、特別である。市民一般について言えば、倫理が道徳に優先するのが原則なのであるから。 実際には、政治家や公務員であっても、濃密な人間関係を優先させたいと思いがちなものであろう。彼らも人間である。それが分かっているからこそ、政治家や公務員特有の反転した倫理と潔癖さが求められる。だからこそ、周囲の情況から推測して、特有の倫理に反する判断がなされたのではないかと人は疑いをかける。「李下に冠を正さず」ということわざが示しているのも、こうした意味の反転した倫理状況である。 濃密な人間関係で結託した集団が官邸や官僚機構を、さらには一部のマスコミまでも占拠し、社会一般に対して権力行使の説明責任を果たそうとしないとき、公権力は私物化され、人と人との私的な絆を梃子に、正統性の蒸発した剥き出しの権力が振るわれる封建制度がよみがえる。つまるところそれは、組織的犯罪集団(マフィア)による政治である。今の日本はそうなりつつあるのではないだろうか。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

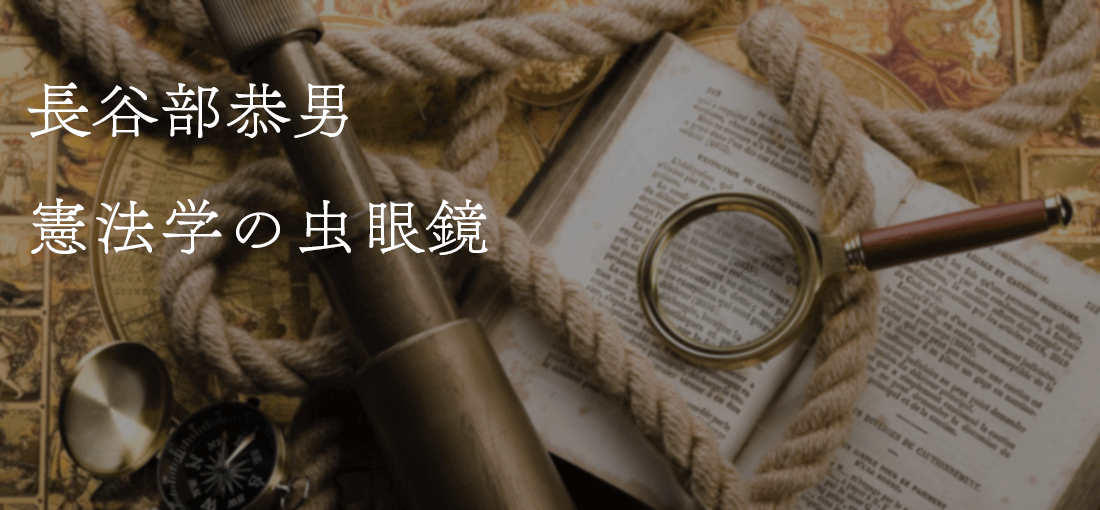
 RSSフィード
RSSフィード