|
日本の最高裁は、法令を違憲と判断することが稀であることで世界的にも知られている。数少ない法令違憲判断の中に、1987年に下された森林法違憲判決がある。 この判決では、持分価額が2分の1以下の森林の共有者は、共有林の分割を請求することができないとする森林法の規定が問題となった。共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるとする民法256条に対する特則となっている。たとえば、ある森林を2人で半分ずつ共有している場合、いずれの共有者も、持分価額は2分の1なので、分割請求ができないことになる。 最高裁の大法廷は、この森林法の規定には、森林経営の安定を図るという立法目的に照らして、必要性もなければ合理性もないことが明らかだとして、財産権を保障する憲法29条に違反するとした。この場合、本則にもどって民法256条の規定する通り、森林法の共有者は持分価額が2分の1以下でも、分割請求ができることになる。分割すれば、それまでの2分の1ずつを2人がそれぞれ単独所有することになる。 この判決で興味深いのは、物の所有のあり方は、単独所有が原則だと最高裁が明言していることである。なぜかというと、「共有の場合にあっては、持分権が共有の性質上互いに制約し合う関係に立つため、単独所有の場合に比し、物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれることがあり、また、共有者間に共有物の管理、変更等をめぐって、意見の対立、紛争が生じやすく、いったんかかる意見の対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなる」からである。そして、「共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめ、[物の経済的効用を十分に発揮させるという]公益的目的をも果たすものとして発展した権利」である(下線筆者)。 単独所有が原則であるからこそ、共有物の分割請求権を制限すると、憲法の保障する財産権を制約していることになるし、必要性と合理性において十分に正当化されない限り、そうした憲法上の権利の制約は違憲となる。違憲とされれば、実定法の状態は単独所有が原則とされる民法256条の規定通りの状態に回帰することになる。いわゆるベースラインへの回帰である。 さて、単独所有こそが近代市民社会における原則形態である理由として、最高裁が提示する議論は、中世カトリック神学をかじったことのある人間であれば、どこかで読んだことがあるなと思うものでもある。
旧約聖書に収められた『創世記』は、その冒頭で、神による天地創造を物語る。地と海と、日と月と星と、鳥と獣と魚を創造した神は、最後に、次のように言う。「われらの像〔かたち〕に、われらの姿に似せて、人を造ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地上を這うすべてを支配させよう」。男と女を創造した神は、彼らに言う。「生めよ、増えよ。地に満ちてこれを従わせよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ」。 つまり、地上のもの、海の中のもの、空を飛ぶものはすべて、全人類に与えられている。この世のものはすべて、そもそもは、全人類の共有財産であった。特定の誰のものでもなく、誰のものでもある状態、入会地のような状態である。村の誰もが、柴をとって薪とすることができ、草を刈って家畜の餌にすることができる。ウサギや鹿を捕まえて、晩御飯のおかずにすることができる。当初は、この世のすべてが、そうした状態にあった。 ところが、その当初の状態は長くは続かず、地上は「これは私のもの、それはあなたのもの」という形で、それぞれに単一の所有者が定まる所有制度がおおうようになる。自然法である共有状態に代わって、人為的な所有制度が設営される。 トマス・アクィナスは、こうした所有制度の設営も、必然とは言えないが、認められてはいると言う。なぜなら、「第一に、誰でも、全員のものや多数に属するようになるものよりは、自分だけのものとなるものを、より熱心に手に入れようとするものだから。・・・第二に、それぞれが自分のものを配慮するようにした方が、物事は秩序立って行われ、あらゆる者があらゆるものの面倒を見ることとなると、混乱が生ずることになるから。第三に、それぞれが自分のもので満足するならば、人々にとってより平和な状態が確保されるから」(『神学大全』IIaIIae66)。 アダムとイヴが神の命に背いて罪を犯したために(具体的に何をしたか、詳らかには説明いたしませんが)、人の本性は利己的となって、全体のためにすすんで働こう、配慮しようとはしなくなった。堕罪後の社会では、単独所有の状態が、各人にとっても、また社会全体にとっても、より好ましい状態となる。物事の管理・運営もより善く配慮・調整され、紛争が起こる蓋然性も減る。 とはいえ、単独所有が支配する状態は、そもそもの自然法には適っていない。当初の自然法の下では、この世のすべては全人類の共有物であった。十分な理由があるならば、それを人為的に変更することも可能だというだけである。そうであれば、単独所有への人為的変更を支える理由が当てはまらない状況では、当初の自然的正義の状態が復活してしかるべきである。また、単独所有が支配している社会においても、その背後にはつねに、本来的にはすべてのものはすべての人の共有であるという状態が伏在している。さらに言うならば、私は何も所有することなく、生きていくという選択の可能性も開かれている。 たとえば、日照りが続いて井戸のほとんどが涸れ、今や飲み水を汲むことのできる井戸は1つだけになったとしよう。その井戸はメリッサが所有している。所有者である以上、メリッサはその井戸も、また井戸から汲むことのできる水も、彼女自身で自由に処分することができるのであろうか。彼女と彼女の家畜だけが水を飲み、他の人々には決して分け与えることはないという選択も、許されるのであろうか。前述の神学的所有制度観からすれば、そうした選択は許されない。 イエス・キリストが生きた社会は、単独所有が支配する社会であった。「これは私のもの、それはあなたのもの」という区別がはっきりしていた社会である。しかしイエスは弟子たちに言う。「道中は1本の杖のほかには何も携えないように。パンも、革袋も持たず、帯の中には銅貨もいれず」(『マルコによる福音書』6:8)。 イエスがそう命ずる相手は弟子だけではない。「行って、自分の持っているものを売り払って、貧しい者たちに与えなさい。そうすればあなたは、天に宝を持とう」(『マルコによる福音書』10:21)。 何の財産もなく、何の蓄えもなしでは飢え死にしてしまうのではないか。しかし、飢えたとき、麦畑の中を通るとき、麦の穂をつんで食べることはできる。それが安息日であっても(『マルコによる福音書』2:23-28)。また、過越の食事を裕福な人に用意してもらうことはできる(『マルコによる福音書』14:12-16)。 このように、自分の財産ではないものを費消することも認められている。当初の自然法からすれば、すべてのものはすべての者の共有物である。社会の実定法(人為法)からすれば、食事を恵んでもらうよう、人に要求すること、裁判を通じて請求することはできない。そんな権利は実定法が認めるところではない。しかし、神の法からすれば、人の食べ物であっても、緊急の際には、飢えをしのぐためにそれを食べることは十分に正当である。 以上のような伝統的な物の所有と費消に関する考え方からすると、ジョン・ロックが『統治二論』で唱えた「自然権としての所有権」という観念がいかに革命的であったかがよく分かる。ただ、そのロックも、出発点においているのは、この世のすべてのものが全人類の共有財産である自然状態である。人は神から自分の身体を固有のものとして与えられている。その身体を動かして(労働して)全人類共有のものを自分のために取り出すとき、たとえば魚を釣る、ウサギや鹿を狩る、土地を耕して麦を収穫するとき、自分の労働と全人類の共有物は混和し、そうして得られた物は、自身の固有の財産となる。 もっともロックは、人が労働を通じて自身の固有の財産を全人類の共有財産から切り出すとき、「少なくともほかに他人の共有のものとして、十分なだけが、また同じようによいものが、残されている限り」という前提条件を付けている(『統治二論』第2篇第5章第27節)。たとえば、ある人が海で魚を釣ると、その結果として、その海の魚すべてがその人のものになるわけではない。議論の基本的構造が、トマス・アクィナスの議論と大きくことなるわけではない。しかし、ロックによれば、個々人が手に入れた財産は、固有の自然権であり、それを政府が侵害すれば、抵抗権の発動さえ正当化される。 日本の法学者の中には、ロック流の「自然権としての所有権」という観念に慣れ親しんだ人は多いようだが、彼が革新した伝統的な所有観念に言及する人は少ない。しかし、森林法違憲判決で最高裁が依拠しているのは、デイヴィッド・ヒュームに受け継がれた伝統的な所有観念のようである。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

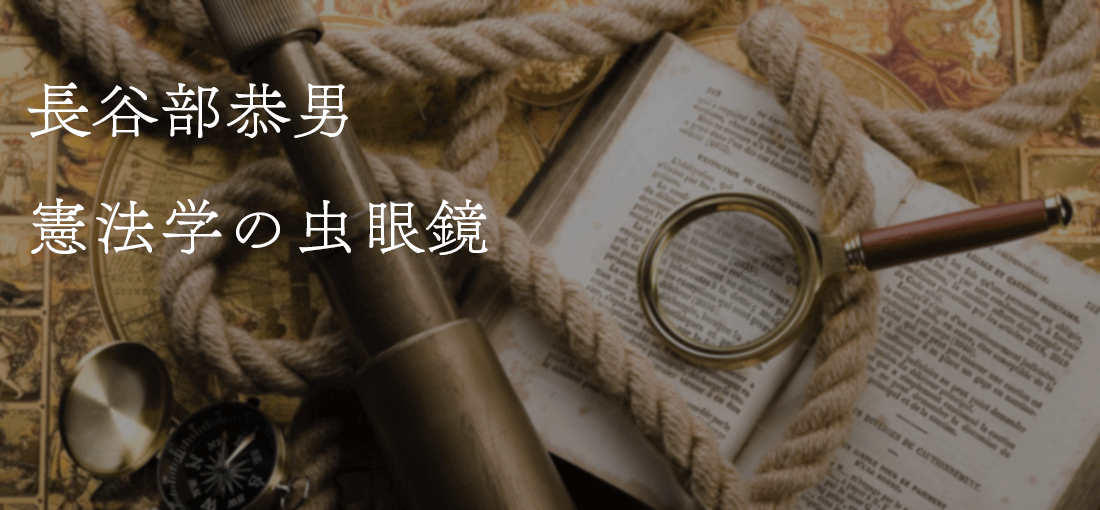
 RSSフィード
RSSフィード