|
イスラエルの「人間の尊厳と自由に関する基本法」は、全体として見れば、ごくありきたりの権利宣言である。あらゆる人の生命、身体、尊厳ならびに財産は保障される。人身の自由もイスラエル国籍を離脱する自由も保障される。プライバシーと住居の不可侵も保障される。基本法は、憲法典がそうであるように硬性化はされていない。しかし、イスラエル議会(the Knesset)が、基本法に反して立法する意思を明示しない限り、基本法に反して権利を侵害する法律は無効とされる。 ときおり議論を誘発するのはその第1条である。同条は、イスラエルが「ユダヤ的民主国家 a Jewish and Democratic state」であると規定する。 問題は、ここでいわれている「ユダヤ的国家」とは何を意味するかである。いろいろな回答が考えられる。(1)ユダヤ教がイスラエルの国教として樹立され、国民すべてがユダヤ教を信仰すべきことを意味するのか、(2)ユダヤ教徒あるいはユダヤ教徒でないとしてもユダヤ人であるイスラエル国民が、他の国民より優越した地位を占めること(つまり、イスラエルには一級市民と二級市民がいること)を意味するのか、(3)基本法が規定するありきたりの普遍的な諸価値のほかに特殊ユダヤ的諸価値があり、後者はときに普遍的諸価値と衡量され、特殊ユダヤ的価値のゆえに普遍的価値が切り下げられることもあるということか。 最高裁長官として長くイスラエルの司法界を率いてきたアーロン・バラク判事によると、この「ユダヤ的国家」という概念が意味しているのは、(1)から(3)のいずれでもなく、イスラエルがユダヤ教の基本的諸価値を擁護する国家であることである。その基本的諸価値とは、「人類への愛、生命の神聖性、社会正義、衡平、人間の尊厳の保護、立法府をも対象とする法の支配等」である(Aharon Barak, ‘A Constitutional Revolution: Israel's Basic Laws’ (1993). Yale Law School, Faculty Scholarship Series. Paper 3697)。 要するにまっとうな民主国家であれば、どこであれ尊重される普遍的諸価値を擁護する国家であることを意味していることになる。法哲学者のジョゼフ・ラズが指摘するように(Joseph Raz, ‘Against the Idea of a Jewish State’, in The Jewish Political Tradition, Michael Walzer et al. (eds.) (Yale University Press, 2000), pp. 509-514)、これが「ユダヤ的国家」の意味であれば、現在のフランスも「ユダヤ的国家」であろう。おそらく現在の日本も「ユダヤ的国家」である。世界を見渡したとき、たしかに「ユダヤ的国家」であるかどうか疑わしい国々もあるが、それは要するに、(その国の憲法典に何が書かれているかは別として)普遍的とされる諸価値を実際に尊重しているとは言えない国家だということである。 バラク判事がここで行っているのは、基本法の規定の「解釈」である。多くの場合、解釈は条文を出発点とする論理的推論ではない。とりわけ憲法典やそれに類する基本法典の場合、条文の通常の意味内容が(普遍的)道徳に照らして不当な論理的帰結をもたらす場合に、むしろ普遍的道徳に訴えかけることで、その不当性を打ち消すために行われる。
バラク判事が行った解釈は、「ユダヤ的国家」という文言の意味内容をほとんど消去するような解釈である。いかなる国であれ、普遍諸価値を擁護する国家であれば「ユダヤ的国家」だというわけであるから。 では、こうした解釈は不当な、許されざる解釈かと言えば、そうではないとラズは指摘する。「ユダヤ的国家」という文言が道徳的に見て不当な帰結をもたらさないためには、つまり上記の(1)から(3)のような帰結をもたらさないためには、「ユダヤ的国家」という文言の意味内容をすべてくり抜くことは、必須の作業であった。 それでもこの文言になお意味を認める第4の解釈の可能性はあるのではないか。普遍的諸価値は擁護せざるを得ない。その国独特の価値によって普遍的諸価値を切り下げることもできない。しかし、普遍的諸価値の擁護の仕方は、時と所によって多様であり得るのではないだろうか。国ごとにたどってきた歴史が異なる。経てきた経験も異なる。それを反映した現在があり、未来がある。同じ民主国家と言っても、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアそれぞれの民主主義のやり方があるように、違憲審査の方法にも国ごとに違いがあるように、イスラエルにはイスラエルなりの普遍的諸価値の擁護の仕方があるのではないか。 ラズは、そんな解釈の可能性はないと言う。普遍的諸価値の擁護の仕方がいろいろであること、国ごとに違いがあり得ることは、その通りである。しかしそれは、あまりにも当然のことであって、わざわざ憲法典や基本法で高らかに宣言するようなことではない。そんなことを言い出したら、デンマークは「デンマーク的国家」であり、カナダは「カナダ的国家」であることをそれぞれ宣言しなければならないことになりそうであるが、そんな必要性はどの国も感じていない。結局、バラクの解釈が正当な唯一の解釈だということになる。 自分たちの国には、自分たちでなければ実現し得ない、自分たちでなければ目指すことのあり得ない、独特の価値があるというヒステリックな考え方にとりつかれる人々は、そんなのやめましょうよと言っても簡単にはなくならない。日本の場合で言えば、9条についてそうした考え方に執着する人が多いようである。日本だけの経験がそこにあること、それを反映した運用が積み重ねられてきたことは、その通りである。しかし、目指すべき未来、念頭に置くべき理念に、日本独特のものがあるかと言えば、それはどうであろう。 あるいは、憲法を改正して、親を敬うように、子どもを大事にするように、家族みんな仲良くするようにと書き込んだらどうかと主張する人々もいる。自分の権利ばかり主張して義務をおろそかにする風潮は我慢ができないという心持ちが背景にあるようである。 多くの憲法典や権利宣言が権利を規定する一方で義務についてはあまり語らないのはなぜか。いろいろな理由があるが、その一つは、普通の人々がまず念頭に置くのは自分の義務であって権利ではないことにある。権利よりははるかに義務が、人が生きる意味を形作っている。生きていく中で自分が引き受けてきた義務、親として、伴侶として、仕事仲間として引き受けてきた義務こそが、人に生きる意味を与えることが普通であろう。体力を超えてでも、精神的に追い詰められても、なお働こうとする人がいる理由の一部はそこにある。権利は各人の意識においてさえ、おろそかにされがちだからこそ、権利をわざわざ宣言することに意味がある。 また、大切な義務は各自が自分のものとして本当に引き受けない限り、当人にとって意味を持たない。憲法典や権利宣言に義務を書き込むことにさしたる意味がないのも、そのためである。勤労する義務を憲法に書いたからと言って、よし働こうとは、人は普通、思わない。自分の仕事をこれと見定めて引き受け、それを日々こなしていく中で、自分の仕事に対する責任感が生まれ、誇りが生まれる。「仕事に誇りと自信を持て」と人に言われたり、憲法に自分の仕事をわざわざ書いてもらったりして生まれるものではない。 結局のところ、日本は日本なりのやり方で「ユダヤ的国家」であることを目指し、そうであり続ける努力をする。それしかないように思われる。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

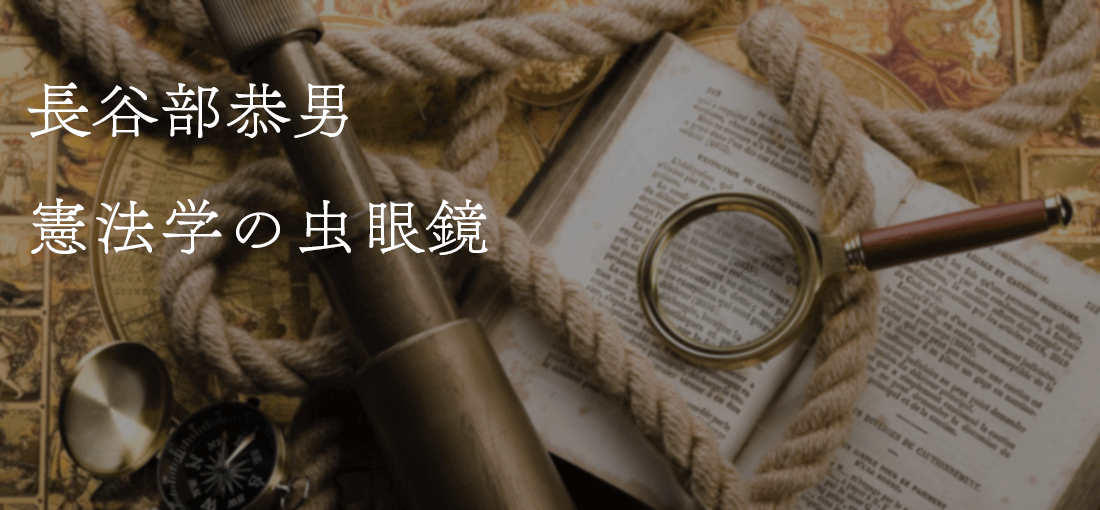
 RSSフィード
RSSフィード