|
Q: 定期試験前の駆け込み質問で申し訳ありません。憲法21条の表現の自由に関する質問なんですが。 A: ああいいですよ。なんですか。 Q: 憲法21条では「一切の表現の自由は、これを保障する」と規定されていますが、わいせつ表現や名誉毀損表現、犯罪の煽動などは刑罰の対象とされています。実際には「一切の表現の自由」が保障されているわけではないことは、誰もが知っていることです。この事態を説明するためには、憲法12条や13条を援用する必要があるのでしょうか。 つまり、憲法の保障する権利は、国民は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(憲法12条)という条項や、国民の権利は、「公共の福祉に反しない限り」において「最大の尊重を必要とする」(憲法13条)という条項を援用しない限り、わいせつ表現や名誉毀損表現が制約されていることは、正当化できないのではないか、ということですが。 A: 憲法の定期試験で不可をとりたくないのなら、そんなことは答案に書かない方がいいでしょう。あなた自身の身のためになりません。 Q: なぜですか? 筋は一応通っていると思うのですが。 A: 現在の憲法学の標準的な解釈では、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動などは、そもそも憲法21条の保護範囲に入っていません。つまり「一切の表現の自由」と言われる「表現」には、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動は、はじめから含まれていないわけです。ですから、これらの活動が刑罰の対象となっていることは、保護された表現の「制約」にもあたりません。したがって「制約」を「正当化」する必要もありません。憲法学の標準的な理解である三段階審査からすれば、当然に出て来る結論です。 この種の表現活動が禁止されていることを「正当化」すること必要自体、そもそもないわけですから、「正当化」のために他の条文を引き合いに出す必要も、もとからないということになります。これは、詐欺や恐喝も表現活動だから、憲法21条で保護されているはずだという議論に対応する必要がないのと同じです。常識を備えた人なら、議論するまでもなく、当然分かるはずのことです。 それから、千歩譲って、かりに表現の自由が本当に制約されていて、その正当化が必要だとしても、広く法的意味はないと受け取られている12条は問題外でしょう。議論する必要がかりにあるとしても、まあ13条でしょうね。 Q: その13条ですが、通説とされる宮沢俊義先生の提唱された「内在的制約説」からすると、憲法13条で言う「公共の福祉」がすべての基本権の制約を説明できるということだったと思いますが。 A: 40年以上前の学説ですね(宮沢俊義『憲法Ⅱ』〔第2版〕が刊行されたのは、1970年である)。憲法訴訟論以前のancient historyに属する学説で、その宮沢説が現在においても通説であるかと言えば、そうではないでしょう。深刻な問題をいろいろと抱えている学説でもありますから。たとえば、わいせつ表現の禁止を人権相互間の衝突の帰結として説明するのは無理ではないかとか。 でも、ここも千歩譲って、かりに宮沢説が正しいとしても、やはり13条があってはじめて基本権の制約が説明できるということにはなりません。宮沢先生の内在的制約説は、憲法13条の言う「公共の福祉」とは、「各人の人権の享有およびその主張に対して、なんらかの制約が要請されるとすれば、それはつねに他人の人権との関係においてでなくてはならない。人間の社会で、ある人の人権に対して規制を要求する権利のあるものとしては、他の人の人権以外には、あり得ない」(憲法Ⅱ229頁)という主張から出発します。そして、この人権相互間に生ずる「矛盾・衝突の調整をはかる」ための「実質的公平の合理」が「公共の福祉」に他ならないという議論でした。 この議論の筋道からすれば、憲法13条に規定されている「公共の福祉」という概念は、実は独立の意味を持っていないということになります。表現の自由が制約されるとすると、それは他の基本権との矛盾・衝突を調整するためでしかあり得ないはずです。名誉権など、他の基本権が保障されているのであれば、それとの調整をはかるために、表現の自由を制約することが求められると言っているだけです。 つまり、憲法13条に規定されている「公共の福祉」は、表現の自由を制約するための独立の根拠にはなっていません。13条がたとえなくとも、憲法上、名誉権があると言えるのであれば、表現の自由との矛盾・衝突を調整した結果として、名誉毀損表現は制約できることになるはずです。宮沢説がたとえ正しいとしても、憲法13条の規定があってはじめて、表現の自由の制約が正当化できるということにはならないわけです。 「内在的制約」ということばを、憲法の規定を根拠として援用しなくてもそういう結論になるという意味合いで使う例は、統治行為に関する最高裁の判例にもあらわれています。衆議院の解散の合憲性が問題となった苫米地事件の判決(最大判昭和35・6・8民集14巻7号1206頁)で最高裁は、高度に政治的な問題について最高裁として政治部門と異なる司法判断をすべきでないことは、「特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきである」と言っているでしょう。「内在的制約」ということばは、憲法上の明文の規定があるか否かとは関係なく存在する制約、という意味で使われるものです。 とはいえ、もともとこんな議論をする必要自体、最初からなかったのですけどね。さっき言った通り、名誉毀損表現は、21条の保護範囲外なんですから。 Q: 話は少し変わりますが、2014年7月の9条の解釈変更に至るまでの政府の有権解釈が、憲法9条の存在にもかかわらず、個別的自衛権の行使は認められると主張していた根拠としては、憲法13条が挙げられているようですね。つまり、9条と13条との矛盾・衝突が調整されているということになりそうです。 A: 田中角栄内閣の下での1972年10月14日の政府見解のことですね。たしかにそこでは、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権限が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置」である限りで、必要最小限度の武力行使としての個別的自衛権の行使は認められる、とされていて、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が念頭に置かれていることは明らかでしょう。ということは、実は、同じ13条で規定されている「公共の福祉」とは全く別の話になっているということでもあります。ちなみに、安倍政権が2014年7月1日に集団的自衛権の限定的行使は認められると、無理やり解釈変更したときも、この「生命、自由及び幸福追求」の権利が根拠として引き合いに出されています。 ただ、ここでもどうでしょう。憲法9条の下でも、日本が急迫不正の侵害を受けたとき、他に選び得る手段がないときに、必要最小限度で実力を行使して対処し得ることは、日本国憲法が立脚している狭義の立憲主義からして、当然のことではないでしょうか。国民の生命と財産を守るという役割は、およそ国家と言い得るものであれば、果たすぞと少なくとも主張はするものでしょう。侵略を受けたとき、何の実力も行使しないで国民の生命・財産を守ることなどできるはずがありません。 外敵の侵略を受けたときも、日本国民としては何らの抵抗をすべきではない。ただ、ただ、殺されるがままになることが、人としての正しいあり方だという考え方は、理論的にあり得ないとは言いませんが、それは相当に強烈な価値観を前提としなければ、支えられない考え方でしかありません。そんな特定の価値観を全国民に押し付けても構わないという立場は、根源的に異なる多様な価値観の存立を前提としつつ、そうした多様な価値観の公平な共存をはかろうとする狭義の立憲主義とは両立しません。ということは、日本国憲法そのものと両立し得ないということです。 日本国憲法公布の同じ日、つまり1946年11月3日に政府が刊行した『新憲法の解説』というパンフレットは、当時の内閣法制局のメンバーが執筆したものですが、その中でも、「自己防衛の手段」としての「自衛権」、つまり個別的自衛権は9条の下でも行使できるという政府の立場が明らかにされています(「新憲法の解説」高見勝利編『あたらしい憲法のはなし 他二篇 』(岩波現代文庫、2013)103頁)。その際には、とくに13条は引き合いに出されていません。 つまり、ここでも、わざわざ憲法13条の条文を援用するまでもないということになります。常識を備えた人なら、当然、9条の下でも個別的自衛権は行使できるという結論を了解できるだろうという話です。 もっとも、こうした議論は、常識を備えた人にしか通用しない議論ではありますが。 * 本稿は、2017年1月19日に平成国際大学で筆者が行った講演(開学20周年記念講演会)における聴衆の質問およびそれへの筆者の応答を再構成したものである。平成国際大学での聴衆の方々に、そして筆者に講演を招請し万端にわたってお世話をいただいた平成国際大学の新島一彦教授に、深く感謝を申し上げたい。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

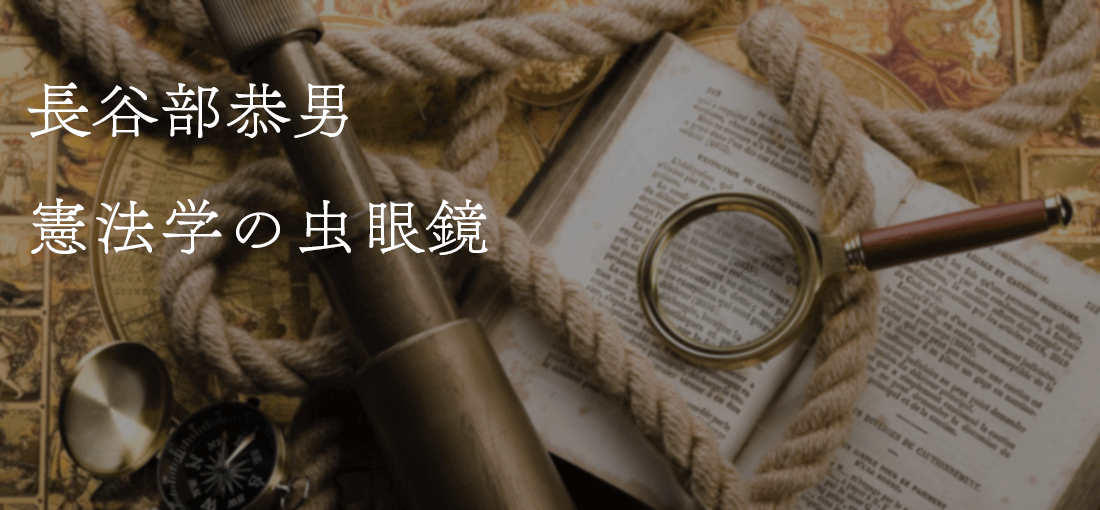
 RSSフィード
RSSフィード