|
憲法についてほかの人と話が通じにくいなと感じるとき、そもそも憲法や法に関するものの考え方が、さらに言えば人や社会に関する見方が、根本から異なっているからではないかと思うことがある。ウィトゲンシュタインが指摘するように、「たとえライオンが人語を話すことができたとしても、われわれは彼の言うことが理解できない。」われわれは、生肉を食らいつつ咆哮する生き物として世界を意味づけることはできない。 実定法や憲法の条文にしろ、有権的(authoritative)とされる各種の解釈にしろ、いずれもどう行動すべきかに関する実践的な判断の補助手段であり、道具である。最終的に判断を下すのは、結局は自分自身である。 実定法は権威であると自己主張することがしばしばある。「あなた方、自分で判断するのはやめて、私の言う通りにして下さい。そうした方が、あなた方が本来すべき行動をよりよくとることになりますから」と主張するものである。大多数の人々が、大多数の人々と同じ行動をとろうと考えている調整問題状況では、実定法を権威として受け止め、その通りにすることで、本来すべき行動をとることのできる場合が多いであろう。実定法が、自動車は道路の左側を通るように指示している社会で、左側を通るようにすれば、事故を起こすこともなく、スムーズに、かつ、安全に自動車を運行することができる。 他方、いついかなる場合でも、必ず実定法の文言通りに行動することが、本来とるべき行動をとることになるとは限らないことも、常識的に考えればすぐ分かることである。人の命がかかっているような緊急の場合に、必ず実定法を遵守して行動しなければならないとは限らない。「この状況で人として本来すべきことは何か」を最終的に判断するのは、いつも自分自身である。実定法の条文は、所詮、実践的な判断の補助手段である。物神として条文を崇め、自分の判断を放棄することは、人であることを放棄することである。 本連載のその14でも指摘したことであるが、憲法典の条項、とくに基本権条項の果たす役割は、民法や刑法や道路交通法のようなごく普通の実定法とは異なっている。基本権条項は、実定法を権威として受け取ることが人としての本来の行動をとることにつながらない場合に、むしろ実定法の権威としての拘束を解除する手がかりとして働く。実定法の条文自体や、それに基づく公権力の行使が、基本権によって保護された利益の制約・侵害となっており、それが十分に正当化されないときは、実定法やそれに基づく公権力の行使は、権威としての拘束力を喪失する。権威要求が解除される。それを第一次的に判断するのは、一般市民であることが多いであろう。この法律に従ったのでは、人として本来なすべきことをしていることにならない。そう判断して法律の要求とは異なる行動をとる。そうした行動をとると、犯罪者として起訴されることもあるだろう。法律の権威要求が解除されることになるか、どのような場合に解除されるのかは、最高裁の判例(有権解釈)に待つべきところが多い。基本権条項は、条文を読んだだけでは、いつどのような場合に実定法の権威要求が解除されるか、ただちに理解することはできないからである。
解釈の手順は、基本権の条項によって異なる。本連載のその1でも紹介したが、森林法違憲判決(最大判昭和62・4・22民集41巻3号408頁)で最高裁は、近代市民社会における所有の原則的あり方、つまりベースラインは、単独所有であるとした。そうすると、共有状態にある財産については、分割が不可能なものでない限りは、共有者による分割請求権の行使を認めるべきであり、分割請求権を制約すれば、それは憲法の保障する財産権の制約だということになる。十分な根拠によって正当化されるのでない限り、そうした財産権の制約は違憲となり、ペースライン(単独所有)への回帰を認める必要がある。最高裁が下したのは、そうした結論である。 表現の自由をはじめとする精神的自由権の場合、ベースラインをとりたてて設定する必要は、普通はない。憲法によって保護された表現活動の制約は、ゼロだというのがベースラインだからである。表現活動の制約が十分な正当化根拠によって支えられないとき、表現活動の制約は違憲となり、ベースラインであるゼロ、つまり制約の撤廃への回帰を認める必要がある。 憲法9条については、これを普通の実定法であるかのように扱うべきだという理解と、基本権条項と同様に取り扱うべきだという理解とがある。筆者がとっているのは、後者の立場である。 普通の実定法と同様に扱うとすると、9条の条文が何をせよ(何をするな)と言っているかを文言に即して理解する必要があるが、9条の文言は、普通の日本語としては理解しにくいところがあるし、1項と2項を合わせた全体を整合的に理解することも容易ではない。そもそも「国際紛争を解決する手段」とは何を意味しているのだろうか。 この点については別稿を準備しているので詳しくはそちらに譲るが、結論だけを述べると、9条はグロティウスの提示した戦争観──国家間の紛争は裁判ではなく、戦争によって解決される──を否定した不戦条約の趣旨を再確認したものである。1項が否定しているのは、国際紛争を解決する裁判外紛争処理手段たる戦争、武力の行使並びに武力による威嚇である。2項前段が「前項の目的を達するため」に保持しないとしているのも、国際紛争を解決する手段としての戦争を遂行する能力(戦力)であり、2項後段が否定しているのは、国際紛争を解決する手段として戦争に訴える権利である。不戦条約の提案者を含めた当時の国際社会の通念からして、個別的自衛権の行使は、否定されてはいない。 このように理解することで、9条は全体として整合的な条文としてその趣旨を読み取ることができると筆者は考える。しかし、これでは納得がいかないという人もいるだろう。長年にわたって維持されてきた、かつての政府の有権解釈とも必ずしも一致しない。 かといって、個別的自衛権の行使を含めてあらゆる武力の行使が9条によって、最終的結論としても否定されていると頑なに考えると、防衛サービスという典型的な公共財の提供に関して、あらゆる実力行使を否定するのが人としての正しい生き方だという私的領域の特定の世界観を全国民に押しつけることになりかねない。それは多様な世界観の公平な共存という近代立憲主義の根本原則と両立しない。 内閣法制局がとってきたのは、9条を基本権条項と同様の原理(principle)として捉える立場であると考えると、分かりやすくなる。戦争はもちろん、武力の行使、武力による威嚇も、ベースラインはゼロである。しかし、最終的な結論としてもゼロのままというわけでは、必ずしもない。ベースラインからの乖離が十分に正当化されるのであれば、その限りで武力の行使も、そのための実力の保持も許される。2014年にいたるまで、長年にわたって政府が維持してきたのは、個別的自衛権の行使については、9条の下でも十分に正当化できるし、したがってそのための実力組織(自衛隊)の保持も許されるというものであった。 もちろん、有権解釈という権威も、いついかなる場合でも、つねに権威として受け取るべきかと言えば、そうではない。十分な、しかも最終的にもそうすべきだという理由に支えられるのであれば、解釈を変更すべき場合も決してないとは言えない。安倍内閣による2014年の解釈変更が激しく批判されているのは、変更すべき十分な理由がそもそも示されていないからである。 法も憲法も、所詮は実践的判断を補助する手段にすぎない──こうしたものの考え方は、法や憲法の権威を掘り崩し、その拘束力を脆弱化する危険性を孕んでいるかも知れない。9条にはいついかなる場合でも妥当する永遠に変わらぬ意味があるという立場の方が、拘束力は堅固であろう。しかし、いかに行動すべきか、それを最後に判断するのは自分自身であるという出発点は変わるはずがない。そうである以上、危険と隣り合わせで生きていくしかない。人であることをやめるのでない限り。 本稿は当初、別の内容を扱う予定であった。筆者がゲーム理論の複数のモデルを使用している点を強く非難する文章に出会ったことがきっかけである。たとえば、20年以上前に執筆した拙稿「国家はそもそも必要なのか?」(『比較不能な価値の迷路〔増補新装版〕(東京大学出版会、2018)』所収)は、複数のゲーム理論のモデルを使用している。 この論稿は(その他の同種の拙稿もだいたいそうなのだが)、一読していただければお分かりの通り、国家権力の正当性の有無から憲法9条に関するさまざまな立場にいたるまで、それぞれの議論がどのような前提に立脚していると考えれば筋の通ったものとして理解可能かを、距離を置いた視点から描写しているだけである。こうした分析を通じて、なぜこれらが相互に両立不能であるか、その理由を明確にすることができる。立場が異なれば、個人間・国家間の利害状況の見方や国内の政治過程の見方も異なり、対応するゲーム理論のモデルも異なる。前提の違いに応じて複数のモデルを使うことになるのは、当然のことである──という趣旨の原稿を書き始めたのであるが、なぜこんな分かり切ったことをわざわざ説明しなければならないのかとバカバカしくなったので、それに代えて、実定法や憲法の道具性についてのご覧のような原稿にした次第である。本連載その10と内容が相当に重なり合う結果となっている。 法や道徳に関わる問題では、具体の結論と前提となる一般理論との間を行きつ戻りつしながら、議論が組み立てられること(reflective equilibrium)が常ではある。しかし、具体の結論にこだわるあまり、法とは何か、憲法とは何かに関する根本の観念をゆるがせにするわけにはいかない。 真実という一つの価値のみに仕える認識上の理由と異なり、実践的理由はしばしば相互に両立しない多様な諸価値に仕える。実践的思考の補助手段である法、憲法、原理、準則等が、結局は「部分的な」理由にとどまるのはそのためである。特定の条文が、具体の場面において考慮すべきあらゆる諸価値に満遍なく適切に仕えることはあり得ない。 憲法も原理も、結局は理由によって支えられ、支えられる理由によって射程が限定される。いかなる法も憲法も原理は、人がいかに行動すべきかを究極的に決定するわけではない。決定するのは理由である。いかに行動すべきかの判断を実定法や憲法の規定に丸投げすることは、人であることを放棄することである。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

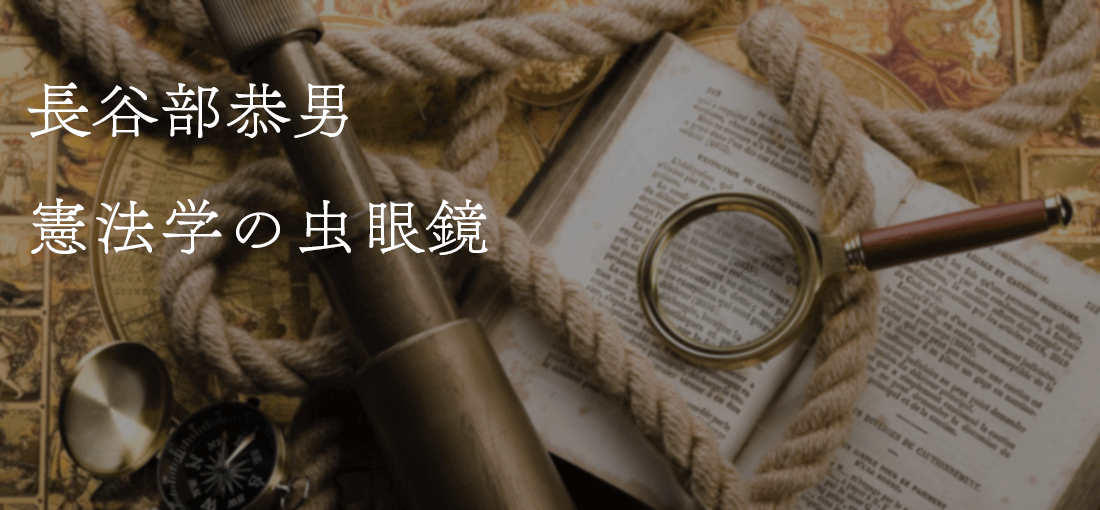
 RSSフィード
RSSフィード