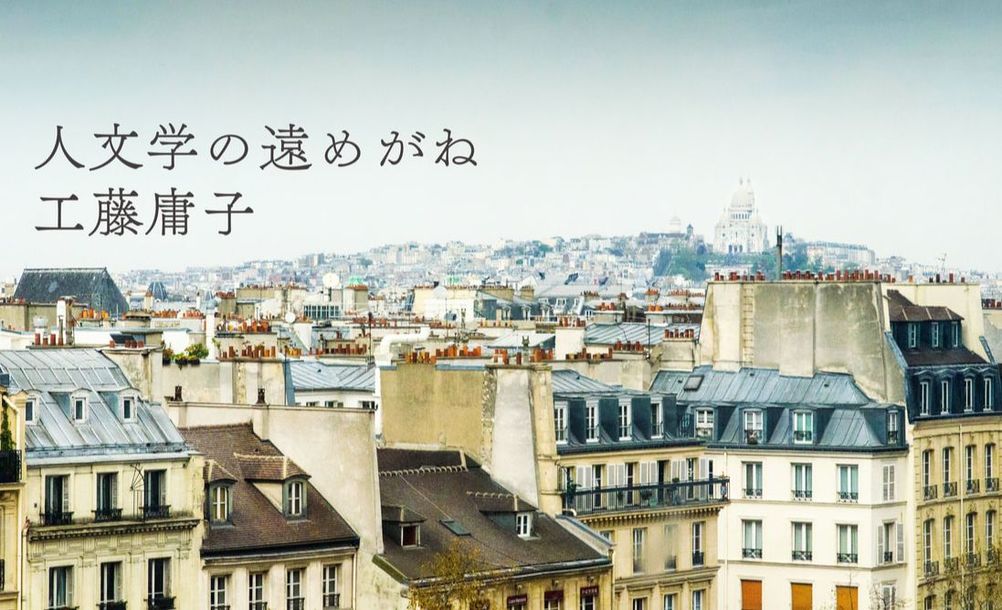|
スタール夫人のテクストで巧みに使われる雷と電位差のメタファーがきっかけで「パリのアメリカ人」のことを考えはじめたのだった。革命前のフランスのサロンには、フランクリン・ブームと呼べるものがあったにちがいない。 1776年7月4日、アメリカ13州の独立宣言が採択された。一方的に「国家」を名乗った若々しい政治勢力を代表し、ベンジャミン・フランクリンがフランスに向けて発ったのは、その年の暮れ。イギリス軍と植民地軍との武力衝突は容易に決着が着きそうにない情勢下、3名の使節団に託された喫緊の課題は、独立軍に対する物資や資金の援助をとりつけ、旗幟を鮮明にした軍人や義勇兵の個人的な参戦を促すことだった。フランスにしてみれば、7年戦争に敗退して植民地を奪われたばかりの英国に荷担するのは非現実的な選択だったけれど、ただでさえ逼迫した国庫に負担をかけてまで他国の争いに介入する必要はないし、そもそも君主制の国家が共和制をめざす反乱軍の味方になれば自国の不安定化を招く、という主張は正論だった。ただし、かりに英国が勝利して北アメリカを傘下に収めれば、目前に世界帝国という脅威が出現することになる。 正攻法で国家間の交渉を提案する正統性をもたぬフランクリンは、アメリカの「革命」に共鳴する「世論」を形成し、搦め手からも外交に働きかけようと考える。手品のような早業でサロンの寵児になることは、短期決戦の戦略的要請でもあった。赫々たる成果は年譜で確認できる。1778年、米仏同盟条約に調印。1779年、駐仏全権公使となり、1781年、対英講和会議代表、1783年、米英の戦争終結にかかわるパリ講和条約締結。宗主国イギリスをはじめ、ヨーロッパ諸国との折衝においても、フランクリンの外交的手腕と人格的な信望は圧倒的なものだった。アメリカに帰国して5年後の1790年、訃報が伝わるとフランスの国民議会は3日間の喪に服した。 それにしたってサロンの寵児などというものは、なろうと思ってなれるものではない。ここで参照するのは、マルク・フュマロリの『ヨーロッパがフランス語を話していたころ(*1)』という著作。タイトルを見ただけで、所詮はグローバル言語幻想だろうと敬遠したくなるけれど、やはり碩学は信頼できる。フランクリンは到着後ただちにルイ16世の外務大臣ヴェルジェンヌ、マルゼルブなどの開明的な貴族、その他、要所要所の重鎮に面会を求め、気むずかしいデファン夫人のサロンを表敬訪問し、フリーメイソンの人脈をつてにパリの郊外だったパシーに居を構え、科学アカデミーを定期的に訪れては議論や実験に参加して、わかりやすいフランクリン・ブームの熱気をかき立てた。 アメリカが国家として承認される以前に「アメリカ人」なるものは存在しないはずなのだが、フランクリンはいわば先取りの「国民性」を造形してみせた。明朗、誠実、謙遜、勤勉、知的好奇心・・・・・・、旧大陸の疲弊した国民が、若き新大陸の国民に期待する美徳やイメージを、さりげなく、完璧に演じてスタール夫人のいう「ソシエテ」を魅了したのだとわたしは思う。服装などもアメリカ式を押しとおした。国交樹立と同盟条約調印を機に、ルイ16世から謁見を賜るという一生の晴れ舞台にも、あの禿頭のまま、鬘なしでヴェルサイユ宮殿にあらわれた。「フランクリンさまは、おつむが大きすぎてフランス製の鬘に入らない」という噂は、いかにもサロン向き、恰好の話題になった。そして、女心をくすぐるエピソードの極めつきは、エルヴェシウス未亡人へのプロポーズ。 啓蒙思想家エルヴェシウスは冨と名声、美しい妻、世紀最高の知的人脈にめぐまれながら1771年に他界した。しかしサロンを主宰する女性にとって夫は必需品とはかぎらない。機転が利いて財力があれば威光は陰らないのである。フランクリンは目ざとく状況を見てとって、文明の都パリで進歩思想の温床とみなされる一流サロンの常連となり、その女主人に恋を仕掛けたのだった。問題の恋文、というより正確にはプロポーズを断られた直後の手紙だが、さすがに全文を律儀に翻訳するいとまはない。おおよそのところは、こんな感じである。 亡き夫への愛と操をつらぬくという、昨晩の貴女の残酷なお言葉に深く傷つき、死んだようになって床につきましたところ、なぜか、あの世で目が醒めました。
誰か会いたい者がいるか、という問いに対して、せっかくだから哲学者のところに案内してほしいと答えましたところ、ご近所によい住人がいる、ソクラテス氏とエルヴェシウス氏だが、とのこと。それはそれは、お二人には衷心から尊敬の念を捧げておりまする。ただし小生、フランス語は多少たしなむものの、ギリシア語は皆目わかりませぬ、まずはエルヴェシウス氏にお目にかかりたい。といった経緯で、ご主人にお会い致しました。評判は聞いているとかで、丁重に迎え入れてくださり、フランスにおいて戦争は、そして宗教や自由や統治の現状は、いったいどうなっておるか、と細々、お尋ねになりました。――ところで、あなたの大切な方、エルヴェシウス夫人について、なぜお尋ねにならないのです。今もあなたを大層愛しておられますよ、たった1時間前にお邸を辞去したところです。――そのひと言で昔の幸福を思いださせてくださった。しかしね、ここで幸福になるためには、忘却が求められる。当初は彼女のことばかり考えていたが、やがて慰められ、べつの女を娶りました。なるべく似た女を探しましてね、美人という意味ではやや劣るが、良識においては同等、頭のよさではやや優る、そして深くわたしを愛してくれます。いろいろ気を遣ってくれましてね、ちょうど天国特製の美酒を買いに出ておりますが、じきにもどって参りましょう。――どうやらかつての奥さまのほうが、操が固いようだ。何人もの立派な人物のプロポーズを断っておられますよ。かくいう私も白状すれば完全にのぼせあがっているのだが、あなたを愛しているからといって、すげなく断られました。――〔同情したエルヴェシウスが、経験者として口説きのコツを教える十数行を省略〕――そのとき、天国の美酒をたずさえた新エルヴェシウス夫人が入ってこられた。その瞬間に、フランクリン夫人であることがわかった、つまり、かつてアメリカで私の大切な人だった人ですよ。私はただちに返還を要求しました。ところが彼女は冷たくいいはなったのです。あたしは49年と4カ月、半世紀近くも、あなたの妻だったのよ。それで満足しなさいよ。こちらで生まれた新しい絆は、あいにく永遠につづきますの。 愛しき妻の拒絶に遭って、私はただちに心を決めた、こんな裏切りにみちた黄泉の国に別れを告げて地上に戻り、お天道さまと貴女に再びまみえたい、と。かくして戻って参りました! だからわれわれふたりで復讐してやりましょうよ! さて、この先はスタール夫人に確認するまでもあるまい。わたしが想像するに、エルヴェシウス夫人はこの手紙を読んでにっこり笑い、しかるべき顔ぶれがそろったところでみずから朗読した。――18世紀に通信の秘密という発想はないし、サロンのマナーを知りつくした者だけが、微妙な手紙を上手に公開して小粋な話題をつくることができる。こうしてフランクリンが定例の訪問を1回か2回スキップしてから、羞じらいを含んだ優雅な微笑を浮かべて登場すれば、ますます人気沸騰。彼を「素敵なパパ」Bon Papa と呼ぶ女性ファンの数はいやがうえにも増してゆくだろう。 問題の手紙がいつ書かれたのかは不明だが、1706年生まれのベンジャミン・フランクリンは70の峠を越えている。当時の平均寿命からすれば立派な後期高齢者である。そのフランクリンのフランス語能力は、フュマロリによれば「なかなか立派」estimableであるという。謙遜を装う本人も、じつはかなり自信があったのだろう。エルヴェシウス夫人への恋文を含め、いくつかの手紙や創作を集めて手元の印刷機で本にして――なにしろ、もとは印刷屋なのだ――『パシーのバガテル』(パシーのよしなしごと)と題したのだった。この洗練された言語的感性は、いったいどこで身につけたものだろう? フランクリンはロンドンで1757年から十数年も暮らし、その間に2度、短期間だがフランスを訪れている。ただし、この伝説的な「蝋燭職人の子」が学校に通わせてもらったのは10歳まで。いつ、どこで外国語を習得できたのか。名高い『フランクリン自伝』によれば、1733年に外国語の勉強を始め、まもなくフランス語に熟達して楽に読めるようになったとのこと。しかし、たんなる読解力の話ではないのである。 そもそも、この『自伝』の学校英語のお手本のような、道徳臭い文章はどうだろう。『バガテル』の洒脱なフランス語とのギャップは、説明のしようがないではないか。それにあの平明で、力強く、格調高い「独立宣言」の文章は? 外交交渉で条約を締結するさいの公文書における一言一句は? おまけに世界に通用する科学論文も発表しているし・・・・・・と分裂症気味になってきたから、このあたりで強引にまとめよう。 パリのサロンのベンジャミン・フランクリンは、ひと言で定義するなら、想像を絶するほどしたたかな後期高齢者なのである。70歳まで植民地生まれの「イギリス人」として生きてきた人間が、今や更地に「アメリカ」を出現させようと企てている。『自伝』のまん中あたりに、すでに書かれた原稿の「教育的効果」を絶賛するクェーカー教徒の友人からの手紙が挿入されている。その友人にすすめられ「1784年、パリの近郊パシー」において後半の執筆が再開されたというのだが・・・・・・。わたしの想像によれば、フランクリンは『自伝』のエピソードを適当にアレンジして、サロンで朗読していたのではないか。いや、しないはずはないと思う。フランクリンが死去して1年後の1791年、世界に先駆けて前半部分の不完全なフランス語訳がパリで出版されたのは、待望する読者がいたからにちがいない。そう思って読めば「建国の父」が「アメリカ国民」に与えた道徳の教科書のような『自伝』も、新旧の大陸をむすぶ知的冒険から生まれた見事な副産物のように見えてくる。 フランクリンが帰国したのち、第二代駐仏全権公使となったのは、いずれ第三代アメリカ大統領となるはずのトマス・ジェファーソン。スタール夫人の友人ガヴァヌア・モリスがその後任として第三代全権公使に任命されたのは、パリに到着して3年が経過した1792年の初め、国王処刑の1年前である。いずれにしても1789年7 月のバスティーユ占領以降は、サロンで恋文や自伝を朗読する時代ではなかった? ・・・・・・ということでもなさそうなのだが、モリスについては、目下、資料を取り寄せているところ。いずれあらためて、スタール夫人とともにご報告をしたいと考えている。 *1 Marc Fumaroli, Quand l'Europe parlait français, Editions de Fallois, Livre de poche, 2001. コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.