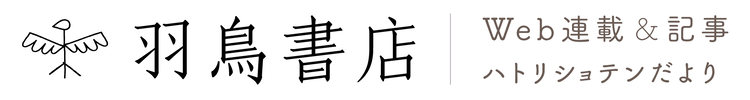|
これは、わたしの生涯の研究テーマ。といっても出遭ったのはそう昔のことではなくて、「近代ヨーロッパ批判」三部作(*1)の第二作の終章に「女たちの声」というタイトルをつけてみたのが、新しい自覚の始まりでした。学生のころから親しんできた『ボヴァリー夫人』の周辺にさまざまの「姦通小説」を配し、政治と宗教、人の掟(民法)と神の掟(教会)という対立軸によって構成された社会秩序の内部で読み解くことが、著作の意図だったのですけれど、書いているうちに、しだいに欲求不満になってきた。どうしてわたしはこれほど忠実に、男の視点、男の立ち位置、男の世界観をなぞるような作業ばかりやっているの? とだんだん腹が立ってきて、これぞ女の視点、女の立ち位置、女の世界観、よくぞ言ってくれました、と応答できるような女性作家はいないものか、という探求の意欲がムラムラとわいたのですが、ついに発見したという確信が得られたのは、第三作を書き終えたときでした(「読むこと」はしばしば知識の「習得」でしかないけれど「書くこと」はときに真の「体験」となる)。
つまり「女たちの声」と今のわたしがいうとき、それはとりわけ「スタール夫人の声」であり、こめられた意図は何よりも「政治的」なもの――なにしろスタール夫人はフランス革命勃発時の大臣ネッケルの娘なのであり、フランスのみならず英国・ドイツ語圏・イタリアなど、ヨーロッパの諸国民にかかわるフィクションや評論を書くときには、その地で「女たちの声」を「公的な領域」に届ける仕掛けが機能しているかどうかに必ず言及する。これは「世論」と「代表」をめぐる問題を、女性が自ら関与する政治的課題として語った初めての例であると思われます(誰もが知るように「声」voixは選挙の票や投票権も指す)。 というわけで日々のBSのニュースを観ても、真っ先に気にかかるのは、公的な領域における女性の身体的なプレゼンスです。3月14日、ドイツ連邦議会でメルケル首相が再選されて、ようやく新政権が誕生しそうですけれど、閣僚の女性比率はどうなることか。ご存じのように、フランスのマクロン政権は、数字のうえでは完全な「男女同数(パリテ)」を達成している。ただし女性閣僚の大半が「女性の権利省」など女性に特化した分野を担当する現状は、アリバイ工作が透けて見える、という批判もあるらしい。もしかしたらドイツのほうがプレゼンスは実質的なのかもしれません(日本の現状を思うとほとんど絶句するけれど、でも、絶句している場合ではない)。 圧倒的な存在感を見せるのは、与党ドイツ・キリスト教民主同盟(CDU)副党首のウルズラ・フォン・デア・ライエンで、国防相の続投が確実視される人物(59歳、洗練された凛々しい女性)。メルケル首相の後継者として俄かに注目されるようになったもう一人の女性は、アンネグレート・クランプ=カレンバウアー(55歳、信頼できる友人であるというメルケル首相と同じタイプの好感のもてる安定型)。たしか2月の半ば、記者団のまえで党の新幹事長候補として紹介する場面だったか、メルケル首相が、もしこの人が幹事長になれば女性で初めて、と言った瞬間の反応が面白かった。えっ? という感じで一瞬その場が固まり、首相はキョトンとして、何かドジやった? という表情を見せてから、照れくさそうに破顔一笑。じつは初代の女性党幹事長はメルケル自身でありました。昨年9月の総選挙後5カ月にわたる紆余曲折の末、3月4日の党員投票の結果を受けてようやく大連立を組むことになったドイツ社会民主党(SPD)は、新体制の党役員6名はまだ発表できないが、男女同数3名ずつになるだろうと発言。ニュース報道ですらない、こういう普通の光景も――集団の社会的なバックグラウンドが一瞬露呈するという感じで――切実に羨ましいですよね。 さて「女たちの声」という主題には、とりあえず3つのアプローチが想定されており、「政治的」なものにつづく第二の切り口は「メディア論的」そして第三は「唯物論的」な考察です。「声vs.文字」「話される言葉vs.書かれた言葉」「パロールvs.エクリチュール」といった具合に対立的に分類された言語の様態に関し、男性と女性は歴史的に同じかかわり方をしてきたか? 同じでないとしたら、いかなる差異があるのだろう? 考えてみたこと、おありでしょうか? |
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.