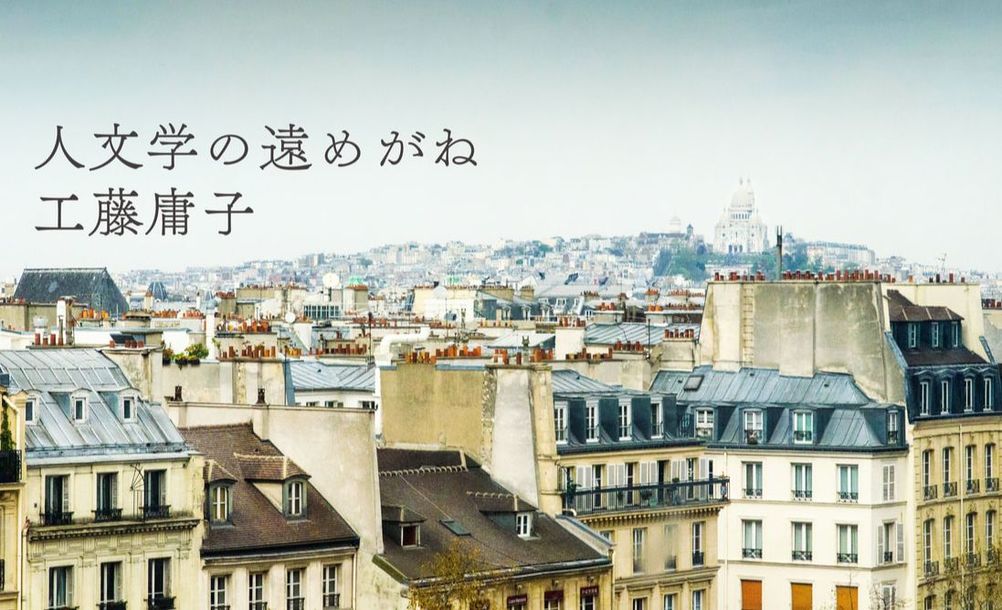|
フローベールを語らずしてフランス第二帝政を語れるか。プルーストやコレットぬきで第三共和政を描けるか。ウルフを視野に入れずに女性と文学という主題に接近できるのか。だとしたら? そう、大江健三郎を恭しく棚上げにしたまま、日本の戦後を展望できるはずはありません。昭和と平成を束にして生きぬいた作家の「全小説」の刊行が、この7月に始まり、元号の改まった年の秋に完結するとのこと(元号などは無意味な作為だと切って捨てられぬ精神風土や論争が、じっさい日本にはあるのだから、なおのこと)。『読売新聞』はじめ大手日刊紙が著名な作家や評論家のエッセイを掲載し、『群像』8月号には「筒井康隆×蓮實重彦対談」が組まれています。この対談で提示されたキーワード「同時代人」を手掛かりにしたいと思うのですけれど‥‥‥。
とはいえ「あなたは大江健三郎の同時代人ですか?」という問いが、わたしに向けて発されることは、およそ想像すらできません。大江健三郎と対談参加者、これら御三方はほぼ同年齢。それより10歳近く年下ではあるものの、ここで年齢差は理由ではなくて、そもそも「同時代」などという大仰なものについて女性が真剣に考え語ることは、絶対的に期待されない社会の片隅で、昔のわたしは生き始めたという自覚があるためでしょう。 「あなたは大江健三郎のcontemporaineですか?」という問いであれば、話は別、という気がします。わたしにとって外国語の語彙を習得することは、日本社会の厳めしさ、居心地の悪さからの脱出であり、解放の経験でもありました。contemporaineというのはプルースト『失われた時を求めて』からの借用です。社交界の花形ゲルマント公爵夫人(その頃の名はレ・ローム大公夫人)が、ある席で初々しい女性のごく自然な仕草が不意に男たちの好感を呼びさましたのを見て、あの方、わたくしのcontemporaineじゃないわね、と言う。本物の社交界で訓練された身体ではない、深読みすれば「生き方のスタイル」を分かち合えないというぐらいの、ちょっと意地悪な台詞です。ちなみに年齢差への仄めかしと見えるのは、ややコケティッシュな言葉の運用に過ぎなくて、ゲルマント公爵夫人は自分のほうが年寄りだと言うつもりは毛頭ない。だいいち人類の歴史から見れば、10年か20年前であろうと2世紀まえであろうと、時の長短などは決定的な差異ではないはずです。つまり、ナポレオンと闘うスタール夫人をわたしがcontemporaineであると感じても、一向にさしつかえない。それゆえ年齢差とは別種の問いとして、あらためて「わたしは大江健三郎のcontemporaineであると感じるか」と自問してみます。ひとまず率直に答えるとすれば、かつてはNon! であった、今ならOui! ということになりそうです。この先はやや具体的な回想を。 1960年代半ばに東大の仏文に在籍する者が、大江健三郎の愛読者でないということはありえませんでした。本郷キャンパスの医学部から弥生門にかけて、通行人もまばらな辺りでは、しかるべき時刻に犬の吠え声が陰気に響くはずであり、夕暮れ時の病院施設では人目もはばかるアルコール漬けの遺体の移動作業が……なんて夢想に浸されることなく文学部に進学した者はいないでしょう。「奇妙な仕事」「死者の奢り」などの短篇や『芽むしり仔撃ち』『性的人間』そして『個人的な体験』までが60年代の前半に出揃っている。強烈な熱風のようなものを肌で感じて刺戟を受けとめたという記憶もあるけれど、それにしてもジェイン・オースティンやブロンテ姉妹に育てられたフツウの文学少女が、読んだふりをして読み飛ばしたページは少なくなかったにちがいない。つまり20代のわたしは、断じてこの小説家を「身近」な存在と感じてはいなかった。もし、あの頃に「セヴンティーン」を読んだとしたら‥‥‥、大江健三郎を嫌いになっていたかもしれない、とすら今は思うのですが、この話題は次回にゆっくりと。 その後、わたしは横文字の世界に脱出し、かぎられた時間をどこに投入するかという切羽詰まった暮らしでしたから、日本語の小説や評論にじっくり親しむことはありませんでした。したがって、自分が大江文学のよい読者だと思ったことはなく、読んだはずの作品も、未消化のまま記憶があいまいになっている。ところが、いつ頃からか、多少は生活にもゆとりができて、いわば大江文学の再発見のような体験をすることになりました。それが、今ならOui!と答えるだろうという意味であり、とりわけ2013年の『晩年様式集』(イン・レイト・スタイル)は――「おそらく最後の小説」と帯の冒頭に記されたものですが――ほとんど戸惑いに似た、言いようのない「親(ちかし)さ」の感情を覚えて読みおえました。 ところで、いただいた御本に肉筆のお礼状を書くためにパソコンで下書きをするという恥ずかしい習慣は、ペンを握るのが身体的につらくなった時期から身についたものですが、おかげで読みおえた時点での率直な印象を正確に思い出すことができる。『晩年様式集』の作者に宛てた手紙から、小説の感想のような文章を、ほぼそのまま引用してみます。 |
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.