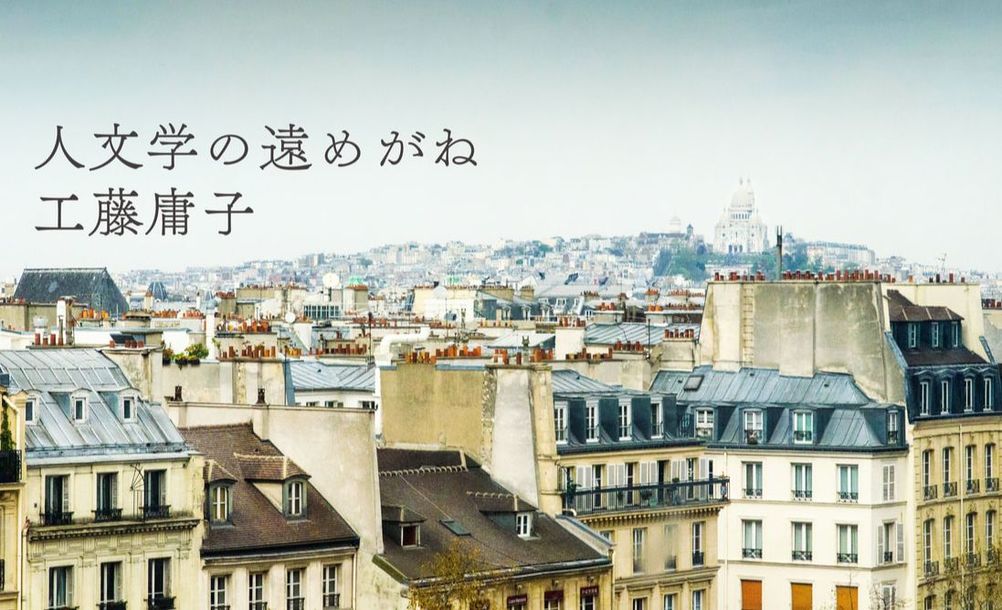|
――これをもってブログは最終回とさせていただきます。 15回の連載記事に書下ろしエッセイを添え、2019年の春に出版予定です。 *本連載は、工藤庸子『女たちの声』として書籍になりました(2019年6月)。 昨年の夏、羽鳥書店から〈淫靡さ〉をめぐる小さな共著(*1) を出版しましたが、その書物と全く無縁ではないものの、このブログの流れからすれば、見出しは「続・女のエクリチュール」としてもよい。前回に述べたように山田登世子さんは、日本で初めて〈批評〉の領域に斬りこんだ稀有な女性でした。同時代を生きた自分の人生をふり返りながら、そのことをあらためて考えているところです。『メディア都市パリ』は、著者の言葉によるなら「戯れのエクリチュール」によって「ファロスの王国」に挑戦したものであり、世に言う「再評価」とは異なる文脈で、そう、ここはいささか大上段に構えることをお許し願うとして、戦後日本の〈批評〉における女性的な言説の希少なプレゼンス――正確には、ほぼ全面的な不在――という歴史的な事実をふまえ、今現在の文脈で、その華麗な演技を読み解いてほしいと願っています。
「続・女のエクリチュール」は、その〈批評〉と対になる〈小説〉について。こちらは現代日本にとらわれず、コレットとウルフ。主題はテクストの「決定的な細部」としてのゼラニウム、その微かに淫靡な匂い。じつはこの話、以前にちょっとふれたことがあり、そこではフローベールとプルースト、いずれも両性具有的な傾向のある男性作家がちらりと姿を見せています。本題への導入として、まずはコレットのアカシアを。 代表作『シェリ』(1920年)の極めつきの場面。ご存じのように、ヒロインのレアは引退したココット(「高級娼婦」とか「粋筋の女」とか訳される)。息子ほど歳のちがう美青年と恋に落ち、何年か生活をともにしたのち、その美青年に結婚話がもちあがるというのが幕開けの状況です。その冒頭から時計をまきもどして馴れ初めの季節。夜の庭園からさっと吹きこんだアカシアの香りに誘われて、初めての口づけが交わされるというだけの場面なのですが――その香りがあまりに能動的(si active)だったので、吹きつけた香りの歩みを目で追うかのように(comme pour la voir marcher)ふたりはそろってふりむいた。「薔薇色の房のアカシアだわ」と女はつぶやき、青年はこれに応じて「しかも今夜はオレンジの花の香りをたっぷり吸いこんでいる」とひと言。あまりに繊細な感覚に、ふと胸を突かれた女が青年の顔を見つめると、恍惚とした生贄(いけにえ)のような表情が浮かんでいる。青年がレアの名を呼び、レアが近づき、そして長い接吻の陶酔が過ぎたとき、睫毛のあいだにキラキラ光る二粒の涙を浮かべているのは青年の方。 男が女の唇を奪うのではありません。レアの仲間のココットの私生児であるシェリは、美形という意味では絶品といえますが、じつは甘やかされた悪ガキで、早くも放蕩に疲れている。一方のレアは「三十年のあいだ輝くばかりの若者と傷つきやすい思春期のためにつくして」きた自分に「清潔感と誇り」をおぼえている聡明な女。思えばハリウッドの恋愛映画もヨーロッパの近代小説も、ひたすら男に唇を奪われ所有される女たち、お決まりのように恋人に去られて深く傷つく女たちを、それこそ無数に生産してきたのだから、やはりコレットは革命的に新しい(ついでに強調しておきたいのは、偉大なジョルジュ・サンドをふくめ女性作家たちの大方は、男性の期待に応える「告白小説」というスタイルを捨てきれずにいたという事実です)。愛と別れの物語でありながら、レアとシェリの関係は所有欲とも心理的な必然性とも無縁な出来事として推移するように見えるのです。ふたりがこうなってしまったのは、ただ単に、さっと室内に吹きこんだ生々しいアカシアの香りのせいだといわんばかり。 蜜蜂をおびきよせるアカシアの甘くかぐわしい匂いは、そうしたわけで、この小説の「決定的な細部」であると断定できそうです。しかも豪奢な「薔薇色」の品種。ここではアカシアの一般的な色は白という了解が暗黙の前提となる。acacia à grappes roséesという原文は、言葉の響きからしてもワインの「ロゼ」のような色合いを思わせるのでしょう。でも女が独り言のように小声でつぶやく台詞なのだから、訳者としては説明的な言葉で〈声〉のリズムを損ないたくはない。「ロゼのような淡い薔薇色の房のアカシア」とか「薔薇色がかった白の房のアカシア」とか、さんざん考えた挙句、いさぎよくあきらめることが、翻訳の宿命であるように思います。 さて、その対極にある、もうひとつの「決定的な細部」は「薔薇色のゼラニウム」。こちらはgéraniums- rosats――見慣れぬ言葉だなあと思って大きな辞書を引くと、この表現がそのまま引かれて用例に載っている。それほどにコレットは語彙が豊富、微妙なニュアンスのお手本として参照される作家なのですが、ちなみにrosatという単語の定義は「薔薇色の」de couleur roseというだけで、これだから辞書は役に立たないという見本のようなケース。おそらくは、よくある濃いめのピンク。「ロザ」という音の切れ味ゆえに選ばれたのでしょうか。つづいてゼラニウムの匂い、ということになれば、コレットを語るまえに、ひと言プルーストに言及しないわけにはゆきません。 |
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.