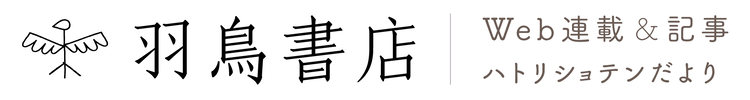|
「個人全集」は何のために編まれ、刊行されるのか、考えてみたことはありますか? それは「特別なできごと」であって「その作家の大御所としての地位を出版市場を通じて改めて確認するだけでなく、文学研究にとっては、出版社の入念な編集作業を経たその作家の仕事の全容を見渡す、新たな立脚点が得られることを意味する」というのは、『大江健三郎全小説』の初回配本、第3巻の巻末に収録された論考(*1) の冒頭にある言葉。筆者はドイツ人の日本文学研究者であり、大江文学は「世界文学」として読まれてほしいと願う者として、異論はありません。
たとえば「丸山眞男全集」など、大学の学問を背景とした「全集」を、比較の例としてみましょう。著者が生前にみずからの業績を整理・選別して刊行することもあり、死後に弟子たちが編纂にかかわることもありますが、とりわけ後者のケースでは、学知の継承という抽象的な行為が、さながらブルジョワ社会の遺産相続にも似た波紋を呼び起こすこともないではない。選ばれた「弟子」と「大御所」とのあいだには「父と嫡出子」のような認知の関係があるのではないか、それが「学問の制度化」を招くのではないか、といった屈折した論評は、しばしば聞かれるところです。 文学の個人全集には、そういうことはない? でも「漱石全集」なら日本文学や比較文学の領域に膨大な「漱石学」の蓄積がありますから、大学の学問的権威を体現する編集企画を立てること自体は、他分野と同じく可能でしょう。一方、出版社が主導して、文壇で活躍する作家たち、評論家たちの解説とともに、主要作品を刊行することもできる。いずれにせよ「全集」の刊行に寄与する編者や解説者と作家との組み合わせ自体に、研究者間の知的血縁関係の開示のようなドラマを見てとる人はいないと思われます。 つぎに存命中の作家の特徴ある一例を。チェコとフランスで人生の前半と後半を過ごしたミラン・クンデラが、2011年にガリマール社のプレイアード叢書に入りました。長い伝統に逆らった破格の編集なのですが、ノーベル賞か、アカデミー・フランセーズか、それともプレイアードか、と昔は冗談にいわれたほど「権威」ある叢書ですから、この企画がすんなり通ったとは思われない。叢書の標準的な形式を破壊しているのです。著者の選択した小説や評論の決定版の総体が、著者自身が最終的に認知した「作品」(単数形のŒuvre)としてヴォリュームのほとんどを占め、注釈や草稿や改稿のたぐい、「年譜」や「評伝」などの情報は全て潔くカット。遠いカナダ在住の比較文学者によるBiographie de l’œuvre(「作品の作られた事情と方法」という感じか)と題した控えめな「作品解説」が巻末についている。 この簡素な造りに秘められた強い意志とは何か? カフカの遺稿をめぐる批判的なエッセイ『裏切られた遺言』をお読みになった方は、言われるまでもない、とお考えでしょう。遺言によって破棄されたはずの草稿を根拠に「作品」が他人の手で改竄されること、死後に本人が与り知らぬ恣意的な解釈に曝されることは、断じて拒絶・回避するという宣言。「全体主義」の時代のチェコで、「検閲」と親密圏への権力の介入を体験しつつ作家になった人の「防衛」の仕草のようにも見える。しかし、ここまで徹底した「作品」の囲い込みに違和感を覚え、こんなふうに、みずからの「遺言」の「執行人」までやってしまうとは ?! と妙な切なさを感じる人もいるようです。若き友人の言によるなら、プレイアード叢書はどことなく「柩」に似ている‥‥‥。 「おそらく最後の小説」であると大江自身が言う『晩年様式集』の最後に近いページで、「三人の女」の一人によって、暗示的な言葉が発されます。「人生のしめくくり(原典は下線ではなく傍点)」をクンデラの「作品」(「ウーヴル」とルビ)に達成する――引用だけではわかりにくいかもしれないけれど、「作品」の決定と開示・刊行が、しめくくりの営みとなるはず、ということでしょう。 『大江健三郎全小説』(講談社)の記念すべき第一回配本の一冊である第3巻は、その巻頭に、二部構成の「セヴンティーン」と「政治少年死す(セヴンティーン第二部)」を収めています。後者は1961年『文學界』に発表されてから再録されることはなく、今ようやく「封印を解かれ」たものという。「モデル」とされる右翼の少年は、わたしより一歳年上、同じ都会の風景を眺め、同じ時代の空気を吸っていたことになりますが、なにゆえ作品は半世紀以上にわたる禁忌と抑圧の対象となったのか?
巻末の周到な「解説」で尾崎真理子さん(面識はないけれど、やはり「さん」付けで)が語っておられることを参照し、メモ風に時代背景を復習するならば――60年安保闘争が首都を席捲し、市民や労働者や学生を動員した時代。街頭では赤尾敏率いる大日本愛国党が大音響の宣伝カーを走らせ、戦後知識人たちの支持を得た日本社会党や日本共産党が大規模集会を開いていた。存在感を誇示する左翼と右翼の正面衝突で、「天皇」は政治的であると同時に象徴的な争点ともみなされた。そもそも敗戦後の日本には「天皇」をめぐる思想書からフィクションまで多くの刊行物あり、とりわけこの時期、現実の殺傷事件と文学作品が奇怪な様相を呈して交錯した。1960年10月12日、日本愛国党の元党員である17歳の少年が、社会党の浅沼稲次郎委員長を立会演説会の壇上で殺害し、逮捕後、独房で首吊り自殺を遂げた。一方11月に『中央公論』に発表された深沢七郎の「風流夢譚」は夢の話という設定で、「左翼」ならぬ「左慾」が皇居に乱入して天皇一家を惨殺するという、過激きわまる滑稽小説だった。年が明けた1961年2月1日、中央公論社の嶋中社長宅に、同じ日本愛国党の元党員である17歳の少年が押し入り、家政婦を刺殺、社長夫人は重傷を負った。一連の事件の合間をぬうようにして、大江の「セヴンティーン」は1960年12月発行の『文學界』に、そして「政治少年死す」は翌年1月の同誌に掲載される。出版社が報復を恐れて単行本化を自粛したのは、嶋中事件の余波とみなされている。 さて「セヴンティーン」は、ひ弱で鬱屈した高校生である「おれ」が、小遣い稼ぎにサクラで参加した極右組織の集会で「皇道派」の大物に魅せられ、凶暴な「右翼少年」に変貌するまでを語る。後半の「政治少年死す」では、右翼団体の活動メンバーとなった「おれ」が広島の平和大会になぐりこみをかけ、帰途の車中で「天皇の精髄」をめぐる「啓示」を受ける。そして党を離れて農場で修練の日々を送ったのち、暗殺を決行して自殺。テクスト上にゴシックの太文字で記された「確信・行動・自刃」という信条に、政治少年は殉じたのである。独房で首を吊った少年の「死亡広告」と題された8行ほどの断章で幕。 全体として浅沼委員長を暗殺した山口二矢(おとや)を生々しく想起させる作品であることは事実だけれど、『全小説』の「解説」には貴重な証言が記されている(尾崎さんは、長年にわたりインタビュアとして大江文学の生成に寄り添ってきた)。右翼少年の誕生を語る「セヴンティーン」の場合、原稿(110枚超)の締切りは11月後半だったはず、10月半ばの暗殺事件に触発されて、その後に物語が構想されたとは考えにくい、という指摘を受けて、作者自身が「経過だけ読むとモデル小説」のように見えるかもしれないが、じつは「右翼的な宣伝、テロみたいなことを考えたり、書いたりしていた時に、そういう事件が起こってしまった」と答えを返している。文学は現実の出来事の反映・反芻なのか? そうでないとしたら? という問いにかかわる重要なポイントです。 「セヴンティーン」二部作は、過激に「政治的」であると同時に過剰に「性的」な作品です。なにしろ「おれ」が17歳の誕生日に風呂場で自瀆に耽る長い記述に始まって、「絞死体をひきずりおろした中年の警官は精液の匂いをかいだという……」で終わるのだから。そこでナイーヴな疑問を呈してみたい。あられもなく露出した「性」を、そして「性」と「政治」との不可分であるらしい関係を、男女の読者、とりわけ女性読者は、どう読むか? それというのも「解説」担当は女性、これにつづく論考は日本文学を専攻するドイツ人女性研究者によるものであり、初回配本における女性のプレゼンスは、たまたま、ということのようには思われない。前回のエッセイで示したように「三人の女たち」の言語的反乱という趣もある『晩年様式集』を書き終えた作家による全集編纂の、いわば作為的配慮でもあろうかと推測するからです(全集の『全小説』という枠組みについては、次回に)。正直なところ、解説や評論や参考文献や雑誌などの関連企画をふくめ、大江文学の周辺が男性の言説で埋め尽くされていたならば――相変わらずホモソーシャルな言語環境に恐れをなして――わたしは日本への回帰など考えてもみなかったはず。 そうしたわけで、わたし流の文学的妄想によれば、半世紀昔の剣呑な右翼少年が、二人の知的な女性にエスコートされて甦ったようでもあり……、それはともかく、お二人の「セヴンティーン」論への応答として、本論を書き始めたいと思います。 |
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.