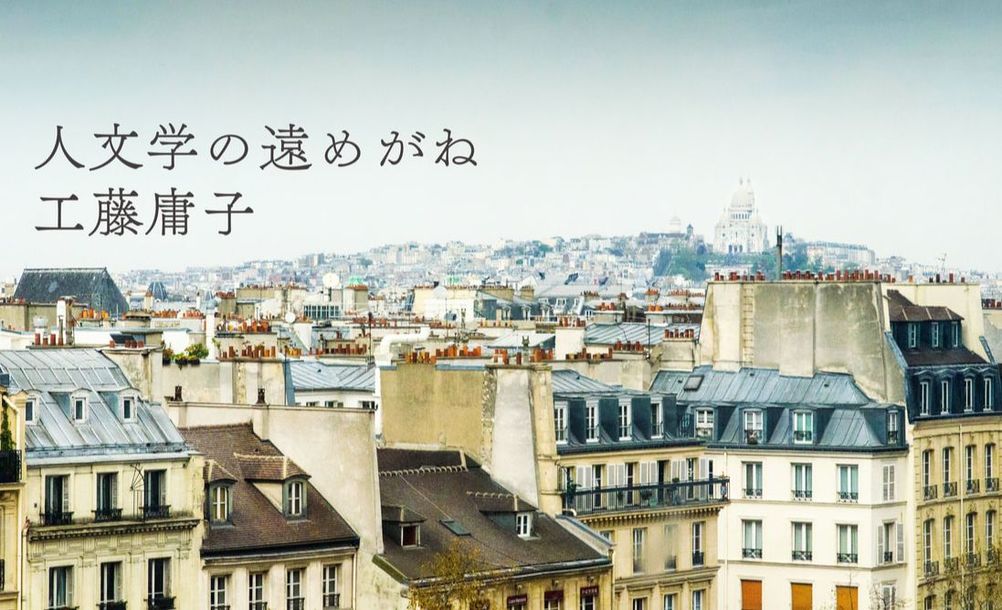|
In our time Proust was wholly androgynous, if not perhaps a little too much of a woman. (現代でいえば、プルーストは完璧な両性具有、女性の割合がやや勝ちすぎているかもしれないけれど)――こんな名台詞を読むと、じんわりと嬉しくなりません? 出典は、わが愛読書ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』ですが、この一言がジェンダーの歴史において画期をなすことの理由は、「近代的=二元論的」な性差の概念を、いとも軽やかに廃絶してしまったから。そこで、引用をもうひとつ。
The best woman (is) intellectually the inferior of the worst man.(いちばん出来のいい女子でも、知性としては、いちばん出来のわるい男子に劣る)――これも同じエッセイのなかの台詞。といっても発話者はもちろん著者本人ではなく、ケンブリッジのさる大物教授だとか。こんな話がウルフにあるのよ、と友人の若い女性編集者に紹介すると、屈託のない笑いが返ってくるのだけれど、そしてウルフ自身もユーモアと皮肉がはじけるような文体でこれを書いているのだけれど、でもね、わたしとしては身に覚えがあるのです。 「プルーストが女にわかるか?」という、昔々、わたしが学生だったころ、雑談のなかで男子学生たちが得意気に口にしていた台詞。くり返し紹介しているのは、恨みがあるからでは全然なくて、その論理構造が客観的に興味深いから。そもそも女性は芸術の鑑賞者であるべきで文学や詩の創造という主題はあまりに高踏的で理解できまいという、今日でも解消されたわけではない古色蒼然たる紋切型が透けて見えるのだけれど、それだけではない。なにしろ『失われた時を求めて』は「男性同性愛者」の書いた「芸術家小説」なのであり、したがって女性は性と知性において二重に排除されている、という理屈。つまり「男性同性愛」というのは二重に「純化」された男性性? プルーストは男のなかの男? 問題の男子学生たちが無意識に依拠していたと思われる見取り図を、とりあえず「排除的性差」×「序列的性差」によるジェンダー概念と定式化しておきましょう。 ウルフは多少とも両性具有的でない人間は、ダメだと言っているのですよ。「偉大な精神は両性具有」という表現は、コールリッジからの借用だそうですが、そのコールリッジを含め、人間と世界を理解した両性具有の王者はシェイクスピア。一方でワーズワースとトルストイは「男性の割合がやや勝ちすぎている」とのこと。ここで、ウルフさま、よくぞ言ってくださいました、という感じの、三つめの引用を。 It is fatal to be a man or woman pure and simple; one must be woman-manly or man-womanly(男でしかない男、女でしかない女は救いようがない。だから男っぽい女、女っぽい男になりましょう!) 女性作家の軽いジョークを紹介しているわけではありません。『自分だけの部屋』が刊行されたのは1929年。イタリアではムッソリーニがファシズム体制を着々と築いており、ヒットラーの大統領選出馬とナチ党の躍進は3年後。テクスト上でもヨーロッパの政治的な緊張を横目で睨んだエピソードとして「両性具有」という話題が導入されているのです。著者にとって女性排除の二大巨頭はナポレオンとムッソリーニ。個人の性格や特質ではなくて、二元論的な近代を構築した人物とその延長上で人類の災厄を招こうとしている人物という位置づけです。「文学」に身をおく者として、男性中心的な「政治」と「歴史」をいかに批判し、相対化して、プルーストの体現する「文学」の尖鋭な革新性をいかに際立たせるか。ウルフの称揚する創造的な「両性具有」とは、そのための戦略的キーワードにほかなりません。 ためしに「排除的性差」×「序列的性差」という定式の語彙を一部入れ替えて「排除的エスニシティ」×「序列的エスニシティ」としてみましょう。同じ論理、同じ力学によって、ヨーロッパが国民国家の内部からユダヤ人という他者性を析出したことが想像できるはず。さて唐突ながら、ここで読みおえたばかりの樋口陽一『抑止力としての憲法』(*1)からカール・シュミットにかかわる段落を抜書きしてみます。 |
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.