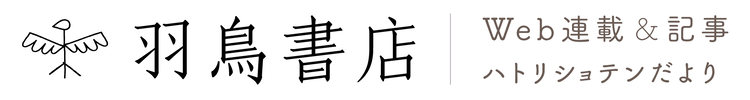|
「人文学の遠めがね」というタイトルで、ブログを開設することになりました。どうぞ宜しく。お隣さんである「憲法学の虫眼鏡」にあやかろうというさもしい魂胆がないとはいい切れませんけれど、ただのパロディというわけでもありません。 発想の源はプルースト。『失われた時を求めて』の大団円『見出された時』の終幕にある語り手の述懐を、わかりやすくまとめておけば、こんな具合です。――書きためた作品のエスキスを人に見せても誰もわかってくれない。私が聖堂に刻みつけようと考えている真実については、それなりに理解してくれる人でも、よくぞ「顕微鏡」でそんなものを発見したと褒めるだけ。だが、じつのところ、私は「望遠鏡」を使っているのである。なるほど私が捉えているのは、とても小さな物体のようではあるが、それはとてつもなく遠いところにあるせいで、じつはそれぞれがひとつの世界をなしている。つまり私は「望遠鏡」を使って大きな法則を探し求めているのだが、にもかかわらず、どうやら手元の細部をほじくり返す人間とみなされているらしい。 というわけで、わたしの「遠めがね」が向けられている先は、とりあえず革命期のフランスです。でも、なぜフランス革命なのか? 現代日本の国会議員の女性比率が189カ国中147位(世界・国会の女性議員割合ランキング:2015IPU版)などという言語道断な数字を見るにつけ、深刻に考えこんでしまうのです。「戦後民主主義」を謳歌して育ったはずの世代は――今や現役を退いて10年以上になるわたし自身をふくめ――これまで何をしてきたのだろう? 国会や政党だけの話ではない。企業にせよ、研究機関にせよ、そもそも女性がしかるべきポストにしかるべき比率で配置されていない組織において、男女共同参画社会にふさわしい「民主主義」が機能するでしょうか? 求められているのは大きな展望にもとづくラディカルな決意です。 さて「黄泉の国の会話」というアプローチが「遠めがね」の比喩にふさわしかどうかは定かではありませんが、以下はフランス革命とナポレオン独裁を生きぬいたスタール夫人と架空のわたし自身であるKYとのおしゃべりであります。ちなみに死者との対話という設定は、ヨーロッパでは伝統ある文芸のジャンル。ダンテもそうだし、プルーストには、少女たちが作文の課題で「ソフォクレスが黄泉の国からラシーヌに送った手紙」を考案するという微笑ましい話がありました。 * スタール夫人――そう、おっしゃるように、あの時代、女性は存分に「世論」に参加することができた。「ソシエテ」というものがありましたからね。そのことは、わたしもフランス革命論できちんと指摘しておいたし、その後、ジュール・ミシュレも華やかな筆で革命期の女性の活躍を称えている。でも、わたしがあなたに聞きたいのは、なぜ21世紀の日本で女性の解放がそれほど遅れているのかってこと。
KY――その理由がわかれば、って誰でも思いますけどね。「ジェンダー秩序」などという言葉を今じゃよく使うのですが、「革命」や「戦争」のために、政治・社会・文化の秩序が轟音を立てて崩れ落ちる瞬間には、その「ジェンダー秩序」も崩壊する。2回の世界大戦とその後の民族紛争は、皮肉なことながら、女性の飛躍的な社会進出を促すというプラスの効果をもたらした。これは歴史の事実です。 一方で敗戦国日本の民主主義は半世紀以上にわたり、明らかに女性を置き去りにした。なぜ今ごろになって、人はようやくそのことに気づきはじめたのか、という大問題は脇に措き、フランスにもどりますと、革命前夜からナポレオンのクーデタまで――国民公会による恐怖政治の時期を除いて、ですけれど――あの限られた時代に「女性の政治化」というか「政治の女性化」というか、ともかく前例のない変革が起きた。そして、ナポレオン法典が「ジェンダー秩序」を含む近代市民社会の秩序を着々と構築するかたわらで、その変革の記憶までが、徐々に忘却の淵に沈んでいった。 空前絶後といえば大袈裟だけれど、あの例外的な時代に輝いておられたのが、わがジェルメーヌさま、とミーハー的に憧れているわけでございます。 スタール夫人――ミーハー的という言葉の意味はわかりませんけれど、褒めていただいたみたいね。でも、印刷されたものだけでは、あの時代の途方もない言語的昂揚の本質はつかめませんよ。なにしろ「世論」の基調をなすのは「語られた言葉」なのですから。学者の方々は「サロン」とか「公共圏」とか空間的な語彙で括る以前に、そのコンテンツを考えてほしい。わたしたちが「ソシエテ」あるいは「会話の精神」と呼んだものが、いかなる「活動」として、つまり男女の参画するパブリックな言語的実践として存在していたか・・・・・・未来からふり返ってみるなら、まさにハンナ・アーレントの語彙にある「活動」の先駆だと思う。 ちなみにわたしの邸に入り浸っていたガヴァヌア・モリスの『日記』にも、「サロン」という言葉は出てこないでしょう? KY――そうそう、そのガヴァヌア・モリスの『日記』ね。あらゆる研究者が「革命期の政治的なサロンについての第一級の史料である」と保証するけれど、読んでいる人はほとんどいない。だいたい「サロン」というのは女性が主宰した空間であって、つまり女物のテーマでしょ、だからね、ここだけの話、たいていの男性研究者は玄関先で礼儀正しく挨拶しただけで消えてしまうわけですよ。そもそも「語られた言葉」には信憑性がない。学問の基調は「書かれた言葉」でありますし。 スタール夫人――ふうん、そうなの。で、あなたはモリスの『日記』を読んだわけ? KY――そりゃ、もちろん! 目から鱗というべきか。でもこの話は長くなるから、ひと言だけ。 スタール夫人――読めばわかるはずですけれど、モリスがパリの「ソシエテ」に登場したのは、1789年の初め。ジョージ・ワシントンの片腕で合衆国憲法の起草に深くかかわり、アメリカ独立戦争で生じたフランスへの借款について交渉する任務を帯びてやってきた。フランス語は達者だし、片脚だけど見場もいい、とても素敵な男でしたよ。あっという間にパリの「ソシエテ」を征服して、タレイランの公認の恋人フラオ伯爵夫人を口説き落とし、それでいてタレイランと仲違いするでもなく・・・・・・ところで、タレイランがあの当時、わたしの恋人だったか否かというのは、評伝作家がかならず触れる大問題なんでしょ? 要するに、わたしたちのあいだには絶妙な四角関係みたいなものがありましてね、それがルイ16世周辺の政治的決断や情報操作の駆け引きにも絡み・・・・・・。 KY――あ、でも、その話は長くなりますから、また今度・・・・・・。あの『日記』を読んで、わたしがマジメな研究者としてある種の感動とともに確認したのは、開幕したばかりのフランス革命が、ほぼ形をなしたアメリカ独立革命を身近なモデルとして真剣に参照していたという事実。つまりあの時点の実感としての米仏の距離の「近さ」です。そして驚愕したのは義足のモリスのフットワークの華麗さ。でも、じつはモリスは、パリでもてはやされた初めての「アメリカ人」ではないんですよね。偉大な先輩はベンジャミン・フランクリン。この話、どうですか? スタール夫人――なるほど、それで「ベンジャミン・フランクリンの恋文」なんて妙な表題がついているわけね。あの手紙、わたしも読んだけれど、なかなか立派。あれならサロンで朗読できます。そのお話、書いてみたら? こちらでもブログは読めますから。 KY――まあ、嬉しい! では、また。いずれあらためてお声をかけますね。 (つづく) コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.