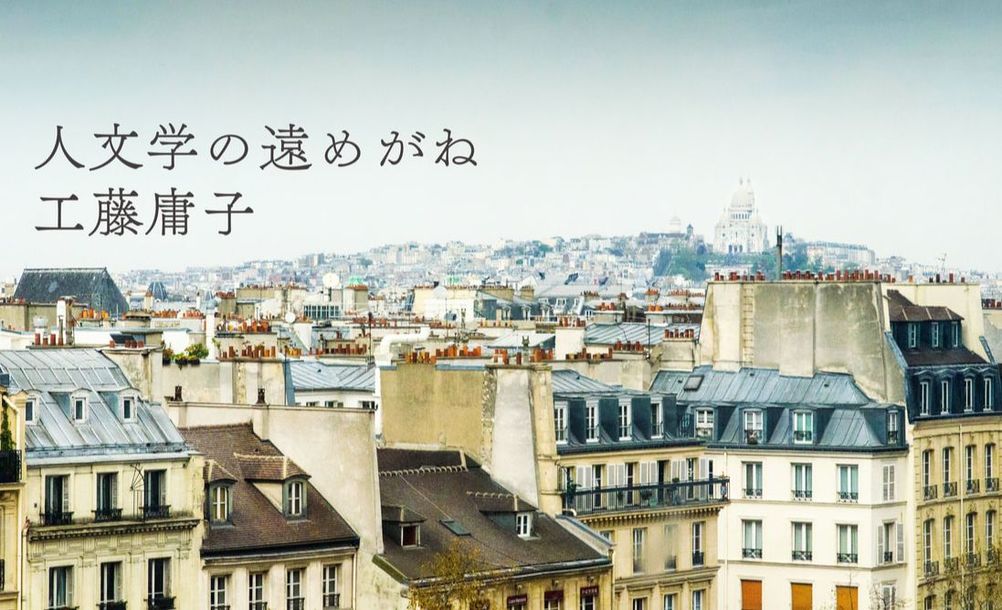|
今回の衆議院選挙においても言語道断な女性比率は相変わらず。その結果に怒り、その怒りがメディアにしかるべく反映されぬことにも、ふつふつと怒りを覚えている女性たちが、はたしてどのぐらいいるか。少なからずいるはず、と信じることにします。 なにしろ内閣府男女共同参画局には「各分野における指導的地位」の女性比率について「2020年30%の目標の実現に向けて」というサイトが麗々しく立ちあがっているのに(2020年までにあと2年!)、政権与党である自民党の当選者の女性比率は、なんと7.7%なのであります。しかも、政権担当者たちは努力目標ですらない空手形の公約など、すっかり忘れたかのように、恥じる気配もありません。興味深い数字は、分裂した野党二党に関するもの。女性が代表を務めていた希望の党は47名の女性候補者を立てながら当選はわずか2名、にわかづくりの立憲民主党は19名の女性立候補者のうち12名が当選(『朝日新聞』10月25日)。この奇妙な歪みは何を意味するか。まっとうな市民生活から政党政治があられもなく乖離しているとしかいいようがありません。 結果として、女性の意志や知性や生活条件を反映する議席が1割しか与えられなかった。じつは政治の世界と知の世界には、もし適正に数値化することが可能であれば、ほぼ同等の男女格差がある、日本では「ガラスの天井」どころか、はるかに低いところに「1割の壁」があって道を塞いでいる、と経験的に感じています(*1)。ともかくこれでは「パリテ法」(男女同数への権利)を発議したくともできない。「代議制民主主義」の大原則からしても、すべての個人に政治的自由を保障すべき「人権」の理念に照らしても、日本の現状は、明らかに不整合なのではありませんか。ここは「指導的地位」におられる9割の男性の方々に、つよく求めておきましょう――「異性の問題」としてではなく「政治の問題」「社会の問題」として、この格差の由来を考え、それぞれの立ち位置から発言していただきたい、と。 さて本日とりあげるのは「二本のネクタイ」という寓話。二本のネクタイのうち好きな一本を選ぶように、自由に男か女かを選べるという解説はまやかし、誤魔化されてはダメ、という厳しいお話です。女性への聖職授与を認めぬカトリック教会の論理構造を批判して、ある人類学者いわく――神さまは二本のネクタイの好きな方を選んだわけではない、社会の鋳型から考えて、それ以外にはありえぬ一本を選んだだけであり、社会は啓示宗教が登場する以前から、男性を上位においてきた。神の子たるものが、性の混乱を象徴する両性具有に生まれてくるわけにはいかなかったのであり、かりに神の子が、規範に反して二本のネクタイを首に巻くような具合に、両性具有に生まれていたら、聖職者の選択の可能性は大いに狭められたことだろう、とユーモアをまじえた考察がつづきます。 この人類学者が女性であることは、もう、おわかりのはず。フランソワーズ・エリチエ『差異の思考(*2)』の「女性が権力をもつことはありそうにない」と題した「結論」からの引用です。書物の与える印象は悲観的どころか、じつに力づよい。クロード・レヴィ=ストロースの後継者として1982年にコレージュ・ド・フランスの教授に就任したエリチエは、現在は名誉教授としてメディアでも活躍していますが、キャリアとしては師と同様、フィールド調査(主にアフリカ)でしっかり実績を積んだ研究者。『差異の思考』も啓蒙書というよりは論文集に近い。世界には、いかに多種多様で思いがけぬジェンダー構造が見出されるか、列挙する余裕はないので女性の不妊が嫌悪されぬ例を一つだけ。
結婚した女性が不妊と判断されると出身家族に帰され、以降は「男」として扱われる。すなわち家畜の群を所有する権利を与えられ、みずからの働きによって婚資を支払うことができるようになれば、「男」として一人もしくは複数の妻を迎えることができる。生物学的には女性である「夫」は妻(たち)と家族を構成し、妊娠については外部から男性を雇い入れて解決する。生まれた子供たちは一家の長である女性を「お父さん」と呼んで成長する――しかし、見たところユートピア的な物語に誤魔化されてはなりません。 たとえば「多産」で「精気」にあふれた作家と「不毛」な作家という比喩に見られるような諸概念の総体、そこに折りこまれた価値体系こそが問題なのであり、その体系のなかで、男女の「差異」は不平等を黙認する「差別」に読みかえられて、おのずと「格差」を助長することになる。そもそも言語体系のなかに、性別に応じた二項対立的な表象のカテゴリーを内包しない社会など存在しない、とエリチエは断言しています。しかも、男/女、右/左、高/低、熱/冷、等々の対立関係において、肯定的な価値を男性に、否定的な価値を女性にふりわけるイデオロギーは、人類学の検証するところによれば、あらゆる社会に普遍的に見いだされるというのです――なるほど。でも、これでは「二本のネクタイ」問題は、解決の糸口すら見いだせないのではありませんか? 『差異の思考』の最終章「個人、生物学的なもの、社会的なもの――子をもつ権利と生殖の問題」は人類学の論文ではなく、著者の社会的な発言を収録したものです。1985年『ル・デバ』誌上に、ロベール・バダンテールによる「医学、生物学、生化学の進歩を前にした人権」と題した論考と、これに対する複数の論評が同時に掲載されました。バダンテールはミッテラン政権下で司法大臣として死刑廃止法を成立させた社会党の政治家ですが、弁護士で上院議員、20年パリ大学で法学を講じ、現在は名誉教授。一言いわせていただくなら、わが国では政治の世界と知の世界が画然と仕切られて、人的交流も希薄なまま、一国の元首が安手の商業広告のように「革命」を謳っても周囲はあきれた顔もせず、法的・政治的な概念や語彙の陶冶など配慮する機運すらありません。やっぱり羨ましい。フランスならではの知識人といえそうです。ちなみに伴侶であるエリザベート・バダンテールのフェミニストとしての活動のほうが、日本では一般に知られているかもしれません。 議論の一部を紹介しましょう。生殖医療の発展により、親子関係をめぐる概念と法の規範は根本から変質する、というバダンテールの指摘に対し、エリチエはまず「子を成すこと」と「親子関係」を短絡させることの危険を説いている。なるほど『差異の思考』の論文をここまで読んできた者であれば、生物学的な不妊に対処する社会的な処方箋をもたぬ社会は存在しない、という実感はおのずともっている。出産は自然に帰属する血の紐帯である一方で、親子とは社会的な約束事にもとづく紐帯なのであり、両者は解きほぐしがたく結びついた二つの概念ではないという見解も納得できる。要するに人類は医学の進歩により前代未聞の現象に直面しているわけではない、というのがエリチエの基本的な立場です。「ヨーロッパ人権条約」が保障する「生命への権利」や「プライヴァシー権」の一部とみなされる「自己実現」の願望などについて、社会人類学と法学のあいだには、微妙ながら無視できぬ立論の相違があることは、読めばおのずと伝わってくるのですけれど、よほど本腰を入れなければ、高度な論点を分析することはむずかしそう。 社会的なもの(法はその「精髄」である)と自然に帰属するものとの境界や軋轢を精査することが肝要であり、一方から他方への安易なシフトは曖昧な思考を招くという教訓のみを反芻するにとどめ、ここは「二本のネクタイ」の寓話を再解釈して、あっさり終わりにいたします。わたしはバダンテールの論考を読んでいないわけですが、エリチエの論評は互角の議論、おそらくはより繊細な議論を提供しているのではないか、そう直感的に感じており、そのぐらいの感想を口にしてもさしつかえあるまいというぐらいの度胸を、最近ようやく身につけたところです。 同じテーマをめぐる法学者と社会人類学者の議論を見比べる機会が――まさに「二本のネクタイ」を見比べて、自由に好きな一本を選ぶような具合に――一冊の書物により与えられている。そこでは、やや理念的でリベラルで圧倒的な権威をもつ男性の視線と、フィールドで具体的な知見をたくわえ抽象的かつ原理的な論争にも堂々と切り込む聡明な女性の視線が交錯する。フランソワーズ・エリチエが、女性の体験と世界観を代弁していると確信できる細部は随所にありますし、日本で大学教師として男女格差を痛感しながら生きてきたわたしにとって、これはじゅうぶん感動的な風景です。 さて、感動して終わりにするのは、やっぱりやめて――妊娠・出産・家族について、あるいは生殖医療と人権について、あるいはまた少子化という「国難」(!)について、行政や立法や司法の現場であれ、研究機関であれ、男性が9割を占める組織で、しかるべき議論ができますか? 1割しかいない女性はたんなるアリバイか、せいぜいインフォーマントの扱いになってしまうでしょう。またもやふつふつと怒りがこみあげてきましたけれど、じつはおわかりのように、数字だけの問題ではないわけです。 このさい元気よく手を挙げて「今度はネクタイじゃなくてスカーフにしましょうよ!」とか宣言する女性が、ぞくぞくと現れてもよさそうに思うのだけれど。求められているのは「指導的地位」に見合ったゆたかな知見と繊細で力づよい論理です。 *1 工藤庸子・蓮實重彦『〈淫靡さ〉について』羽鳥書店、2017年 *2 フランソワーズ・エリチエ『男性的なもの/女性的なものⅠ――差異の思考』井上たか子・石田久仁子 (監訳)、神田浩一・横山安由美 (訳)、明石書店、2017年 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.