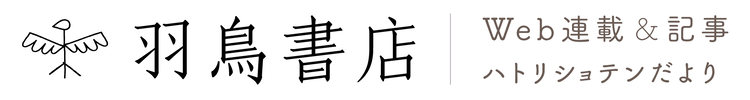|
In our time Proust was wholly androgynous, if not perhaps a little too much of a woman. (現代でいえば、プルーストは完璧な両性具有、女性の割合がやや勝ちすぎているかもしれないけれど)――こんな名台詞を読むと、じんわりと嬉しくなりません? 出典は、わが愛読書ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』ですが、この一言がジェンダーの歴史において画期をなすことの理由は、「近代的=二元論的」な性差の概念を、いとも軽やかに廃絶してしまったから。そこで、引用をもうひとつ。 The best woman (is) intellectually the inferior of the worst man.(いちばん出来のいい女子でも、知性としては、いちばん出来のわるい男子に劣る)――これも同じエッセイのなかの台詞。といっても発話者はもちろん著者本人ではなく、ケンブリッジのさる大物教授だとか。こんな話がウルフにあるのよ、と友人の若い女性編集者に紹介すると、屈託のない笑いが返ってくるのだけれど、そしてウルフ自身もユーモアと皮肉がはじけるような文体でこれを書いているのだけれど、でもね、わたしとしては身に覚えがあるのです。 「プルーストが女にわかるか?」という、昔々、わたしが学生だったころ、雑談のなかで男子学生たちが得意気に口にしていた台詞。くり返し紹介しているのは、恨みがあるからでは全然なくて、その論理構造が客観的に興味深いから。そもそも女性は芸術の鑑賞者であるべきで文学や詩の創造という主題はあまりに高踏的で理解できまいという、今日でも解消されたわけではない古色蒼然たる紋切型が透けて見えるのだけれど、それだけではない。なにしろ『失われた時を求めて』は「男性同性愛者」の書いた「芸術家小説」なのであり、したがって女性は性と知性において二重に排除されている、という理屈。つまり「男性同性愛」というのは二重に「純化」された男性性? プルーストは男のなかの男? 問題の男子学生たちが無意識に依拠していたと思われる見取り図を、とりあえず「排除的性差」×「序列的性差」によるジェンダー概念と定式化しておきましょう。 ウルフは多少とも両性具有的でない人間は、ダメだと言っているのですよ。「偉大な精神は両性具有」という表現は、コールリッジからの借用だそうですが、そのコールリッジを含め、人間と世界を理解した両性具有の王者はシェイクスピア。一方でワーズワースとトルストイは「男性の割合がやや勝ちすぎている」とのこと。ここで、ウルフさま、よくぞ言ってくださいました、という感じの、三つめの引用を。 It is fatal to be a man or woman pure and simple; one must be woman-manly or man-womanly(男でしかない男、女でしかない女は救いようがない。だから男っぽい女、女っぽい男になりましょう!) 女性作家の軽いジョークを紹介しているわけではありません。『自分だけの部屋』が刊行されたのは1929年。イタリアではムッソリーニがファシズム体制を着々と築いており、ヒットラーの大統領選出馬とナチ党の躍進は3年後。テクスト上でもヨーロッパの政治的な緊張を横目で睨んだエピソードとして「両性具有」という話題が導入されているのです。著者にとって女性排除の二大巨頭はナポレオンとムッソリーニ。個人の性格や特質ではなくて、二元論的な近代を構築した人物とその延長上で人類の災厄を招こうとしている人物という位置づけです。「文学」に身をおく者として、男性中心的な「政治」と「歴史」をいかに批判し、相対化して、プルーストの体現する「文学」の尖鋭な革新性をいかに際立たせるか。ウルフの称揚する創造的な「両性具有」とは、そのための戦略的キーワードにほかなりません。 ためしに「排除的性差」×「序列的性差」という定式の語彙を一部入れ替えて「排除的エスニシティ」×「序列的エスニシティ」としてみましょう。同じ論理、同じ力学によって、ヨーロッパが国民国家の内部からユダヤ人という他者性を析出したことが想像できるはず。さて唐突ながら、ここで読みおえたばかりの樋口陽一『抑止力としての憲法』(*1)からカール・シュミットにかかわる段落を抜書きしてみます。 シュミットは、「友・敵」関係の中に集合体を登場させた。彼が好んで言及する集合体が教会と労働組合、より基本的には階級である間はまだしも、「友・敵」関係は流動する可能性のもとにおかれている。それに対し、ひとたびartig(種的)なもの――種類、ジャンル、ジェンダー――の間の「友・敵」が問題となると、敵対関係は固定する。さらに特定的に、völkisch(純ドイツ民族であること)なものに対置された「ユダヤ人」は、一体として否定されることになる。「最終解決」「根絶やし」、ことばの正確な意味でのgenocideは、その帰結であった。
二つのことを考えました。第一に、特定の集合体のアイデンティティを排除的な分類によって描出し、根拠づけるプロセスは、それ自体が権力的な行為であり、これに集合体のアイデンティティと個人のアイデンティティを同一視するという強制力が伴えば、恐怖政治や全体主義的な運動へのエスカレートは避けられない。これに対し、プルーストの世界においては、バルザックの登場人物がそうであったように「個」は「集合」の代表ではないし、そもそも特定の所与として個人のアイデンティティを描出するという作業からこれほど遠い近代小説は前例がないともいえる。それゆえ『失われた時を求めて』の夥しい登場人物を異性愛や同性愛やバイセクシャルやトランスジェンダーなどの男女に分類整理して考察することは、ウルフのような両性具有的思考からすれば、やや物足りない作業とみなされるかもしれません。いっそのこと、シャルリュスひとりの肉体に秘められた底知れぬ両性具有性――分類を拒む性――にひたすら魅入られる場に留まったほうがよい・・・・・・、という脱線は、ここまでとして。 第二に、だからといってプルーストとともにウルフやコレットなどの名をあげて、世代的にはカール・シュミットよりやや年長でありながら、これらの作家たちは早くも全体主義的な排除的思考を乗り越えていたと吹聴することには、あまり意味がない。上記引用のテクストにつづく問題提起は「シュミットにとって決定的に重要だったのはつまるところ、単一・不可分の政治統一体を創り出し維持するための決断それ自体だったのではないか」というもの。この疑問に対し『抑止力としての憲法』の著者は、シュミットは「具体的法的判断」においては「内容を問わない」決断主義に走ったという批判で応えているのですが、この「決断」を迫られるのは「政治」であって「文学」ではない。意見さえ求められず「決断」の主体という資格をもたぬらしい「文学」は、それでもつねに「具体的な内容」を問いつづける、と言い添えることもできましょう。 ところで、ひとたび「政治」という枠組みが設定されれば、小説は近代的なアイデンティティの問題を超克してしまったなどと嘯くわけにはゆきません。個人のアイデンティティが定義されなければ「政治」も「法」も国民を保護することはできない。たとえ虚構であろうと、ユダヤ人と非ユダヤ人の境界線は引かれなければならない。だからこそ、男と女が同居しているのではなく両者の境界線を溶解させてしまったシャルリュスは、存在様式そのものが違反的なのだ・・・・・・、とこれも指摘するにとどめます。 そろそろ「文学」や「政治」という枠組みをはずし、気儘に「両性具有」の探索をつづけましょう。まず思いつく問いは――「両性具有」の女性? ウルフとコレットがプルーストと同世代でドレフュス事件の時代に生きたことは偶然ではないと思われますし、ウルフの夫、コレットの3番目の夫はユダヤ人です。一方でナポレオンに対抗したスタール夫人は当然ながら「両性具有」だったとわたしは確信していますが、20世紀でいえば、筆頭はハンナ・アーレント。なにしろ一週間ほどまえにエリザベス・ヤング=ブルーエルによる浩瀚な評伝(*2)(二段組630ページ!)を読了し、まさに「脱帽!」したところなのですから、自信たっぷり、一方的に宣言しておきます。いろいろと考えるところはありますが、当面は兆候、あるいは状況証拠のみをメモ。 第一にアーレントはヘビー・スモーカーで若いときに「黒いハバナ葉巻」なんかをふかして、最初の夫ギュンター・アンダースはたいそう嫌がったとのこと。 第二に二番目の夫ハインリヒ・ブリュッヒャーは非ユダヤ人でありながらアーレントに同伴してアメリカに亡命し、ひたすら話し言葉によって、つまり書き言葉は妻にまかせ、ゆたかな知的共同体を育んだ。歴史に例がないほど絶妙な「両性具有」的カップルだったと推察されるのです。 第三に、そしてこれが長い時間をかけて考察すべき論点の予告となるはずですが、アーレントの思考は「三拍子」です。シュミットの加担してしまった「友・敵」関係が強固な排除的二元論を構成することを思い出していただきたい。対するユダヤ人亡命者アーレントは、書物も三部構成、キーワードも三つ――『全体主義の起源』が『反ユダヤ主義』『帝国主義』『全体主義』から成ることはいわずもがなだけれど、それ以前に「政党・運動・階級」という論文を書いている。かりに書物の章立てが三部構成になっていなくとも、「労働/仕事/活動」「私的領域/社会/公的領域」「判断/思考/意志」といったキーワードの布置が――ヘーゲル的な弁証法の論理を遠ざけて――柔軟で強靭な思考の場を保全しているように思われます。時間の感覚も然り。「過去と未来の間の裂け目」にカフカ的な「現在」があらわれて「過去/現在/未来」という「三拍子」が編成されるプロセスは『過去と未来の間』の幕開け、美しい「序」の文章に記されています。 *1 樋口陽一『抑止力としての憲法――再び立憲主義について』岩波書店、2017年 *2 エリザベス・ヤング=ブルーエル『ハンナ・アーレント伝』荒川幾男・原一子・本間直子・宮内寿子訳、晶文社、1999年 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.