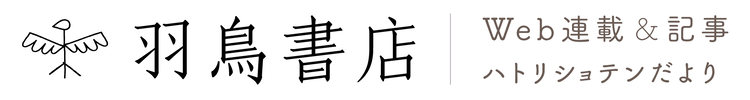|
「いや要するに、マダム、貴女方は何も不平をおっしゃるには及ばないのですよ」と彼は意味ありげに微笑しながら言葉をつづけた。「魂はお持ちだと認めてさしあげたのだから。ご存じのように、決定しがたいという哲学者もおりますよ。平等だとおっしゃりたい? それは狂気の沙汰ですな。女というのはわれわれの所有物(propriété)であるが、われわれは女の所有物ではない。女はわれわれの子供を作ってくれるが、男が女の子供を作ることはない。それゆえ、実のなる木がその木を育てる庭師のものであるように、女は男の所有物である。男が妻を裏切って浮気をしたら、正直に白状して、後悔すればよい、それできれいさっぱり跡形も残らない。女房は怒るかもしれないし、赦すかもしれないし、あるいは適当に折り合いをつけるかもしれない、それで得をすることだって、たまにはあるだろう。ところで妻の浮気となると、そうはゆかない。白状して、後悔しても、なんの意味もない、きれいさっぱり跡形も残らないなんて、誰が保証できますか? なされた悪は修復できない。それゆえ女は身に覚えがないと言い張るべきであって、ほかにやりようはない。そうしたわけで、マダム、お認めいただけるでしょうが、よほど判断力がないか、俗っぽい考えに囚われているか、教養が不足しているか、というのでないかぎり、妻が自分の夫とあらゆる点において同等であるなどと考えるようになろうはずはないのです。だいいち、相違があるからって不名誉なわけではありませんよ。それぞれに特性と義務というものがある。貴女方の特性は何かといえば、マダム、それは美であり優雅であり魅惑である。貴女方の義務は何かといえば、それは従属と従順である」 「語られる言葉」の肉声を思い浮かべながら、こんな感じかなあ、と日本語に移し替えているだけで、じわじわと、かなり、腹が立ってきました。19世紀フランスの「姦通小説」のロジックがここに凝縮されており、今日的な「セクシュアル・ハラスメント」の原点もここにある。出典はラス・カーズの『セント=ヘレナ覚書』(1823年)――でも、録音機器もなかった時代に、これが退位した皇帝の台詞をそのまま「書かれた言葉」に移し替えたものだという保証がどこにある? 著者のラス・カーズが巧みに造形したフィクションかもしれないでしょ? という抗議の声が聞こえてきそう。じつは2017年の末に、この『覚書』の元原稿とみなされるラス・カーズの『日記』が初めて書物のかたちで公開されました(*1)。これは近年のナポレオン学の興味深いトピックなのですけれど、その話は後回しにして‥‥‥。女性蔑視の見本のような長い台詞のキーワードはpropriétéであるという観点から分析したいと思います。 ご存じのように近代法の基本原則とされる「私的所有権」private property / propriété privéeを体系化したのが、ナポレオンの名を冠した1804年の民法典なわけですが、ある歴史家の言によれば、フランス革命の精神――「法の前の平等」「所有権の不可侵」「経済活動の自由」等――を見事に制度化した法典にも「時代遅れ」な部分はあった、なぜなら女性は法的な主体と認められず「妻の地位」が低くなったから、とのこと。この記述を読んで、わたしは唖然としました。まるで、その「時代遅れな一面」をちょいと手直しすれば――痛む虫歯を1本抜くみたいに――問題は解決するといわんばかり。民法典は社会の「秩序」を支える構造体なのだから、たとえば「妻が夫の所有物」であるような家族像と、これを包摂する「ジェンダー秩序」を解体し、全体を再構築しなければダメなのです。ヨーロッパは2世紀をかけてそれをやってきた‥‥‥。なんてこと、その歴史家は、考えもしないのでしょうね。上記ナポレオンの台詞も、たしかに「時代遅れ」だけど、こういうことをヌケヌケと言えた昔の男は気楽だよね、という顔をして――それこそ「意味ありげに微笑しながら」――読み飛ばすかもしれない。そういう男性、皆さんの身の回りにはいないと断言できますか? 女もひとりの人間であるのなら、男のpropriétéにはなりえない。そう断言したのは、スタール夫人です。ナポレオンに国外追放され、レマン湖の畔コペの城館で軟禁状態にあったとき書き始めた『自殺論』(1812年)のなかで展開される議論です。おりしもベルリン在住の著名な劇作家クライストが人妻と心中するという事件が起きて、これがロマン主義的な愛の崇高なる成就であるかのような論調が世論を支配した。スタール夫人は賛美の風潮を批判して、男が女をピストルで撃ち、ただちに自殺したというけれど、たとえ女の合意があったとしても、人間の意志などは一過性のものだから、これは正真正銘の殺人であり、他人の生に対する「残忍な所有」féroce propriétéにほかならないと指摘したのです。自立した個人とは何か、という問いかけでしょう。人は人を所有できない。人は他人の生を神聖なものとみなし、独りで死んでゆく人間の孤独を引き受けなければならない――スタール夫人の主張は普遍的に、つまり男にとっても女にとっても正しいのではありませんか? そしてこれはまた、徹底した「反ナポレオン」の哲学ともいえる。もちろん、ご紹介したナポレオンの台詞が本人の本音であると仮定しての話ですが。 結論を先に言ってしまえば、捏造されたフィクションではなかろう、と考えています。ラス・カーズはナポレオンより3歳年上でスタール夫人と同い年の1866年生まれ。スペイン系の貴族で海軍に入り、革命が勃発すると反革命軍に身を投じて英国にわたり、1802年に帰国を許され、ナポレオンの宮廷で侍従となる。その後は百日天下の前後も忠誠がゆらぐことなく、セント=ヘレナへの随行を許された。といっても、侍従などは80名ほどいたらしく、参事院(コンセイユ・デタ)の一員にはなりますが、側近の大物政治家ではありません。
この先は想像力を働かせることをお許し願うとして、ナポレオンはプロパガンダの天才です。ジャック・ルイ・ダヴィッドなどの天才画家に治世の名場面を描かせたことからも、そのことは知れるはず。有能な文官で文筆の才もあり英語に堪能なラス・カーズが、コミュニケーション・広報担当として、3人の将軍とともに元皇帝の随員となったことは疑いようがない。結果として『セント=ヘレナ覚書』がダヴィッドの名画に劣らず生々しい衝撃をもたらしたことも確かでしょう。「ボナパルティスム」という今日も生きている言葉と概念が生成したのは、「ボナパルティストの祈祷書」などと呼ばれるベストセラーに育まれてのことであるからです。 ナポレオンが大西洋の孤島で厳しい幽閉生活を送った68カ月のうち、ラス・カーズが生活を共にしたのは、わずか14カ月に過ぎません。おそらく聞き上手、話し上手で、お気に入りのお相手だったのでしょう。日々の生活風景や屈託のない雑談から世界統治の野心まで、ジャンルを問わず書き留めたのが『日記』と呼ばれる原稿です。ただしこの原稿は、ラス・カーズが島の総督ハドソン・ローに睨まれて投獄されたとき、当局に没収されてしまいました。返却されたのは、ナポレオンの死の半年後、1821年の秋。長い苦労の末、疲労困憊してフランスに帰還したラス・カーズは、取り戻した原稿を元にして、大車輪で『覚書』を執筆し、1823年の末までに8巻本を刊行します。 このとき返却された元原稿は、行方知れずになり――破棄されたのかもしれず――いまだに見つかっていません。では、2017年に公開されたのは何なのか? じつはハドソン・ローに没収された原稿は、英国に送られ、ただちにコピーが作成されていたのです。大英図書館に人知れず眠っていた端正なコピーが、偶然21世紀のナポレオン研究者の目にふれた。そこで、皆が大興奮したというわけです。 元原稿の『日記』と刊行された『覚書』の異同ということが、当然、問われるでしょう。なんと分量が2倍半に増えています! といっても増えた分は捏造だろう、もとの『日記』のほうが文書としての信憑性は高く、史実に近いはず、などと単純なことを考える歴史家は、さすがにいないでしょうね。この比較は、文学的にも、なかなか面白そうなのですが、いずれ別の機会に本腰を入れて‥‥‥。 プロパガンダの天才という話にもどりましょう。そもそも、ラス・カーズが1816年の末に島の総督によって投獄された経緯が、いささか謎めいているのです。囚われの皇帝の近況を本国にもたらすために、ヨーロッパへの強制送還を目論んだ周到な策略ではないか? と仄めかす実証研究もあるほどです。退位したナポレオンは、まだ40代の若さ。この先、ヨーロッパで重大な政変がある可能性だって皆無とはいえないし、この地で死ぬ覚悟を決めるとしても、輝かしいナポレオン伝説を創造しておけば、子や孫の代に千載一遇のチャンスが訪れるかもしれないのだから、と元皇帝が思いを巡らせたとしても、不思議ではないでしょう(この夢は第二帝政によって実現します)。 そうなると、あらためて気になるのは、ナポレオンとラス・カーズとの関係、絶対的な崇拝と信頼にささえられた男と男の関係です。いや何よりも、ナポレオンが『日記』の存在を知っていたのかどうかを確認したい――じつは知っていました、それも早い時期から。原稿に目を通したこともある、と『日記』に記されているのです。だとしたら、記録映画を作る監督とカメラをまえにした主役の関係に似た、ある種の共犯関係があったかもしれない、という気がしてきませんか? 共犯は大袈裟だとしても、暗黙の合意と協力はあったにちがいない。以上の理由で、冒頭でご紹介したナポレオンの台詞は、本人の本音であると考えた次第です。むしろ、ナポレオン自身が演じた然るべきナポレオンの肖像、といったほうが正確かもしれません。 それにしてもカメラはおろか、録音機器もなかったという事実は重要です。ちなみにセント=ヘレナで時間をもてあましたナポレオンは「口述筆記」でイタリア戦役やエジプト遠征にかかわる「回想録」を作成しています(今では学問的な校訂版で読むことができるけれど、あえて言うなら全く面白くないこと自体が面白いというタイプの文献で、研究者でさえ注目しないように見える)。読み比べてみれば、文体の違いからして、ラス・カーズの『日記』は「口述筆記」ではないこと、つまりナポレオンが現場で書き取らせたものではないことは明らかです。じつは自然体の長い会話のあと、その記憶を大切に自室に持ち帰り、ただちに息子に「口述筆記」をやらせたらしい。15歳の少年をまえに、ナポレオンが乗り移ったみたいにラス・カーズがしゃべって、少年が懸命に書き取りをした、と空想するだけで、なかなか楽しいですね。 ご紹介した台詞について『日記』と『覚書』を照合してみましたが、主な変更は「彼は意味ありげに微笑しながら言葉をつづけた」という地の文の挿入のみ。ナポレオンの笑い方についてはen souriant de côtéとなっている。ひとしきり訳語に迷ったのち、英訳のsmiling significantlyという解釈を借りました。ともあれ、このささやかな加筆にも、作家の芸は見てとれます。 さてナポレオンとは、ブルジョワジーがヨーロッパの覇者になる19世紀の幕開けに、その制度的な基盤を怪物的な力量で創設してしまったヨーロッパの覇者にほかなりません。元祖ブルジョワジー? まさにそうではないかという気がしているのです。所有権の対象になるのは、私有財産だけではない。知的な資源も高等教育も男性が独占する。女性は政治からも社会経済的な活動からも排除され、男性の所有物になる。その結果、ナポレオンとラス・カーズとの関係に典型が見られるように、男性間のホモソーシャルな結びつきと崇拝の感情が顕揚される。そして一方では、強靭なミソジニーがはびこることになりました。 ここで話題は2018年の日本に着地します。そのようなブルジョワジーの秩序が破綻して、もはや政治と社会経済的な活動から女性を排除することはないという一般的な了解が成立した以上、一足先に権力の座に就いた中高年の男性たちも、何かが根底から変わりつつあることを理解していただきたい――これが、眩しいほどに活動的になった若い女性たちの切なる願いであろうと考えます。某大学運動部のケースも某高級官僚のケースも、組織のメンタリティという意味で、元祖ナポレオン時代のようではありませんか。 振り子のようですが、最後に2世紀前の胸のすくエピソードを――あるときボナパルトが、ひとりの名高い女性のまえで仁王立ちになり「マダム、私は女たちが政治に口出しするのは好みません」と喝破した。相手は「ごもっともですわ、将軍、でも女たちが首を斬られる国では、斬られる理由を女たちが知りたがっても当然ではございませんか」と痛快な答えを返したという。 将軍ボナパルトがクーデタにより政権を奪取する直前の出来事であろうと思われます。「名高い女性」とは、恐怖政治の犠牲になった思想家コンドルセの美しい未亡人。出典はスタール夫人の『フランス革命についての考察』という千ページもある堂々たる革命論ですが、つづくコメントによれば、このとき将軍は反撃しなかった。つまり「真の抵抗」こそが、権力との対決において有効なのであり、そのことを各自が肝に銘じるべきだとのこと。昔の女たちも、しっかり、聡明に闘っておりました。 *1 Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène. Le manuscrit retrouvé, Texte établi, présenté et commenté par Thierry Lentz, Peter Hicks, François Houdecek, Chantal Prévot, Perrin, 2017. コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.