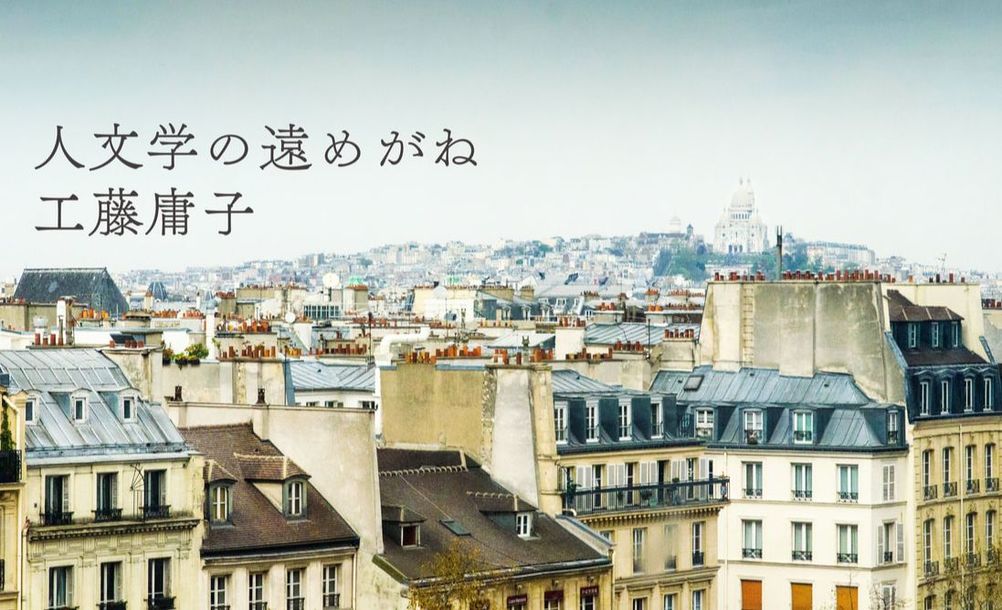|
「個人全集」は何のために編まれ、刊行されるのか、考えてみたことはありますか? それは「特別なできごと」であって「その作家の大御所としての地位を出版市場を通じて改めて確認するだけでなく、文学研究にとっては、出版社の入念な編集作業を経たその作家の仕事の全容を見渡す、新たな立脚点が得られることを意味する」というのは、『大江健三郎全小説』の初回配本、第3巻の巻末に収録された論考(*1) の冒頭にある言葉。筆者はドイツ人の日本文学研究者であり、大江文学は「世界文学」として読まれてほしいと願う者として、異論はありません。 たとえば「丸山眞男全集」など、大学の学問を背景とした「全集」を、比較の例としてみましょう。著者が生前にみずからの業績を整理・選別して刊行することもあり、死後に弟子たちが編纂にかかわることもありますが、とりわけ後者のケースでは、学知の継承という抽象的な行為が、さながらブルジョワ社会の遺産相続にも似た波紋を呼び起こすこともないではない。選ばれた「弟子」と「大御所」とのあいだには「父と嫡出子」のような認知の関係があるのではないか、それが「学問の制度化」を招くのではないか、といった屈折した論評は、しばしば聞かれるところです。 文学の個人全集には、そういうことはない? でも「漱石全集」なら日本文学や比較文学の領域に膨大な「漱石学」の蓄積がありますから、大学の学問的権威を体現する編集企画を立てること自体は、他分野と同じく可能でしょう。一方、出版社が主導して、文壇で活躍する作家たち、評論家たちの解説とともに、主要作品を刊行することもできる。いずれにせよ「全集」の刊行に寄与する編者や解説者と作家との組み合わせ自体に、研究者間の知的血縁関係の開示のようなドラマを見てとる人はいないと思われます。 つぎに存命中の作家の特徴ある一例を。チェコとフランスで人生の前半と後半を過ごしたミラン・クンデラが、2011年にガリマール社のプレイアード叢書に入りました。長い伝統に逆らった破格の編集なのですが、ノーベル賞か、アカデミー・フランセーズか、それともプレイアードか、と昔は冗談にいわれたほど「権威」ある叢書ですから、この企画がすんなり通ったとは思われない。叢書の標準的な形式を破壊しているのです。著者の選択した小説や評論の決定版の総体が、著者自身が最終的に認知した「作品」(単数形のŒuvre)としてヴォリュームのほとんどを占め、注釈や草稿や改稿のたぐい、「年譜」や「評伝」などの情報は全て潔くカット。遠いカナダ在住の比較文学者によるBiographie de l’œuvre(「作品の作られた事情と方法」という感じか)と題した控えめな「作品解説」が巻末についている。 この簡素な造りに秘められた強い意志とは何か? カフカの遺稿をめぐる批判的なエッセイ『裏切られた遺言』をお読みになった方は、言われるまでもない、とお考えでしょう。遺言によって破棄されたはずの草稿を根拠に「作品」が他人の手で改竄されること、死後に本人が与り知らぬ恣意的な解釈に曝されることは、断じて拒絶・回避するという宣言。「全体主義」の時代のチェコで、「検閲」と親密圏への権力の介入を体験しつつ作家になった人の「防衛」の仕草のようにも見える。しかし、ここまで徹底した「作品」の囲い込みに違和感を覚え、こんなふうに、みずからの「遺言」の「執行人」までやってしまうとは ?! と妙な切なさを感じる人もいるようです。若き友人の言によるなら、プレイアード叢書はどことなく「柩」に似ている‥‥‥。 「おそらく最後の小説」であると大江自身が言う『晩年様式集』の最後に近いページで、「三人の女」の一人によって、暗示的な言葉が発されます。「人生のしめくくり(原典は下線ではなく傍点)」をクンデラの「作品」(「ウーヴル」とルビ)に達成する――引用だけではわかりにくいかもしれないけれど、「作品」の決定と開示・刊行が、しめくくりの営みとなるはず、ということでしょう。 7月に刊行され始めた『大江健三郎全小説』の「モデル」がクンデラのプレイアード版だろう、などと言いたいわけではない。当然のことながら「全集」編纂の構想が、文学の真価を保証するわけではないし、じつはクンデラの「作品」論には、イデオロギー的権力論の限界と退屈さのようなものが看取されるのではないかという気もします。それはそれとして、二つの「全集」を比較してみたら面白いかな、とは思う。そもそも注や関連資料を排した「簡素な造り」は似ているし、「大江健三郎年譜」が別添で折込みになっているのは、クンデラの場合と同じく、「作品」は作品として自立している(小説は作家の人生の反映・反芻ではない)という趣旨でもあろうと考えます。わたしの手元にあるのは第3巻のみですから、無責任な予感のような話だけれど、クンデラの全集に「全体主義」との闘いの痕跡が見てとれるとしたら、大江の全集は「戦後民主主義」の精神を裏切らぬものとなりそうです。何であれ「権威」や「権力」に対しては距離を置くとか、女性と外国人の参加とか‥‥‥。でも、この点は、すでに(1)と(2)で論じましたから、最後に「全小説」という枠組みと、「小説家」と「作家」の関係について考えてみることにします。
それというのも「小説家」と「作家」は同じではない。当りまえ? でも定義はむずかしいですよ。大江健三郎の場合、本人の用語法は明快です。『私という小説家の作り方』(1998年)を『大江健三郎 作家自身を語る』(2007年)と読み比べてみればわかる。後者は、この度の「全集」で解説をつとめる尾崎真理子さんがインタビュア(聞き手・構成)。帯には「作家生活50年を語りつくした、対話による自伝」とある。口絵写真には、渡辺一夫から贈られた額のまえで執筆する「作家」の姿、エドワード・W・サイードの横顔などが飾られた書斎、家族とのひととき、故郷の風景、等。「作家」の中核をなすのが「小説家」であることは自明として、「作家」は生活者でもあるから、巻末では「一番好きな季節、お天気は?」「一番好きな花、樹木は?」「一日で一番好きなひとときは?」といった質問にも立ち向かう。政治的な選択をした社会人として、広島や沖縄や福島をめぐる市民運動にかかわり、発言し、さらに関連の本を書くのも「作家」の仕事。文学の功績によりノーベル賞を受賞するのも「作家」です。 さて『私という小説家の作り方』は、もともと『大江健三郎小説』全10巻(新潮社1996~97年)のために書かれた「月報」の文章です。第8章「虚構の仕掛けとなる私」によれば、一般に日本で「私小説」と呼ばれるのは「一風変わった告白癖のある人間」の書くものであり、そのような「小説家とは、ドキドキするような私の秘密について語らずにはいられぬ人間」「いったんそれを語り始めると、どのようにでも図々しくなり、語りつづけて倦まない人間」であるとのこと。このような「私小説」の伝統に対する自覚的な距離を語る文章を引用します。 『懐かしい年への手紙』への展開で、その後の私の小説の方法に重要な資産となったのは、自分の作ったフィクションが現実生活に入り込んで実際に生きた過去だと主張しはじめ、それが新しく基盤をなして次のフィクションがつくられる複合的な構造が、私の小説のかたちとなったことである。この点において、私は日本の近代、現代の私小説を解体した人間と呼ばれていいかも知れない。 フィクションと現実の境界があいまいになるというだけの話ではない。「私」が「虚構の仕掛け」となることで、一つのフィクションが書かれるたびに、次なるフィクションに取り組む新たな「小説家」が卒然と姿を現すかのようなのです。いいかれば「小説家」が「小説」を作るというより、「小説」によって「小説家」が「作られる」のではないか――これが『私という小説家の作り方』の示唆するところであるように思われて、今回は「fictionとしての「小説家」」という言葉をタイトルに掲げてみたわけです(横文字を使うと、「作り出されたもの」という語の原義に立ち返ることができそうな気がするので)。 近代ヨーロッパの伝統には「芸術家小説」という確固たるジャンルがあります。作家志望の青年が、芸術とは、文学とは何か、とみずからに問いながら、人生経験を積む、そのプロセスが「修行時代」として報告されるもの。ジョイスの『若き芸術家の肖像』はその代表でしょうが、プルーストの『失われた時を求めて』も、あまり知られていないフローベールの初期作品『初稿感情教育』も、そのような読み方ができる。ただし、ここでは大江健三郎のいう「小説家」との相違を強調することだけが重要です。 くり返すなら「芸術家小説」は一般に「芸術家」の誕生を、つまり「書きはじめる」までを回想する物語です。ところが大江は『晩年様式集』のなかで「小説」を「書きやめる仕掛け・様式」を「小説家」に考案させている。やはり「小説の歴史に前例がない」のではありませんか? 『大江健三郎全小説』15巻が刊行されたとき、クンデラの用語でいう大文字・単数形の「作品」が全貌を現すことでしょう。それだけでなく「「作品」のBiographie」を超えるものとして、また、いわゆる「作家の評伝」とも異なる次元に、真に迫力ある「「小説家」のBiographie」が浮上するのかもしれません。「同時代人」たちが生きた昭和・平成の持続する長い時間のなかで、透徹した「時代精神」の語り手でありつづけた「小説家」‥‥‥。 *1 日地谷=キルシュネライト・イルメラ「「政治少年死す」若き大江健三郎の「厳粛な綱渡り」ある文学的時代精神の “考古学”」 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.