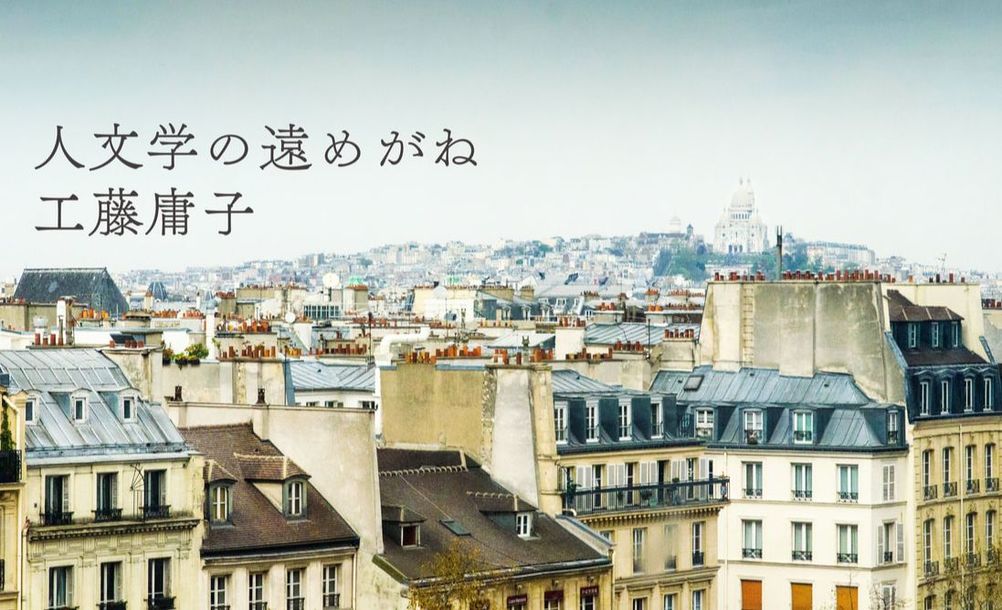|
――これをもってブログは最終回とさせていただきます。 15回の連載記事に書下ろしエッセイを添え、2019年の春に出版予定です。 *本連載は、工藤庸子『女たちの声』として書籍になりました(2019年6月)。 昨年の夏、羽鳥書店から〈淫靡さ〉をめぐる小さな共著(*1) を出版しましたが、その書物と全く無縁ではないものの、このブログの流れからすれば、見出しは「続・女のエクリチュール」としてもよい。前回に述べたように山田登世子さんは、日本で初めて〈批評〉の領域に斬りこんだ稀有な女性でした。同時代を生きた自分の人生をふり返りながら、そのことをあらためて考えているところです。『メディア都市パリ』は、著者の言葉によるなら「戯れのエクリチュール」によって「ファロスの王国」に挑戦したものであり、世に言う「再評価」とは異なる文脈で、そう、ここはいささか大上段に構えることをお許し願うとして、戦後日本の〈批評〉における女性的な言説の希少なプレゼンス――正確には、ほぼ全面的な不在――という歴史的な事実をふまえ、今現在の文脈で、その華麗な演技を読み解いてほしいと願っています。 「続・女のエクリチュール」は、その〈批評〉と対になる〈小説〉について。こちらは現代日本にとらわれず、コレットとウルフ。主題はテクストの「決定的な細部」としてのゼラニウム、その微かに淫靡な匂い。じつはこの話、以前にちょっとふれたことがあり、そこではフローベールとプルースト、いずれも両性具有的な傾向のある男性作家がちらりと姿を見せています。本題への導入として、まずはコレットのアカシアを。 代表作『シェリ』(1920年)の極めつきの場面。ご存じのように、ヒロインのレアは引退したココット(「高級娼婦」とか「粋筋の女」とか訳される)。息子ほど歳のちがう美青年と恋に落ち、何年か生活をともにしたのち、その美青年に結婚話がもちあがるというのが幕開けの状況です。その冒頭から時計をまきもどして馴れ初めの季節。夜の庭園からさっと吹きこんだアカシアの香りに誘われて、初めての口づけが交わされるというだけの場面なのですが――その香りがあまりに能動的(si active)だったので、吹きつけた香りの歩みを目で追うかのように(comme pour la voir marcher)ふたりはそろってふりむいた。「薔薇色の房のアカシアだわ」と女はつぶやき、青年はこれに応じて「しかも今夜はオレンジの花の香りをたっぷり吸いこんでいる」とひと言。あまりに繊細な感覚に、ふと胸を突かれた女が青年の顔を見つめると、恍惚とした生贄(いけにえ)のような表情が浮かんでいる。青年がレアの名を呼び、レアが近づき、そして長い接吻の陶酔が過ぎたとき、睫毛のあいだにキラキラ光る二粒の涙を浮かべているのは青年の方。 男が女の唇を奪うのではありません。レアの仲間のココットの私生児であるシェリは、美形という意味では絶品といえますが、じつは甘やかされた悪ガキで、早くも放蕩に疲れている。一方のレアは「三十年のあいだ輝くばかりの若者と傷つきやすい思春期のためにつくして」きた自分に「清潔感と誇り」をおぼえている聡明な女。思えばハリウッドの恋愛映画もヨーロッパの近代小説も、ひたすら男に唇を奪われ所有される女たち、お決まりのように恋人に去られて深く傷つく女たちを、それこそ無数に生産してきたのだから、やはりコレットは革命的に新しい(ついでに強調しておきたいのは、偉大なジョルジュ・サンドをふくめ女性作家たちの大方は、男性の期待に応える「告白小説」というスタイルを捨てきれずにいたという事実です)。愛と別れの物語でありながら、レアとシェリの関係は所有欲とも心理的な必然性とも無縁な出来事として推移するように見えるのです。ふたりがこうなってしまったのは、ただ単に、さっと室内に吹きこんだ生々しいアカシアの香りのせいだといわんばかり。 蜜蜂をおびきよせるアカシアの甘くかぐわしい匂いは、そうしたわけで、この小説の「決定的な細部」であると断定できそうです。しかも豪奢な「薔薇色」の品種。ここではアカシアの一般的な色は白という了解が暗黙の前提となる。acacia à grappes roséesという原文は、言葉の響きからしてもワインの「ロゼ」のような色合いを思わせるのでしょう。でも女が独り言のように小声でつぶやく台詞なのだから、訳者としては説明的な言葉で〈声〉のリズムを損ないたくはない。「ロゼのような淡い薔薇色の房のアカシア」とか「薔薇色がかった白の房のアカシア」とか、さんざん考えた挙句、いさぎよくあきらめることが、翻訳の宿命であるように思います。 さて、その対極にある、もうひとつの「決定的な細部」は「薔薇色のゼラニウム」。こちらはgéraniums- rosats――見慣れぬ言葉だなあと思って大きな辞書を引くと、この表現がそのまま引かれて用例に載っている。それほどにコレットは語彙が豊富、微妙なニュアンスのお手本として参照される作家なのですが、ちなみにrosatという単語の定義は「薔薇色の」de couleur roseというだけで、これだから辞書は役に立たないという見本のようなケース。おそらくは、よくある濃いめのピンク。「ロザ」という音の切れ味ゆえに選ばれたのでしょうか。つづいてゼラニウムの匂い、ということになれば、コレットを語るまえに、ひと言プルーストに言及しないわけにはゆきません。 それというのも主人公の「私」が恋人のアルベルティーヌ相手にヴァントゥイユの天才を説明しようとするときに、その本質は「ゼラニウムの花のかぐわしい絹の肌」la soierie embaumée d'un géranium「楽曲のゼラニウムの芳香」la fragrance de géranium de sa musiqueといった語彙で語られる。しかも、アルベルティーヌと出遭った夏の思い出にも、こんな微妙な話があるのです。あるかなきかの卑猥さを含んだ娘の挑発的な笑い声を耳にして、疼くような不安をおぼえた語り手が、これを「ゼラニウムの匂い」に譬えている。その匂いの特性は「ちょっといがらっぽく、官能的で、秘密を明かすような」âcre, sensuel et révélateurと形容されています。ほかでも思いおこされるイメージによれば、プルーストのゼラニウムは、やはり濃い薔薇色であるらしく、なめらかな花弁の物質性が、健康な少女の頬の「肉色」carnationと結びつく。この言葉、語源的には文字どおり「肉の色」なのです。だからアルベルティーヌの不謹慎な笑い声が、体内の肉の壁をこすって、欲望を誘う粒子を運んでく‥‥‥などという、きわどい幻想が立ちのぼるのかもしれません。ともあれ「私」にとって、ヴァントゥイユの音楽は、薔薇や百合などのピュアで圧倒的な香りではなくて、いささか微妙な植物のフレグランスを放っているらしいのです。
それにまた、ゼラニウムは花に固有の香りはなくて、葉っぱをこすったときに強い芳香を放つという経験的な事実も強調しておかねばなりません。調べてみるとアフリカ原産のgéranium- rosatは、名称としては19世紀には知られており、薔薇の匂いに近い葉のアロマオイルを抽出しよう試みも早くからあった(*2)。とはいえ今では数えきれぬほどの園芸種が存在しますから、わたしたちが花屋で目にするゼラニウムから100年前のフランスで海辺や庭先に咲き誇っていた野生に近い植物の芳香を想像することは不可能に近い。わたしのテラスで10年来白い花を咲かせている小さな鉢植えも、期待するような「淫靡な匂い」を放ってはくれません。 それはそれとして、以上に見たようにプルーストの世界では、よく知られた「薔薇色のサンザシ」(幼いころ憧れの少女だったジルベルト)と対をなすかのように「肉色のゼラニウム」(思春期に出遭い性愛や嫉妬の伴侶となるアルベルティーヌ)という幻想が見え隠れする。コレットのアカシアとゼラニウムにも、ごくささやかながら、どことなく似た感じの対比が見出されるような気がします。というわけで長い回り道をへて、ようやく『シェリ』の本題に辿りつきました。結婚してしまった美青年への思いを断ち切るために、レアは南仏に旅立ち長い休暇をすごして早春のパリに帰還する。いくつもの出遭いや出来事を反芻し、一夜の情事を思いおこしたところ。 「馬鹿な男‥‥‥」彼女は溜め息をついた。 あのゆきずりの男の愚かしさは見逃してやるつもりだったけれど、自分に気に入られる術(すべ)を知らなかったことだけは赦せなかった。忘れっぽい肉体をもった健康な女である彼女にとって、もはやムッシュー・ロランは、いささか滑稽で、たいそう不器用なふるまいにおよんだつまらぬ大男でしかなかった‥‥‥。今となっては身におぼえがないとレアは言ったかもしれない。あふれる涙に目がかすみ――あれは薔薇色のゼラニウムのうえを、草の香に染まった驟雨(しゅうう)がころげおちる雨の晩のことだったが――ムッシュー・ロランの姿が一瞬かき消され、シェリの面影にすりかわってしまっていたことを……。 筋骨隆々の鈍重な大ばか者、とレアが心のなかで罵倒する相手は、ただの好青年なのですが、それはどうでもよいとして。問題は「薔薇色のゼラニウムのうえを、草の香に染まった驟雨がころげおちる雨の晩」certain soir de pluie où l'averse roulait parfumée sur des géraniums- rosatsという指摘。大粒の雨に打たれた叢(くさむら)から、もわっと青臭いゼラニウムの匂いが立ちのぼり、それが水滴に沁みこんでいるのでしょう。でも、誰がそんなことを確認しているの? もちろんレアでもないし、間抜けな大男でもない。そう問いかけながら、わたしは雨に打たれて宵闇にひっそりと咲く小さなピンクの花が、たまらなく愛おしいと感じてしまうのです。 断言しておきましょう。これが「女のエクリチュール」というものです。ヨーロッパ近代小説が、うんざりするほど女性を花に譬えてきたことはご存じのとおり。あでやかな大輪の薔薇? 乙女の純潔を思わせる白百合? 野辺に人知れず咲く可憐な菫? いずれも単純そのもの。男の所有欲と権力欲の陰画としての象徴的形象であることは、否定しようがないはずです。くり返すなら、そうした文脈において革命的といえるコレットの世界において、強い芳香をもつアカシアとゼラニウムが匂いたつのです。男の攻撃的な性に艶然(えんぜん)と対峙して。男に捨てられて泣く女にはならぬという独立宣言さながらに。 ごく最近のこと、ヴァージニア・ウルフの『波』(1931年)のなかでそのゼラニウムに出遭い、見知らぬ土地で親しい友の姿を見かけたように胸がときめきました。それにしても、この手に負えぬ小説をなんと形容したらよいものか。まさしくサイード的な意味での「レイト・スタイル」にちがいない(11・13回参照)。芸術家の生涯をかけた営みの総集編であると同時に、その解体と破壊でもあるような、不穏にしてラディカルな試みであり、作家の野心という意味で、大江健三郎の『晩年様式集』(2013年)に匹敵するといえましょう。 最も難解な代表作の一つとみなされる『波』についての然るべき解説は、邦訳の著作集(*3) はもとより、ウィキペディアなどでも読むことができますから省略。ネット上で見つけた論文(*4) によれば、この時期、ウルフは人生を「銀色の球」のようなものとして思い浮かべていたらしい。来る日も来る日もその「球体」の感触を味わいながら、プルーストを読もうと思う、行きつ戻りつして読もう、と日記に書いている。『失われた時を求めて』の最終巻が刊行されたのは1927年であり、ついに完結したプルーストという「球体」が、『波』を執筆するウルフにとって目前の参照点であったことは頷けます。具体的な技法やアイデアを借りるというだけでなく、プルーストの「私」による語りの豊かさを日々の滋養にしつつ――プルーストがフローベールの半過去や自由間接話法を滋養にしたように――ヴァージニア・ウルフならではの〈小説〉を産みだすために、未知の可能性に挑んでいたにちがいない。 ウルフはこれを「自伝」とも呼んでいたようです。男女それぞれ3名の登場人物の「意識の流れ」を順繰りに文字化しただけという建前の、なんとも不思議な〈小説〉です。夜明けから日没まで、海と天空の変容を描いた散文詩のようなイタリックの断章が、全部で9篇、幕間の音楽のように挿入されており、子供が老人になるまでの時の流れを暗示する。幕開けは学齢期の少年少女たち。ここで『波』のプルースト的な側面と言えそうな特徴を一つ――『失われた時を求めて』の第1巻「コンブレー」はメルヘンの空間でもあって、教会の古い石畳が蜜のように溶けてしまったり、陽射しの降り注ぐ教会の尖塔が香ばしいブリオッシュに見えてしまったり。言葉の力が風景の変容をもたらし、モノを現前せしめ、世界を創造することを、おとぎ話を読む子供たちは本能的に信じている。「コンブレー」の少年時代が最も華やかなメタファーの舞台となるのは偶然ではないはずです。比較の一例としてジェイムズ・ジョイスの『若き芸術家の肖像』(2016年)を参照するなら、幕開けに童話や子供の作文のパスティーシュ(文体模写)はあるけれど、魔法の世界が広がっているわけではありません。 そうしたわけで『波』はジョイスではなくプルーストの方を向いて書かれている。したがって幕開けで、少女が少年にキスをする素晴らしい場面は、リアリズム小説のロジックでは読み解けないとわたしは考えます。 ルイスは仲間に見つからぬように緑の繁みに潜み、そこで完全に「変身」して一本の木になっている。要約するならこんな具合。 ルイスは言った(登場人物の「意識の流れ」、あるいは「内的独白」の「声にならぬ内心の声」を機械的に導入するのは「考える」ではなく「言う」say という動詞)――濃い緑の海原で花々が魚のように泳いでいる。ぼくは茎を握る。ぼくは茎だ。根は深く、乾いた土や湿った土、鉛や銀の鉱脈を突きぬけて世界の奥底までのびている(ルイスがくり返し言及することになる文明の記憶、ナイル河の風景が挿入される)。 こ のあと、ルイスは葉陰からジニイの姿を見かけ、ジニイが自分の首筋にキスをしたことに気づき、全てが粉々に砕け散った、とつぶやく(改行してジニイへ)。 ジニイは言った――緑の繁みが揺れていた。飛び込んでみたら、ルイス、あなたが緑の灌木みたいに突っ立っていた。目を見据えて。死んじゃったの? と思って、それで、あなたにキスしたの、胸をドキドキさせながら。(解釈が分かれるつぎの文章は原文のみということで)Now I smell geraniums; I smell earth mould. あたしは踊る、さざ波のように揺れる、光の網のようになって、(緑の木である)あなたに覆いかぶさるの(おそらくここでジニイの「変身」が成就して、ただちに改行。二人のキスを見て嫉妬するスーザンの内心の声が導入される)。 おわかりのようにNow I smell geraniums; I smell earth mould. というところで、わたしははっと立ち止まったわけなのです。時間の流れとしてはずっとのち、社交界の女になったジニイが、似合いの相手と野辺を彷徨うことを夢想する場面があって、そこにI smell roses; I smell violets. という文章が記されている。これら二つの場面でジニイは同じように世界にかかわっているのかどうか。つまり、散歩者が見かけるバラやスミレとは異なって、ゼラニウムの場面では「匂い」を嗅ぐ日常的な主体、外界の事象を「感覚」として受容する自覚的で経験論的な主体は、すでに溶解しているのではないか――そうわたしは考えました。考えあぐねて、伝手(つて)をたどり、ヴァージニア・ウルフ協会にも所属しておられる研究者のご意見をうかがうことができました。詳細は省きますけれど、確認できたのは、この不思議なキス・シーンについて、よく知られた議論や定まった解釈は存在しないらしいこと。わたしの示唆した上記の解釈も不可能ではなかろうとのコメントをいただいたので、以下、その方向で話をつづけます。 「あなたにキスをした」と過去形で記した瞬間に、ジニイ自身の「変身」のプロセスが始まるという解釈です。問題のNow I smell geraniums; I smell earth mould. という文章は、「ほら、あたしの体はゼラニウムの匂いがする、土くれの匂いがするの」という意味にも読みとれるのではないか。なぜなら花の咲く繁みにもぐりこみ、緑の木に変身し、地球の奥深く根を生やしてしまった少年の体に、ジニイは接触したからです。リアリズム小説のロジックによれば、いや、そんな非現実的な話ではない、キスをしたあと、ジニイは辺りに漂うゼラニウムの匂い、土の匂いに主体的に気がついた、ここで外界を客体として捉え、それから踊ったのだ、小説は現実の出来事の報告なのだから、ということになるのでしょう。 それにしてもsmellという動詞には「匂いを嗅ぐ」と「匂いを放つ」という両義的な機能があって、日本語の「匂う」という言葉にも同様のあいまいさがありますが、この先は「匂いの現象学」の問題、より正確には「匂いと意識の関係」をめぐるウルフの考究という話題になるでしょう。この小説には、smellという語彙が、食べ物の匂いからリノリウムの匂いまで、執拗なほどの頻度であらわれる。ちなみに花の象徴という意味でも6人の共同体はカーネーション、全員の憧憬の的で内面の言葉をもたず早死にする7番目の人物パーシファルは百合に擬えられている。何かある、と思わざるを得ないのです。 くり返すなら、わたしの考えによれば、身体的に接触した「ゼラニウムの匂い」が引き金となり、少女の意識のなかで、一気に世界の変容が加速し、深まってゆく(Now というところから現在形に移行する)。緑の木のような少年に、光の網のように身を投げかけるというのです。その頂点はI lie quivering flung over you. ていねいに単語を拾ってゆけば「あたしは震えて横たわり、あなたのうえに覆いかぶさっている」――たしかに、そう書いてあるのではないですか? これが性的なイメージでなくて何でありましょう! でも露骨さや暴力性は微塵もない。まさに「女のエクリチュール」ならではの「エロス」というものです。あまりに見事すぎて、思わずたじたじとなり、でもねえ、ウルフさま、子供にそんなこと言わせていいの? とお訊ねしたいほど‥‥‥。 『波』の幕開け、ウルフの新しい〈小説〉が朝日のごとく、世界の創造さながらに、虚空に立ち現われようとしているのです。こうした「決定的な細部」の一つ一つにじっと目を凝らしたい。ウルフがコレットやプルーストの「ゼラニウムの匂い」に気がついていたという可能性もあるでしょう。じつは『ボヴァリー夫人』にもあるのです。新婚のエンマが寝室の窓辺から往診に出かけるシャルルを見送るところ。しどけない部屋着のままゼラニウムの二つの鉢のあいだに肘をつき、話しながら花びらや葉っぱを口でむしりとっては夫のほうにふっと吹きかける。すると花びらや葉っぱがひらひらと舞い降りて、老いた白馬のたてがみにひっかかる。美しい場面なのですが、それにしても、なぜ田舎家の窓辺にありそうなスイカズラとか、平凡なつるバラなどではないのだろう。そう疑問に思ったのは、いつ頃のことだったか。もう文学少女という歳ではなかったけれど、なにしろ根がきまじめなほうだから、エンマの真似をして、ゼラニウムを口でむしりとってみた。そしてほぼ無臭の花びらはともかく、こんな青臭くていがらっぽい葉っぱに唇でふれるのは、わたしには無理と確信したのです。 同じゼラニウムと言ってもフローベールは19世紀の半ば、同世代であるプルースト、コレット、ウルフは20世紀前半のゼラニウムであり、品種も匂いも、相当に違うだろうと思います。それでもわたしはこう宣言しておきたい――20世紀後半を生きた戦後世代のわたしは、あの「微かに淫靡な匂い」を知らないわけではありません。 *1 工藤庸子・蓮實重彦『〈淫靡さ〉について』羽鳥書店、2017年。 *2 géranium- rosatの学名はPelargonium graveolens、和名は「ニオイテンジクアオイ」、通称「ローズゼラニウム」。ただし植物学的な定義によれば、貴重なアロマオイルを抽出する品種は南アフリカ原産の繊細な植物で、ヨーロッパの風土には馴染まず、19世紀末からレユニオン島など海外植民地の農場で栽培されるようになったとのこと。近代小説に登場する鉢植えや野辺の「ゼラニウム」は、別系統の似た植物や改良種などの総称であると思われます。花はピンクが一般的。植物学ではrosatは色ではなく「バラの匂い」と解釈するようです。 *3 ヴァージニア・ウルフ『波』川本静子訳、みすず書房「ヴァージニア・ウルフ著作集5」1976年。 *4 向井千代子「ヴァージニア・ウルフの小説における'Globe'のイメージについて」白鴎女子短大論集、1976年。同「V・ウルフの『波』について」白鴎女子短大論集、1975年。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author工藤庸子 Archives
12月 2018
|
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.