|
2017年8月、東京大学教授でドイツ近現代史がご専門の石田勇治さんと共著で『ナチスの「手口」と緊急事態条項』という新書を集英社から刊行した。ワイマール憲法に組み込まれた緊急事態条項を頻繁に行使する政治運営が、結局は、ワイマール共和国自体の崩壊を招いた過程と要因を主として検討する本である。 本を作る過程での石田さんとの議論も大いに勉強になったのだが(歴史家との議論は本当に勉強になる)、その後も勉強は続いている。というのも、集英社で編集を担当された方が、この本のプロモーションのために著者二人のトーク・イベントなるものを企画し、何度かワイマール憲法や緊急事態条項一般について、改めて討議する機会を作って下さったからである。 2018年1月には、早稲田大学でこのトーク・イベントが開催されたが、そこでの石田さんとのやりとりが、ある事件について考え直すきっかけを与えてくれた。その事件とは、プロイセン憲法争議である。この連載の第5回でも触れたことだが、プロイセンの宰相ビスマルクは1866年、オーストリアとの戦争に勝利した後、1862年以降、予算なしに歳出を続けた政府の行動についての免責法案を提出し、議会で可決・成立させている。憲法の明文に忠実に従ったままでは国難を解決し得ない場合は、必要な措置はとり、しかし事後的に議会で事情を釈明して許しを請うた例として知られている。 どんなことが起こるか分からないのだから、どんな大変なことが起こっても対処できるようにと緊急事態条項を拵えると、とてつもなく危ない権限を政府に与えることになる。便利だからといって、困ったときにそれに頼りきりになると、ワイマール共和国のように、議会の諸勢力が協調して国難に対処する気を無くし、何でも反対派の寄せ集めになってすべてを御破算にしようとして、政治という活動全体が国民の信頼を失うことになる。むしろ、そんな便利な条項を作ろうとするのはやめて、しかし国民の生命・財産を守るために必要な最低限の措置はたとえ違法であっても、政府はとる。ただ、とった後では事後的に政府は議会でなぜ法に反する措置をとったか説明し、許しと免責を請うべきである。その場合、政府は国民の生命・財産の危機を救うために、本当に必要最小限ギリギリのことだけをしようとするはずである。ということで、その事例の一つが、プロイセン憲法争議だというのが筆者の主張である。 この事例を早稲田のトーク・イベントで紹介したところ、石田さんから疑義が提示された。この事案は長い目で見ると、プロイセン、さらにはドイツ第二帝国で民選議会の地位が低下し、政府優位の状況で統治が行なわれるきっかけとなったもので、必ずしもビスマルクが議会の意思に従った事例とは言えないのではないか(単純粗雑なまとめで申し訳ありません)という疑義である。 この疑義には、たしかにもっともなところがある。その点を以下、説明したい。 1860年代初頭、国際情勢の緊迫化に対応すべく、徴兵期間を2年から3年に延長するとともに、各地の民兵を改組して常備軍に組み込む形で軍備を拡張しようとしたプロイセン国王ヴィルヘルムⅠ世は、リベラル派が多数を占める議会下院の抵抗に直面する。民兵組織はリベラル勢力の力の源泉でもあった。1862年に両者の対立は激化し、下院は政府の提出した予算案を組み換えた独自の予算案を可決する。国王は対抗して下院を解散するが、総選挙で選ばれた新たな下院ではリベラル派の議席はさらに増加した。プロイセン憲法によれば、予算は上下両院で可決されない限り成立しない。下院多数派は、憲法が定める通りの統治を要求する。政府が譲歩すべきだというわけである。一時は退位も考えたヴィルヘルムはしかし譲らず、新たにビスマルクを宰相の地位に据えた。1862年9月のことである。
ビスマルクが議会で行なった演説のことば、「現下の主要問題は、弁舌と多数決ではなく、鉄と血によって解決される」は広く知られている。プロイセンは、ベルギーでもイギリスでもない。議会多数派の支持がなければ国政を遂行し得ない国家ではない。ビスマルクは、下院の同意を必要とすることなく、つまり予算が成立しなくとも、国家の生存を維持するために政府は租税を徴収し、支出をすることができると主張した。それを支えるために用意されたのが、「憲法典の欠缺」という議論である。 プロイセン憲法によれば、予算は、国王を代表する政府の提出した予算案を上下両院が可決することで成立する。成立しない場合はどうなるのだろうか。憲法典はそうした事態を想定していない。憲法典だけを頼りにしたのでは、この事態は解決できないことになる。憲法典が頼りにならない以上、憲法学によっては解決できないというのが、一つの回答(?)である。ゲアハルト・アンシュッツの「ここにあるのは、憲法典の欠缺というよりは、いかなる概念操作によっても埋めることのできない法の欠缺である。ここに憲法は止まる(Das Staatsrecht hört hier auf)」という述懐は(Gerhard Anschutz, Georg Meyer, Lehrbuch des deutschen Staatrechts, 7th ed. (Duncker & Humblot, 1919), p. 906)、こうした態度を示している。それは法律問題ではない。後は政治の問題だというわけである。 しかし、憲法典に穴があるとしても、憲法に穴があるとは限らない。法に基づいて条文ができるのであってその逆ではない(non ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat)、という回答もあり得る。プロイセン憲法は、先行するバイエルンやビュルテンベルクの憲法、さらには後に続く大日本帝国憲法と同じく、君主制原理(monarchisches Prinzip)に基づいている。国の統治権は元来、君主がすべてを掌握しているが、統治権を実際に行使するにあたっては、君主自身が定めた欽定憲法の条項に従って、これを行使するという考え方である。「天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ」とする大日本帝国憲法第4条に、この考え方が典型的に示されている(この辺りの消息については、本連載第8回参照)。 したがって、憲法典が想定していない事態が発生したとき、どうすべきかを判断し、決定する権限は、元来すべての統治権を掌握している君主に属するはずである。憲法典を読んだだけでは帰属の判明しない権限は、君主に帰属するという推定(praesumptio pro rege)が働くからである(cf. Carl Friedrich von Gerber, Grundzüge des deutschen Staatsrechts, 3rd ed. (Bernhard Tauchnitz, 1880), p. 133)。ちなみに、日本国憲法についても、その41条で最高機関とされる国会に関して、帰属不明の権限が帰属するとの推定が働くという議論があるが、現憲法下の国会が元来、全統治権の掌握者ではない以上、この議論の説得力は極めて薄弱である。 プロイセン憲法についても、憲法典がそもそも想定していない緊急事態が生じたときは、元来の統治権の掌握者である君主がこの事態を解決する権限を持つはずだ、というのが、君主制原理と憲法典の欠缺とを掛け合わせると、自然に導かれる結論である。ビスマルクが依拠したのは、こうした論理の筋道であった。 さて、議会の正式の承認なしに歳入・歳出を行ない、軍備を増強したプロイセンは、参謀総長であったモルトケの作戦──機動性の高い部隊からなる膨大な兵力で敵軍を組織的に包囲殲滅する作戦で、この作戦を遂行するためには、徴兵の長期化と兵力の増強が必須であった──が功を奏して、対デンマーク戦争(1864年)に続いて対オーストリア戦争にも勝利する。オーストリアに対する戦勝を決定づけたケーニヒグレーツの戦いと同じ日(1866年7月3日)に行なわれた下院選挙で、リベラル派は惨敗する。 それまでビスマルクを支持してきた保守派は、一気に畳みかけて憲法を改正し、議会の権限を縮小して政府の権限を強化すべきだと主張した。しかし、新たに召集された議会でビスマルクが採ったのは、政府の免責法案を提出するという方策である。予算不成立のままなされた1862年から66年までの歳出について、下院は大臣が弁償すべきだとの態度をとっていた。免責法案は、事後的に政府の歳出を合法化し、大臣の責任を免除するものである。リベラル派の主流はこの提案を受け入れ、免責法案を可決した。 あくまで君主制原理にこだわるのであれば、議会による免責は不要のはずである(ヴィルヘルムはそう主張した)。しかしビスマルクとしても、今後のプロイセン、さらには統一ドイツの国政を執るにあたって、議会の主要勢力であり中産階級に支持されるリベラル派と対峙しつつ、憲法上の対立が解けない異常事態が継続することは避けたかった。彼をこれまで支えてきた大土地保有者を基盤とする保守派は、今後は衰退していく勢力である。また、リベラル派としても、ビスマルクが実際に執ってきた政策、オーストリアを除外したドイツの統一と産業の振興は、自分たちの年来の主張に沿うものである。 この結果、リベラル派は免責法案に賛成する勢力と反対する勢力とに分裂した。免責法案に賛成したリベラル右派勢力は、その後、ビスマルクを確固として支持する勢力となった。形の上では、ビスマルクは非を認め、議会の免責を求めているが、その結果、実際に生じたのは、ビスマルクの望むような議会の勢力配置が構成されたことであった。石田さんの指摘はあたっているというのは、この点である。 ただし、君主制原理はプロイセンおよび統一ドイツの国制を支える基本原理として、生き続ける。君主制原理に基づくドイツ型立憲制と、議会に依拠して統治を行うイギリス=ベルギー型立憲制との対立は、約50年後に第一次世界大戦として爆発することになる。日本の憲法典の文面から君主制原理が排除されるには、第二次世界大戦を要した。 プロイセン憲法争議ほどの事件になると、政治・経済・軍事・国際情勢が複雑に絡み合い、それにさまざまな憲法学説が戦闘手段として動員される。一つの正しい見方だけがあるわけではない。異なる分野の方々と討議する楽しみの一つは、そのことに気付かされることである。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.
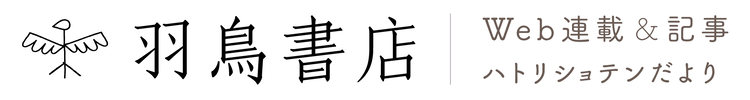

 RSSフィード
RSSフィード