|
モーシェ・ハルバータルとスティーヴン・ホームズの共著『政治のはじまり』(Moshe Halbertal and Stephen Holmes, The Beginning of Politics: Power in the Biblical Book of Samuel (Princeton University Press, 2017))は、第2章で『サムエル記』が伝えるノブの大虐殺を分析する。
イスラエルの王サウルは、自身の女婿であり側近の武将でもあったダビデが王位をうかがおうとしているのではと疑い、その命を奪おうとする。ダビデはサウルの息子ヨナタンとサウルの娘ミカルの助けで危うく難を逃れ、ノブに住むヤハウェの祭司アヒメレクを訪ねる。供も連れずただ一人であらわれたダビデをアヒメレクは不安げに迎え、なぜ一人なのかと問う。ダビデは、王サウルの密命を帯びて急遽出立したと嘘をつく。供とはこれから落ち合うところだが、何か食糧はないか、武器はないかと訊ねる。お供えものの聖別されたパンはある、ダビデがかつて討ち倒したペリシテ人ゴリアテの帯びていた剣ならあるとアヒメレクは答える。ダビデはお供えのパンとゴリアテの剣を得て、逃亡の旅を続ける(I 19: 1 – 21: 10)。 他方、被害妄想にとりつかれた王サウルは側近の臣下に、なぜおまえたちは共謀して自分に背くのか、なぜヨナタンとダビデが契約を結んだことを誰も自分に告げないのか、と当たり散らす。しかしサウルは、そもそもイスエラルの王になりたくてなったわけではない。サムエルが民をミツパに集め、くじによってまず部族を、そして氏族を選び、最後にサウルを王として選んだとき、サウルは荷物のかげに隠れていた(I 10: 22)。 しかし、イスラエルの民をペリシテ人をはじめとする周辺の敵対者から守るため、民に望まれ、心ならずも王に選ばれたサウルは、次第に王の地位に恋々としはじめる。ダビデが巨人ゴリアテを討ち倒して戦いを勝利に導いたのち、人々が「サウルは千を討ち、ダビデは万を討った」と喜び歌うのを聞いて、サウルは怒りに燃え、「ダビデには万を当て、私には千を当てる。彼に与えるとすれば、あとは王国だけだ」と言い放つ(I 18: 6-8)。民の幸福と安全を保障する手段であるはずの王位が、被害妄想と猜疑心にさいなまれたサウルにとっては自己目的化し、人民や臣下はもちろん自身の息子や娘にいたるまで、手段としてはならないものまでが、王位を保つための手段と化す。権力は私物化され、権力者はその虜となる。 側近の部下に対してまで、自分の地位をダビデに渡すために共謀しているのかと尋ねるサウルに情報をもたらしたのは、エドム人、つまり異邦人のドエグであった。彼は、祭司アヒメレクがダビデに食糧を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣をも与えたと告げる。アヒメレクはダビデに騙されてそうしたのだが、ドエグはあたかもアヒメレクがダビデと共謀しているかのように語る。これでサウルの猜疑心は、側近の臣下から、ノブの祭司アヒメレクへと向かった。 サウルは、アヒメレクだけでなく、彼の一族すべてを呼び出し、なぜダビデと共謀して自分に背いたかとアヒメレクを詰問する。 アヒメレクは、ダビデに騙されたと答えることもできたはずである。しかし彼は、ダビデがサウルの臣下の中でも最も忠実で一族の中で最も尊敬されている人物であることを指摘する。サウルとダビデとが反目していることについて、彼が一切何も知らなかったのも当然である。ダビデに対して強い猜疑心を抱き命を狙うサウルを暗に批判する応答である。 サウルは激怒し、アヒメレクだけでなく、彼の一族すべては死ななければならないと言い、護衛の者たちにダビデと手を握るヤハウェの祭司どもを殺せと命ずる。しかし、臣下たちは祭司に手を出そうとしない(I 22: 17)。 ハルバータルとホームズは、ここに権力のある普遍的な特質があらわれていると言う(Halbertal and Holmes, op. cit., p. 75)。あらゆる統治者と同じく、サウルも臣下の協力を必要とする。王がその命令を執行させるには、現場で武力をふるう執行者にとって、王の命令が正当性を帯びるものでなければならない。直接に実力を行使する部下が一致して協力を拒むとき、王の命令はもはや命令として機能しない。アヒメレクは同じイスラエル一族の司祭であり、神に仕える者である。また、たとえアヒメレクがダビデと共謀していたとしても、彼の一族がすべて殺されねばならないのであろうか。 部下の抵抗に直面したサウルは、ドエグに、おまえが祭司どもを討てと命令する(I 22: 18)。ドエグは異邦人である。アヒメレクもその一族も、ドエグにとって同胞ではない。支配する人民の信頼を失った統治者にとって頼りとなるのは、異邦人の傭兵である。ドエグは祭司85人を殺し、さらに祭司の町ノブを襲って、男女を問わず、子どもや乳飲み子にいたるまでを刃にかけた。家畜も同様に皆殺しである。同胞であることを信頼の証となし得ないドエグにとって、王のおぞましい命令を忠実に執行することこそが、自身の身を守ることになる。臣下の信頼を失った王と同胞を頼りとなし得ない異邦人の傭兵とは、大虐殺において密接な共犯関係に立つ。その結果、王と傭兵とはさらに自分たちを孤立させることになるのだが。 アヒメレクの息子エブヤタルだけが難を逃れ、ダビデのもとに走り、サウルによる祭司たちの虐殺について知らせた。ダビデのことばは奇妙に冷静である。私があなたの父の家の者全員を死なせてしまった、私の命を狙う者は、あなたの命をも狙う、私と一緒にいれば、あなたは安全だと、ダビデはエブヤタルに言う(I 22: 22-23)。 H.L.A. ハートは、フレデリック・メイトランドの法人観について、「なぜ彼がリアリストと呼ばれるのか、なぜ彼が解説したギールケの教説を承認したと考えられているか、理解できない」と述べる。ハートによれば、メイトランドは、法人が「擬制であるとか、多数人の集合の呼び名だとする理論は『事実を歪めるdenatured the facts』ものと確信していたが、法人が実在するか否かについて、最終的な結論は留保している(H.L.A. Hart, ‘Definition and Theory in Jurisprudence’, in his Essays in Jurisprudence and Philosophy (Clarendon Press, 1983), p. 37)。ハートがわざわざこのように述べるのは、メイトランドをギールケ流の法人実在論者だとする学者が少なくないからである(cf. J.A. Mack, ‘Group Personality—A Footnote to Maitland’, Philosophical Quarterly, Vol. 2, No. 8 (1952), p.249)。
メイトランドは、ギールケのドイツ団体法論(Das deutsche Genossenschaftsrecht)の第3巻からDie publicistischen Lehre des Mittelalters の章を翻訳し、著名な訳者解説を付して刊行している(Otto Gierke, Political Theories of the Middle Ages, trans. Frederick William Maitland (Cambridge University Press, 1900))。メイトランドがギールケの団体・法人論に好意を寄せていたことは確実である。しかし、メイトランドは自説を声高に主張する学者ではない。史料が裏付ける事実、他の学者が説く内容等を、判明する限りで控え目に述べる学者である。ギールケと同様に、法人にそれ自身の意思や精神があるとメイトランドが信じていたことを確証する、彼自身の言明は存在しない。むしろ彼は、彼の法人論の到達点を示したと言われる論稿において、「哲学は私と関係がないno affairs of mine」と予防線を張る(’Moral Personality and Legal Personality’, in F.W. Maitland, State, Trust and Corporation, eds. David Runciman and Magnus Ryan (Cambridge University Press, 2003), p. 71)。 Moral Personality and Legal Personality で彼が述べているのは、法的な理論や観念は、長期的には、社会通念 (moral sense or moral sentiment of the people) と合致している必要があり、したがって、法人は単なる擬制に過ぎないとか、国家が法人格を特許することではじめて法人は誕生するし、国家は自由にそれを撤回することもできる等といった典型的な法人擬制説の立場は、維持できないということである。以下、この論文の内容を見て行こう。 法人をめぐる理論の変化を見るとき、イギリスの歴史は参考にすべきではないとメイトランドは言う。イギリス人は、出発点とするには、あまりにも論理的でなさすぎる。出発点としてふさわしいのは、フランスである(p. 66)。王制下のフランスは、個人と国家の間に割り込む媒介物を粉砕し、無に帰そうとしてきた。絶対国家と絶対個人を対峙させるこうした企図は、革命へと受け継がれる。結社の自由が認められるには、20世紀初め(1901)を待たねばならなかった。 フランスを含めたヨーロッパ各国は、19世紀の経験を通じて、以下のような結論へと到達した、とメイトランドは言う。(1)人々が永続的な団体を組織することが適法である限り、そうした団体は、権利義務を担う主体である、(2)団体の人格は純粋に法的な現象ではなく、国家が強制的に団体を解体するのであればともかく、その存続を許容している限り、国家は団体が人格を担うことを認めざるを得ない、(3)社会通念上は、団体は人(person)である(p. 68)。 メイトランドによれば団体は人であり、n人の構成員が団体を組織すれば、そこにはn+1人が存在する。もちろん、生身の個人と全く同じ意味で人であるわけではない。法人が婚姻することはないし、嫡出子として出生することもない(p. 63)。それでも団体は実在する。唯心論者にとっても街灯(lamp-post)が実在するのと同じ程度には(p. 69)。街灯を物理的に解体することはできる。しかし、街灯として機能している以上、街灯は街灯として実在する。黙りこくってはいるが。 以上のようなメイトランドの行論からすれば、彼が法人(団体)の実在性について結論を留保しているというハートの言明は、控え目に言っても不正確である。メイトランドは、典型的な法人擬制説は誤りであるとし、団体は人格を担い(人であり)、それは実在する(real)と明確に述べている。ギールケと同じように、団体自体に意思や精神が備わっているとは、彼は明確に述べてはいない。しかし、アイロニーに富み、極度に控え目な文章表現に巧みなメイトランドに、ことばの表面上の意味のみを帰すことには、逆のリスクがある。アーネスト・バーカーやデイヴィッド・ランシマンのように、メイトランドをギールケと同じ意味における法人実在論者として扱うことが、公正でないとまで言い切ることは難しいであろう。 ところで、ハートの意図は必ずしもメイトランドの立場を擁護することにあったわけではない。彼は、メイトランドのことをin his greatnessとか言って持ち上げておきながら(op. cit., p. 37)、実際にはメイトランドを法人実在論者として扱い、その議論を反駁しようとしている(イギリス人は、全くもって食えない)。 ハートが取り上げるのは、メイトランドがMoral Personality and Legal Personalityの中で描くNusquamiaという仮想の国家の物語である。メイトランドは次のように言う。 前回は多数決による社会の決定は、適切にして十分な理由に支えられていなければならないはずだという話をした。今回は、この世の中は集合的決定に関する限り、そう簡単にはできていないという話である。
個人であっても、適切にして十分な理由によって支えられる選択肢があるにもかかわらず、それと異なる不合理な選択をすることはないわけではない。しかし、それは不合理な選択である。他方、集団の場合、理由に関するメンバーの判断を集計した結果とメンバーの結論の集計結果とが整合しないことがある。それは必ずしもメンバーによる不合理な判断や不合理な選択の結果ではない。 集合的決定の結論が、それを支えているはずの理由付けの集計結果と不整合を起こす問題状況は、それを最初に定式化したフランスの数学者、シメオン-ドゥニ・ポワッソンの名前をとって、ポワッソンのパラドックスと呼ばれる。最近では、法理のパラドックス(doctrinal paradox)と呼ばれることもある。 早稲田大学中央図書館4階にある古書資料庫に収められたポワッソンの著作は、次のような陪審裁判の事例を伝える(Simeon-Deny Poisson, Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile (Bachelier, 1837), p. 21 note)。 ピエールとポール、2人の被告人がある同一の窃盗事件で起訴された。12人の陪審員の結論は3つのグループに分かれた。ピエールについて、最初の4人は有罪、次の3人も有罪、残りの5人は無罪と判断した。ポールについて、最初の4人は有罪、次の3人は無罪、残りの5人は有罪と判断した。ピエールは7対5で有罪、ポールも9対3で有罪である。次に、2人は共犯かどうかが判断された。共犯であれば刑が加重される。2人がともに窃盗に関与したと考える陪審員は4人だけである。したがって、共犯ではない。2人とも有罪なのに。 理由に関する2つの判断からは、2人は共犯であるという結論が導かれるはずだが、結論について多数決をとると共犯ではないとの結論が出る。理由と結論とが不整合を起こす。 法理のパラドックスとも呼ばれるのは、次のような設例によって説明されることがしばしばあるからである。1人の被告人について、3人の裁判官が、次のような判断を下したとしよう。 犯罪を実行したか? 違法性は阻却されるか? 有罪か? 裁判官A Yes No Yes 裁判官B Yes Yes No 裁判官C No No No ジャン-ジャック・ルソーは、一般意思と特殊意思を区別した。一般意思は社会全体の利益の実現を目指し、特殊意思は個人の(あるいは身の回りの人々の)利益の実現を目指す。個人の一般意思を多数決手続を通じて集計すると社会としての一般意思が得られる。特殊意思を集計しても、個別的な欲求の集積である全体意思が得られるだけで、一般意思にはならない。
政治思想史家のパトリック・ライリーによると、一般意思と特殊意思という区別は、神学上の論争に由来する。神は人類すべての救済を目指したのか、それとも個人ごとに救済するか否かを決めたのかが争われた。その区別が政治哲学に輸入され、ルソーによって概念の改鋳が施された(Patrick Riley, The General Will Before Rousseau: The Transformation of the Divine Into the Civic (Princeton University Press, 1986))。 神には意思とは別の理由(あるいは理由に対応して判断する理性)があるのだろうか。神の理性は人の理性と同じだろうか。分からない。神のことであるから。 人には意思と理性とがある。理由に対応して判断する能力が理性である。人の行動を方向づける理由、なぜそう行動したのか、それを理解可能なものとして説明することができる理由は実践的理由である。もっとも、人が行動するとき、いつもその理由は何かを意識するわけではない。本人が把握している限りの具体の状況において適切な行動が何か、何が適切でないか、意識することも熟慮することもなく直感的に行動することがむしろ殆どであろう。しかし、説明を求められれば、説明することはできる。その場で妥当するすべての理由をくまなく数え上げることは困難ではあるが。 理由にはいくつかの種類がある(この部分の説明は、ジョゼフ・ラズに依拠している。Cf. Joseph Raz, Engaging Reason: On the Theory of Value and Action (Oxford University Press, 1999))。ある選択を合理的なものとして理解可能(つまり説明可能)とする事情があれば、それは「十分な理由sufficient reason」である。 ある時点で人が直面する、十分な理由によって支えられた選択肢は、複数あることが通常である。それらの選択肢を支える十分な理由のうち、他の理由によって打ち消されない理由は「適切な理由adequate reason」である。適切な理由が一つだけであれば、判断には困らない。しかし、複数の適切な理由に直面することも少なくない。それらの理由は、比較不能である。 たとえば、近所に評判のフレンチ・レストランがあるとする。そこでは、おいしい料理が食べられるであろう。今夕はほかに用はないし、外食をする金銭的な余裕くらいはある。しかも近所にある。しかし、時間の空いている今夕は、近くの映画館で評判の映画を鑑賞するという選択肢もある。映像が美しく、プロットも巧みで役者の演技も上々であると言われている。もちろん、映画のチケットを購入する程度の金銭的余裕はある。二つの選択肢を支える理由は、いずれかがいずれかを打ち消すという関係にはなく、また、二つの緊要性が全く同じというわけでもない。そうしたとき、二つは比較不能である。比較不能性は世の中に満ち溢れている。 比較不能な理由によって支えられる複数の選択肢に直面したとき、そのいずれを選んだとしても、その選択は合理的である。どの選択肢も、他の理由によって打ち消されない十分な理由によって支えられているのだから。 適切な理由によって支えられる選択肢が一つだけ(つまり「結論を決定する理由conclusive reason」によって支えられる選択肢が存在する)という稀な事態においても、その選択肢を選ぶことに必ずなるわけではない。適切な理由によって支えられる選択肢が一つだけあるというのは、理性の判断である。それは人の意思や感情を拘束するわけではない。理性的に考えればすべきことは一つだという場合でも、そうしたくないということはあるし、結局そうはしないということもあるだろう。 比較不能な理由によって支えられる複数の選択肢に直面したとき、そのいずれを選ぶかを決めるのは意思である。意思は、ときに非合理的な決定をすることもある。適切な理由によって支えられる選択肢が一つだけであるにもかかわらず、それに反する行動をとる決定をすることさえある。人とはそうしたものである。自分がどういう人間かは、そうした選択を通じて徐々に形成される。そうした選択を通じて、人は自分が何者であるかを決めていく。人は自分の人格を部分的には自ら作る。 普遍性を標榜するありがたそうな道徳原理や定言命法は、生きる上での重大な岐路や困難な道徳的選択の場面ではほとんど役に立たない。そうしたものにこだわっていると、むしろ自分が構築してきた人格や無意識のうちに正しい選択を選び取る能力を損なうことになりかねない。 憲法についてほかの人と話が通じにくいなと感じるとき、そもそも憲法や法に関するものの考え方が、さらに言えば人や社会に関する見方が、根本から異なっているからではないかと思うことがある。ウィトゲンシュタインが指摘するように、「たとえライオンが人語を話すことができたとしても、われわれは彼の言うことが理解できない。」われわれは、生肉を食らいつつ咆哮する生き物として世界を意味づけることはできない。
実定法や憲法の条文にしろ、有権的(authoritative)とされる各種の解釈にしろ、いずれもどう行動すべきかに関する実践的な判断の補助手段であり、道具である。最終的に判断を下すのは、結局は自分自身である。 実定法は権威であると自己主張することがしばしばある。「あなた方、自分で判断するのはやめて、私の言う通りにして下さい。そうした方が、あなた方が本来すべき行動をよりよくとることになりますから」と主張するものである。大多数の人々が、大多数の人々と同じ行動をとろうと考えている調整問題状況では、実定法を権威として受け止め、その通りにすることで、本来すべき行動をとることのできる場合が多いであろう。実定法が、自動車は道路の左側を通るように指示している社会で、左側を通るようにすれば、事故を起こすこともなく、スムーズに、かつ、安全に自動車を運行することができる。 他方、いついかなる場合でも、必ず実定法の文言通りに行動することが、本来とるべき行動をとることになるとは限らないことも、常識的に考えればすぐ分かることである。人の命がかかっているような緊急の場合に、必ず実定法を遵守して行動しなければならないとは限らない。「この状況で人として本来すべきことは何か」を最終的に判断するのは、いつも自分自身である。実定法の条文は、所詮、実践的な判断の補助手段である。物神として条文を崇め、自分の判断を放棄することは、人であることを放棄することである。 イギリスの首相ウィンストン・チャーチルの有名な警句として、「民主主義は最悪の政治体制だと言われてきた。今まで試されたことのある他の政治体制を除けばの話だが」というものがある。
チャーチルがそう語ったのは、1947年11月のことである。その時点で「今まで試されたことのある他の政治体制」として念頭に置かれていたのは、ファシズムか共産主義であった。共産主義と言ってもスターリン体制である。その二つに比べれば、たしかに民主主義はまだましであろう。早朝にドアをノックする者が秘密警察ではなく、牛乳配達夫にすぎない政治体制である。 それからほぼ半世紀を経過した今、今までに試されたことのある政治体制として、新たな種類のものが現れた。中国の現体制である。どう見ても共産主義体制ではない。中国の憲法第1条は、中国が「人民民主独裁の社会主義国家である」と宣言している。独裁国家であることは確かだが、果たして社会主義国家であろうか。 ケンブリッジ大学の政治学者、デイヴィッド・ランシマンの近著『民主主義はいかに終焉するか』(David Runciman, How Democracy Ends (Profile Books, 2018)) は、中国の政治体制を欧米の民主国家との対比で、次のように分析する。 民主主義体制の特徴は、第一にすべての国民を個人として尊重すること、第二に社会全体におよぶ長期的な便益を供与することである。個人としての尊重は、典型的には国政参加権の平等な付与としてあらわれる。社会全体におよぶ長期的な便益は、さまざまな公共財の提供──治安の維持、経済的繁栄、社会的基盤整備、対外的平和等──としてあらわれる。個人として尊重された国民は、こうした公共財を背景としてそれぞれ自由に活動し、その結果を個人として享受する。 民主主義体制、とくに欧米の古くからの民主主義体制は年老いた。若い、エネルギーにあふれた民主国家は、高い経済成長率を誇り、選挙権を拡大していくことで、個人としての尊重についても、社会全体におよぶ長期的な便益の供与についても、目覚ましい結果を誇ることができた。今は違う。選挙権拡大の余地はもはや乏しく、経済成長も大きく期待はできない。社会全体に広く薄く便益がおよぶ公共財は、それが公共財であるだけに、個々の国民にとっては便益を直ちには実感できない。 他方、現在の中国はすべての国民を個人として尊重しようとはしていない。形式的にはすべての国民に参政権はあるのであろう。しかし、それはほとんど意味のない参政権である。モンテスキューが喝破したように、共和政国家でも専制国家でも、国民はみな平等である。前者では国民がすべてであり、後者では国民が無である点で(『法の精神』第6篇第2章)。しかも、チベットやウイグルの人たちの地位は、無以下のマイナスである。それでも、社会全体としては尊重と尊厳が付与されている。ナショナリズムを通じて、国威発揚を通じて、中国人民の威厳は回復されている(と中国政府は主張する)。 しかも、個々の国民は経済発展の便益を感じることができる。民主主義的な現在のインドと権威主義的な現在の中国との違いである。中国政府の方がはるかに効率的である。党組織が腐敗や汚職にまみれているとしても。つまり、中国の現体制は、民主主義体制を逆立ちさせている。民主主義の提供する個人の尊重と社会全体への長期的便益供与の代わりに、社会全体の尊厳と個人への短期的便益供与の組み合わせで、現在の中国の政治体制は成り立っている。 裁判官は法を適用し、ときには解釈する。条文で言うと、条文が具体の事案に対して適切な答を導くときはその条文をそのまま適用する。具体の事案に対して適切な答を導かないときは、条文に解釈を加える。関連する法令や先例に加えて、起草者がどのような場面を想定してその条文をこしらえたか、面前の事案がそうした場面にどの程度対応しているか、制定時と現在とでどのような事情が変わらず、どのような事情が変化したか等を勘案して条文に解釈を加え、事案に即した適切な答を出そうとする。
憲法の条文、とくに基本権に関する条文については、話が変わってくる。基本権条項は、それをそのまま適用して何か具体的な答が出てくるということは、まずない。表現の自由の場合で言うと、日本国憲法21条は、「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定める。しかし、何でもかんでも表現活動のし放題というわけではない。他人の名誉を毀損する表現活動は取り締まられるし、人格権侵害にあたるとして差し止められることもある。届出もしないで道路で集会やデモ行進をしてかまわないというわけでもない。「車両は道路の中央から左の部分を通行しなければならない」と定める道路交通法17条4項や、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない」と定める民法214条とは、相当に趣が違う。道路交通法や民法の場合は、何をすべきか、何をしてはならないか、読んだだけですぐに分かる。憲法21条はそうはいかない。 イスラエルの「人間の尊厳と自由に関する基本法」は、全体として見れば、ごくありきたりの権利宣言である。あらゆる人の生命、身体、尊厳ならびに財産は保障される。人身の自由もイスラエル国籍を離脱する自由も保障される。プライバシーと住居の不可侵も保障される。基本法は、憲法典がそうであるように硬性化はされていない。しかし、イスラエル議会(the Knesset)が、基本法に反して立法する意思を明示しない限り、基本法に反して権利を侵害する法律は無効とされる。
ときおり議論を誘発するのはその第1条である。同条は、イスラエルが「ユダヤ的民主国家 a Jewish and Democratic state」であると規定する。 問題は、ここでいわれている「ユダヤ的国家」とは何を意味するかである。いろいろな回答が考えられる。(1)ユダヤ教がイスラエルの国教として樹立され、国民すべてがユダヤ教を信仰すべきことを意味するのか、(2)ユダヤ教徒あるいはユダヤ教徒でないとしてもユダヤ人であるイスラエル国民が、他の国民より優越した地位を占めること(つまり、イスラエルには一級市民と二級市民がいること)を意味するのか、(3)基本法が規定するありきたりの普遍的な諸価値のほかに特殊ユダヤ的諸価値があり、後者はときに普遍的諸価値と衡量され、特殊ユダヤ的価値のゆえに普遍的価値が切り下げられることもあるということか。 最高裁長官として長くイスラエルの司法界を率いてきたアーロン・バラク判事によると、この「ユダヤ的国家」という概念が意味しているのは、(1)から(3)のいずれでもなく、イスラエルがユダヤ教の基本的諸価値を擁護する国家であることである。その基本的諸価値とは、「人類への愛、生命の神聖性、社会正義、衡平、人間の尊厳の保護、立法府をも対象とする法の支配等」である(Aharon Barak, ‘A Constitutional Revolution: Israel's Basic Laws’ (1993). Yale Law School, Faculty Scholarship Series. Paper 3697)。 要するにまっとうな民主国家であれば、どこであれ尊重される普遍的諸価値を擁護する国家であることを意味していることになる。法哲学者のジョゼフ・ラズが指摘するように(Joseph Raz, ‘Against the Idea of a Jewish State’, in The Jewish Political Tradition, Michael Walzer et al. (eds.) (Yale University Press, 2000), pp. 509-514)、これが「ユダヤ的国家」の意味であれば、現在のフランスも「ユダヤ的国家」であろう。おそらく現在の日本も「ユダヤ的国家」である。世界を見渡したとき、たしかに「ユダヤ的国家」であるかどうか疑わしい国々もあるが、それは要するに、(その国の憲法典に何が書かれているかは別として)普遍的とされる諸価値を実際に尊重しているとは言えない国家だということである。 2017年8月、東京大学教授でドイツ近現代史がご専門の石田勇治さんと共著で『ナチスの「手口」と緊急事態条項』という新書を集英社から刊行した。ワイマール憲法に組み込まれた緊急事態条項を頻繁に行使する政治運営が、結局は、ワイマール共和国自体の崩壊を招いた過程と要因を主として検討する本である。
本を作る過程での石田さんとの議論も大いに勉強になったのだが(歴史家との議論は本当に勉強になる)、その後も勉強は続いている。というのも、集英社で編集を担当された方が、この本のプロモーションのために著者二人のトーク・イベントなるものを企画し、何度かワイマール憲法や緊急事態条項一般について、改めて討議する機会を作って下さったからである。 2018年1月には、早稲田大学でこのトーク・イベントが開催されたが、そこでの石田さんとのやりとりが、ある事件について考え直すきっかけを与えてくれた。その事件とは、プロイセン憲法争議である。この連載の第5回でも触れたことだが、プロイセンの宰相ビスマルクは1866年、オーストリアとの戦争に勝利した後、1862年以降、予算なしに歳出を続けた政府の行動についての免責法案を提出し、議会で可決・成立させている。憲法の明文に忠実に従ったままでは国難を解決し得ない場合は、必要な措置はとり、しかし事後的に議会で事情を釈明して許しを請うた例として知られている。 どんなことが起こるか分からないのだから、どんな大変なことが起こっても対処できるようにと緊急事態条項を拵えると、とてつもなく危ない権限を政府に与えることになる。便利だからといって、困ったときにそれに頼りきりになると、ワイマール共和国のように、議会の諸勢力が協調して国難に対処する気を無くし、何でも反対派の寄せ集めになってすべてを御破算にしようとして、政治という活動全体が国民の信頼を失うことになる。むしろ、そんな便利な条項を作ろうとするのはやめて、しかし国民の生命・財産を守るために必要な最低限の措置はたとえ違法であっても、政府はとる。ただ、とった後では事後的に政府は議会でなぜ法に反する措置をとったか説明し、許しと免責を請うべきである。その場合、政府は国民の生命・財産の危機を救うために、本当に必要最小限ギリギリのことだけをしようとするはずである。ということで、その事例の一つが、プロイセン憲法争議だというのが筆者の主張である。 この事例を早稲田のトーク・イベントで紹介したところ、石田さんから疑義が提示された。この事案は長い目で見ると、プロイセン、さらにはドイツ第二帝国で民選議会の地位が低下し、政府優位の状況で統治が行なわれるきっかけとなったもので、必ずしもビスマルクが議会の意思に従った事例とは言えないのではないか(単純粗雑なまとめで申し訳ありません)という疑義である。 この疑義には、たしかにもっともなところがある。その点を以下、説明したい。 時折、英語で原稿を書くよう頼まれることがある。最近では、ニューヨークに本拠を置くInternational Journal of Constitutional Law という季刊誌に、日本の憲法に関する本の書評を書くように言われ、近年、最高裁を退官された藤田宙靖、泉徳治、千葉勝美の3氏の著作の書評をこしらえて、先方に送ったところである。2018年中には刊行されるであろう。
すでに刊行されたもので近年のものというと、たとえば、Routledge Handbook of Constitutional Law という本が2013年に刊行された。「ハンドブック」とはいうものの、大項目の憲法事典とでもいうべきもので、特徴は、大部分の項目が複数の研究者の共同執筆となっている点にある。筆者は、ローマ大学のチェーザレ・ピネーリ教授とともに、冒頭の「Constitutions」という項目を担当している。世界中の研究者が参照する書物なので、独自の見解を披瀝するわけにはいかない。英米独仏といったところを中心として、オーバーラッピング・コンセンサスになっているところを述べていくことになる。 憲法関係で「ハンドブック」と称される書物は、他の出版社からも刊行されている。オクスフォード大学出版局も、2012年にThe Oxford Handbook of Comparative Constitutional Lawを刊行している。こちらの本では、筆者は「戦争権限 War Powers」の項目を担当した。武力の行使に関する権限の所在、コントロールのあり方に関する問題群を広く指して「戦争権限」と言われる。ここでも、各国の戦争権限に関する実務と学説とを客観的に記述するのが求められている。 他国の戦争権限について知ることは、日本人にとっても役に立つ。たとえば、日本が他国によって武力攻撃を受けたとき、大部分の日本人は、当然のようにアメリカ合衆国が武力を行使して日本を助けてくれると考えているようだが、それは「当然」ではない。日米安保条約の第5条は、日本国の施政下にある領域において、日米いずれかに対する武力攻撃が行われたときは、それぞれの国の「憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動すること」としている。「行動」の中には、武力の行使も含まれるであろう。問題は、「憲法上の規定及び手続」である。 |
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.
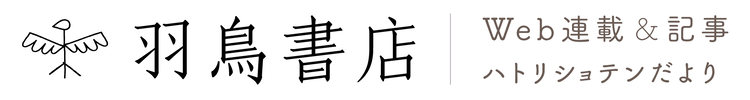

 RSSフィード
RSSフィード