|
藤田宙靖教授は、最近、「自衛隊76条1項2号の法意──いわゆる「集団的自衛権行使の限定的容認」とは何か」という論稿を著され(自治研究93巻6号(2017年6月号)、以下「法意」と略す。)、その中で、拙著『憲法の理性〔増補新装版〕』(東京大学出版会、2016)補論Ⅱで筆者が行った主張に対する応答をしておられる。筆者の主張は、藤田教授が以前に公表された論稿「覚え書き──集団的自衛権の行使容認を巡る違憲論議について」(自治研究92巻2号(2016年2月号)、以下「覚え書き」と略す。)への疑問を提示するものであった。
筆者が日頃から尊敬してやまない藤田教授から、拙論に対する応答をいただいたことは大変にありがたいことであり、また、藤田教授と筆者との間の対立点が奈辺にあるかを明らかにする上でも、大変に意義深いものであると筆者は理解している。結論を簡単に述べると、当初から懸念されたことではあるのだが、藤田教授には、実定法とその解釈に関する筆者の議論の意味内容が十分には伝わっていない。裏返して言うならば、藤田教授が理解するような法規範とその解釈との関係は、少なくとも実定法とその有権解釈との関係にかかわる限りでは、現代日本の法律家共同体の共通了解としては、およそ成り立ち得ないものであると、筆者は考えている。 藤田教授による法規範とその解釈に関する考え方の核心は、次のようなものである(法意14頁)。 「法律家共同体」の世界における法解釈論は、ある法律(ここでは憲法典をも含む)の規定が制定されることによって何らかの規範が生じたということを前提とし、その規範の内容はどのようなものか(何を定めているのか)あるいは、何が定められていると考えるのが最も妥当であるか、という問題を巡って、各論者がそれぞれに自分の考えを主張し競い合う、という思考枠組み・理論枠組み(法解釈論上の作法)の中で展開される。 この理論的な競い合いにおいては、「論者の平等が保たれている」。したがって、解釈を行う主体がたとえ内閣法制局であっても、「それ自体の性質はなお一つの「解釈」である」(法意15頁)。そうである以上、そうしたさまざまな解釈については、いずれかが「客観的に正しい唯一の解釈」であるということはあり得ない(法意11頁)。競い合う諸解釈は、あくまで「内容」の「適否」について同等の立場で競い合っている(法意15頁)。 こうしたスケッチから明らかになるのは、藤田教授は、現代日本の実定法は、あくまで制定法規であると考えているらしいことである。その解釈は実定法ではない。そして、実定法の諸解釈は、あくまで解釈であるという点ではすべて平等の地位にあり、いずれかが特権的地位に立つということはない。一学者の解釈論も、内閣法制局の解釈論も、そしておそらくは最高裁判所の解釈論も、すべては平等である。こうした理解からすれば、新たな解釈の方が「正しいと信ずる解釈」だというのであれば、「従前の解釈を変更することはいつでも許される」という立場を内閣法制局の「有権解釈」についてとることも、もちろん許されるのであって、それがなぜ筆者が主張するように「極めて不適切」であるのかは、「私 [藤田教授] には到底理解できない」(法意12頁)こととなるのも当然である。有権解釈とされる解釈と、学者の行う非有権解釈との間に差異はない。「通説・判例」にも何ら特別の地位が認められることはない(法意15頁)。 それにしても藤田教授は、単なる一法学者がその私的見解を改めるのと同様のことを2015年7月に内閣法制局は行ったに過ぎないと、そして、それにもかかわらずその結果として、安保法案に対するあれほどの広汎な国民の反対運動が起こり、数多くの著名な法律家が安保法案は違憲であるとの論陣を張ったのだと、本気で信じているのであろうか。また、その程度の見解の変更に過ぎないものの前提として行われた内閣法制局長官の人事が、あれほどの論議と批判を巻き起こしたことも、単なる一法学者の私的見解の変更と同等の帰結をもたらした、そのきっかけに過ぎないと、本気で信じているのであろうか。 さらにまた、藤田教授の覚え書きが公表されたとき、藁をも掴む思いでそれにすがりついた人々が手にしたのは、結局のところ、単なる一法学者が私的見解を改めるのと同等のことを内閣法制局が行っただけのことだから、あまり気に病むほどのことはないというアドバイスに過ぎないことになる。何より、すべての解釈論が同等なのだとすると、安保法案は違憲だと考える学者が口を揃えて違憲だと唱えたとしても、そのこと自体を非難したり疑問視したりする理由は藤田教授にはないということになるはずである。 |
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

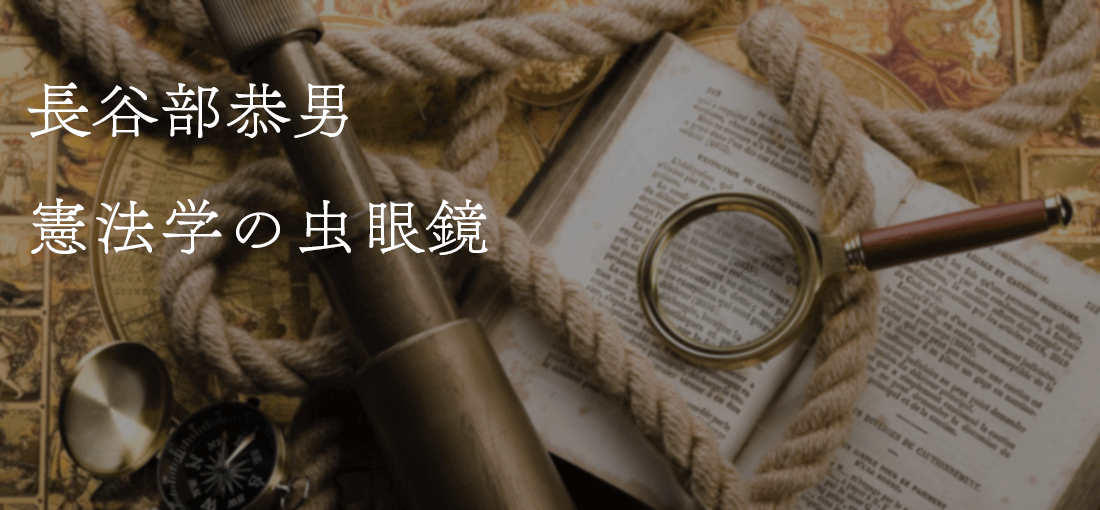
 RSSフィード
RSSフィード