|
ジャン-ジャック・ルソーは、一般意思と特殊意思を区別した。一般意思は社会全体の利益の実現を目指し、特殊意思は個人の(あるいは身の回りの人々の)利益の実現を目指す。個人の一般意思を多数決手続を通じて集計すると社会としての一般意思が得られる。特殊意思を集計しても、個別的な欲求の集積である全体意思が得られるだけで、一般意思にはならない。 政治思想史家のパトリック・ライリーによると、一般意思と特殊意思という区別は、神学上の論争に由来する。神は人類すべての救済を目指したのか、それとも個人ごとに救済するか否かを決めたのかが争われた。その区別が政治哲学に輸入され、ルソーによって概念の改鋳が施された(Patrick Riley, The General Will Before Rousseau: The Transformation of the Divine Into the Civic (Princeton University Press, 1986))。 神には意思とは別の理由(あるいは理由に対応して判断する理性)があるのだろうか。神の理性は人の理性と同じだろうか。分からない。神のことであるから。 人には意思と理性とがある。理由に対応して判断する能力が理性である。人の行動を方向づける理由、なぜそう行動したのか、それを理解可能なものとして説明することができる理由は実践的理由である。もっとも、人が行動するとき、いつもその理由は何かを意識するわけではない。本人が把握している限りの具体の状況において適切な行動が何か、何が適切でないか、意識することも熟慮することもなく直感的に行動することがむしろ殆どであろう。しかし、説明を求められれば、説明することはできる。その場で妥当するすべての理由をくまなく数え上げることは困難ではあるが。 理由にはいくつかの種類がある(この部分の説明は、ジョゼフ・ラズに依拠している。Cf. Joseph Raz, Engaging Reason: On the Theory of Value and Action (Oxford University Press, 1999))。ある選択を合理的なものとして理解可能(つまり説明可能)とする事情があれば、それは「十分な理由sufficient reason」である。 ある時点で人が直面する、十分な理由によって支えられた選択肢は、複数あることが通常である。それらの選択肢を支える十分な理由のうち、他の理由によって打ち消されない理由は「適切な理由adequate reason」である。適切な理由が一つだけであれば、判断には困らない。しかし、複数の適切な理由に直面することも少なくない。それらの理由は、比較不能である。 たとえば、近所に評判のフレンチ・レストランがあるとする。そこでは、おいしい料理が食べられるであろう。今夕はほかに用はないし、外食をする金銭的な余裕くらいはある。しかも近所にある。しかし、時間の空いている今夕は、近くの映画館で評判の映画を鑑賞するという選択肢もある。映像が美しく、プロットも巧みで役者の演技も上々であると言われている。もちろん、映画のチケットを購入する程度の金銭的余裕はある。二つの選択肢を支える理由は、いずれかがいずれかを打ち消すという関係にはなく、また、二つの緊要性が全く同じというわけでもない。そうしたとき、二つは比較不能である。比較不能性は世の中に満ち溢れている。 比較不能な理由によって支えられる複数の選択肢に直面したとき、そのいずれを選んだとしても、その選択は合理的である。どの選択肢も、他の理由によって打ち消されない十分な理由によって支えられているのだから。 適切な理由によって支えられる選択肢が一つだけ(つまり「結論を決定する理由conclusive reason」によって支えられる選択肢が存在する)という稀な事態においても、その選択肢を選ぶことに必ずなるわけではない。適切な理由によって支えられる選択肢が一つだけあるというのは、理性の判断である。それは人の意思や感情を拘束するわけではない。理性的に考えればすべきことは一つだという場合でも、そうしたくないということはあるし、結局そうはしないということもあるだろう。 比較不能な理由によって支えられる複数の選択肢に直面したとき、そのいずれを選ぶかを決めるのは意思である。意思は、ときに非合理的な決定をすることもある。適切な理由によって支えられる選択肢が一つだけであるにもかかわらず、それに反する行動をとる決定をすることさえある。人とはそうしたものである。自分がどういう人間かは、そうした選択を通じて徐々に形成される。そうした選択を通じて、人は自分が何者であるかを決めていく。人は自分の人格を部分的には自ら作る。 普遍性を標榜するありがたそうな道徳原理や定言命法は、生きる上での重大な岐路や困難な道徳的選択の場面ではほとんど役に立たない。そうしたものにこだわっていると、むしろ自分が構築してきた人格や無意識のうちに正しい選択を選び取る能力を損なうことになりかねない。 ルソーの一般意思と特殊意思の区別に戻ると、ここで問題とされているのは、意思なのであろうか。むしろ、社会はいかにあるべきか、いかなる社会を目指すべきか、その判断を支える理由が問われているように思われる。
そうではないという反論が考えられる。ルソーは、各人の欲求あるいは選好を問題にしていたというものである。自分はこうありたいという欲求(選好)が特殊意思、社会はこうあって欲しいという欲求(選好)が一般意思である。一般意思を集計すると、社会全体としての一般意思が結果として導かれる──それがルソーの想定である、という反論である。 そうであろうか。社会をこうするべきだという欲求なり選好なりは、なぜ社会はそうあるべきかという理由によって支えられているはずである。適切な理由(十分であり、かつ、他の理由によって打ち消されていない理由)によって支えられていない欲求は、非合理的な欲求であり、それを実現することに意味はない。個人の欲求もそうである。なぜその映画を見たいのか、なぜそのレストランに行きたいのか、それを説明できる理由があるはずである。理由もないのにある映画を見たくてたまらないというのは、精神病の一種であろう。あるべき社会像についても同じである。なぜそうした社会を構築すべきか、その理由がなければならない。理由がなければ、そうした社会の構築を説明する物語もない。理由のない欲求に従うのでは、わけの分からないことをしているだけである。 しかし、欲求や選好と異なり、理由を集計することは意味をなさない。一つの正しい理由は、何名の人が支持しようと、一つの正しい理由である。一つの誤った理由は、何名の人が支持しようとも、一つの誤った理由である。では多数決の手続をとることにどのような意味があるだろうか。 一つの解釈は、異なる理由によって支えられる複数の選択肢に直面したとき、いずれの選択肢が客観的に見て適切な(正当な)理由であるかを判断するために、多数決という手続がとられるというものである。一定の条件が整っている場合には、投票参加者の数が増せば増すほど、単純多数決で客観的な正解に到達する確率が高まるというコンドルセの定理に基づく説明が提示されている(この点については、拙著『比較不能な価値の迷路』〔増補新装版〕(東京大学出版会、2018)第6章参照)。 しかし、適切な理由によって支えられるあるべき社会の姿がただ一つしかないという想定は、あまりにも硬直的で現実離れしているように思われる。互いに比較不能な、それぞれ適切な理由によって支えられた複数の社会像が存在するという想定の方が良識にかなう。政府の活動規模を大きくし所得の再配分機能を高めて人々が平等な暮らしを送ることのできる社会が善いのか、政府の活動を縮減し、富や所得の格差はあっても人々が自由に活動できる範囲を可能な限り確保する社会が善いのか。あるいは、周辺地域全体の安全を保障し得るほどの膨大な軍備を備える社会が善いのか、それとも軍備は自国のみを防衛し得る程度に抑え、経済や文化の発展により力を注ぐ社会が善いのか。全く前提なしの更地で考えたとき、いずれがより善いとも、両者は全く同じ価値だとも言いにくい。比較不能である。 理由のみに基づいてはいずれの判断が正しいかを決めかねるそうしたときでも、いずれをとるかを決定する必要がある。両立し得ない複数の社会像を一つの社会の中で実現することはできない。実現すべき社会は、社会全体として一つに決まっている必要がある。そのために多数決という手続が踏まれる。個人の意思決定にあたる手続である。そうした役割を果たす手続であれば、自分が適切だと考える社会像に反する決定がなされたと考える人の数を可能な限り少なくする必要がある。ハンス・ケルゼンは、単純多数決こそがそうした特性を備えていると主張した(『民主主義の本質と価値』長尾龍一=植田俊太郎訳(岩波文庫、2015)参照)。 もっとも、以上のような物語による説明がうまく当てはまるためには、人々に示される選択肢が、いずれも適切な理由によって支えられたものである必要がある。現実の政治においてそうした条件が満たされているかは、事実に基づいて適否が決まる経験的な問題であり、先験的に結論を決めることはできない。 ときには、社会として実現すべき緊要性が結論としても分かり切っている決定を先延ばしにするという選択肢をほとんどすべての政党が提示して選挙戦が遂行されることもないとは言えない。社会として必要であるに決まっている政策の実現が有権者の意に染まないのではないかと恐れて、必要な政策を提示しようとしないこともあるだろう。たとえば、巨額の財政赤字に対処するために、消費税率を上げざるを得ないことは分かっているのに、すべての党がそれを先送りしようとする場合である。非合理的な選択肢のみに直面した有権者は、どの非合理的な政党の候補者を選ぶかという究極の選択を迫られることになる。 民主的に決まったことだから、必ずその通りにすべきだということになるわけではない。適切な理由に対応する能力を備えた、すぐれた政治家を育てることが肝要である。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

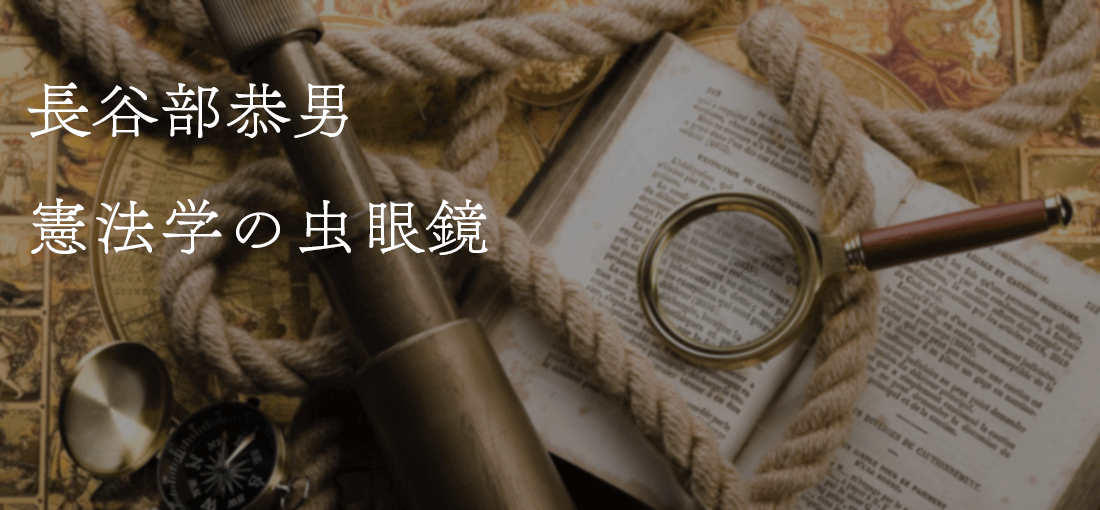
 RSSフィード
RSSフィード