|
モーシェ・ハルバータルとスティーヴン・ホームズの共著『政治のはじまり』(Moshe Halbertal and Stephen Holmes, The Beginning of Politics: Power in the Biblical Book of Samuel (Princeton University Press, 2017))は、第2章で『サムエル記』が伝えるノブの大虐殺を分析する。 イスラエルの王サウルは、自身の女婿であり側近の武将でもあったダビデが王位をうかがおうとしているのではと疑い、その命を奪おうとする。ダビデはサウルの息子ヨナタンとサウルの娘ミカルの助けで危うく難を逃れ、ノブに住むヤハウェの祭司アヒメレクを訪ねる。供も連れずただ一人であらわれたダビデをアヒメレクは不安げに迎え、なぜ一人なのかと問う。ダビデは、王サウルの密命を帯びて急遽出立したと嘘をつく。供とはこれから落ち合うところだが、何か食糧はないか、武器はないかと訊ねる。お供えものの聖別されたパンはある、ダビデがかつて討ち倒したペリシテ人ゴリアテの帯びていた剣ならあるとアヒメレクは答える。ダビデはお供えのパンとゴリアテの剣を得て、逃亡の旅を続ける(I 19: 1 – 21: 10)。 他方、被害妄想にとりつかれた王サウルは側近の臣下に、なぜおまえたちは共謀して自分に背くのか、なぜヨナタンとダビデが契約を結んだことを誰も自分に告げないのか、と当たり散らす。しかしサウルは、そもそもイスエラルの王になりたくてなったわけではない。サムエルが民をミツパに集め、くじによってまず部族を、そして氏族を選び、最後にサウルを王として選んだとき、サウルは荷物のかげに隠れていた(I 10: 22)。 しかし、イスラエルの民をペリシテ人をはじめとする周辺の敵対者から守るため、民に望まれ、心ならずも王に選ばれたサウルは、次第に王の地位に恋々としはじめる。ダビデが巨人ゴリアテを討ち倒して戦いを勝利に導いたのち、人々が「サウルは千を討ち、ダビデは万を討った」と喜び歌うのを聞いて、サウルは怒りに燃え、「ダビデには万を当て、私には千を当てる。彼に与えるとすれば、あとは王国だけだ」と言い放つ(I 18: 6-8)。民の幸福と安全を保障する手段であるはずの王位が、被害妄想と猜疑心にさいなまれたサウルにとっては自己目的化し、人民や臣下はもちろん自身の息子や娘にいたるまで、手段としてはならないものまでが、王位を保つための手段と化す。権力は私物化され、権力者はその虜となる。 側近の部下に対してまで、自分の地位をダビデに渡すために共謀しているのかと尋ねるサウルに情報をもたらしたのは、エドム人、つまり異邦人のドエグであった。彼は、祭司アヒメレクがダビデに食糧を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣をも与えたと告げる。アヒメレクはダビデに騙されてそうしたのだが、ドエグはあたかもアヒメレクがダビデと共謀しているかのように語る。これでサウルの猜疑心は、側近の臣下から、ノブの祭司アヒメレクへと向かった。 サウルは、アヒメレクだけでなく、彼の一族すべてを呼び出し、なぜダビデと共謀して自分に背いたかとアヒメレクを詰問する。 アヒメレクは、ダビデに騙されたと答えることもできたはずである。しかし彼は、ダビデがサウルの臣下の中でも最も忠実で一族の中で最も尊敬されている人物であることを指摘する。サウルとダビデとが反目していることについて、彼が一切何も知らなかったのも当然である。ダビデに対して強い猜疑心を抱き命を狙うサウルを暗に批判する応答である。 サウルは激怒し、アヒメレクだけでなく、彼の一族すべては死ななければならないと言い、護衛の者たちにダビデと手を握るヤハウェの祭司どもを殺せと命ずる。しかし、臣下たちは祭司に手を出そうとしない(I 22: 17)。 ハルバータルとホームズは、ここに権力のある普遍的な特質があらわれていると言う(Halbertal and Holmes, op. cit., p. 75)。あらゆる統治者と同じく、サウルも臣下の協力を必要とする。王がその命令を執行させるには、現場で武力をふるう執行者にとって、王の命令が正当性を帯びるものでなければならない。直接に実力を行使する部下が一致して協力を拒むとき、王の命令はもはや命令として機能しない。アヒメレクは同じイスラエル一族の司祭であり、神に仕える者である。また、たとえアヒメレクがダビデと共謀していたとしても、彼の一族がすべて殺されねばならないのであろうか。 部下の抵抗に直面したサウルは、ドエグに、おまえが祭司どもを討てと命令する(I 22: 18)。ドエグは異邦人である。アヒメレクもその一族も、ドエグにとって同胞ではない。支配する人民の信頼を失った統治者にとって頼りとなるのは、異邦人の傭兵である。ドエグは祭司85人を殺し、さらに祭司の町ノブを襲って、男女を問わず、子どもや乳飲み子にいたるまでを刃にかけた。家畜も同様に皆殺しである。同胞であることを信頼の証となし得ないドエグにとって、王のおぞましい命令を忠実に執行することこそが、自身の身を守ることになる。臣下の信頼を失った王と同胞を頼りとなし得ない異邦人の傭兵とは、大虐殺において密接な共犯関係に立つ。その結果、王と傭兵とはさらに自分たちを孤立させることになるのだが。 アヒメレクの息子エブヤタルだけが難を逃れ、ダビデのもとに走り、サウルによる祭司たちの虐殺について知らせた。ダビデのことばは奇妙に冷静である。私があなたの父の家の者全員を死なせてしまった、私の命を狙う者は、あなたの命をも狙う、私と一緒にいれば、あなたは安全だと、ダビデはエブヤタルに言う(I 22: 22-23)。 『サムエル記』の描くサウルは、何を考えているのか、怒っているのか、悲しんでいるのか、恐れているのか、その心理が手にとるように分かりやすく描かれている。ダビデは違う。何を考えているのか、よく分からない。ダビデはアヒメレクとその一族の死について、自らの犯した非を悔やんでいるのだろうか。それとも、サウルが自分の命を狙っている以上、こうなるのも仕方のないことであり、エブヤタルにとって最も安全な途は、自分と行動をともにすることだと、ただ客観情勢を分析し、将来を予測しているだけなのだろうか。
ダビデはサウルの追及の手を逃れるため、ペリシテ人の領主アキシュの下に身を寄せる。しかし、ペリシテ人の他の領主たちはダビデを信頼せず、ヘブライ人との戦いに彼が加わることに異議を唱える。この男は、サウルは千を討ち、ダビデは万を討ったと人々が踊り、歌い交わしたあのダビデではないか、と領主たちは言う。アキシュはダビデに帰るようにと命じ、こうしてダビデは、ギルボアの地でのサウルとの最後の決戦に臨む定めを逃れた。 イスラエル軍はペリシテ人とのギルボアの戦いに敗れ、ヨナタンを含むサウルの息子たちは戦死し、サウル自身も自決する。サウルの死の知らせをダビデのもとにもたらしたのは、アマレク人の男である。彼は、褒賞をもらえると信じたのか、瀕死のサウルを自ら手にかけたとダビデに告げる。それに対してダビデは、ヤハウェの油注がれた者を手にかけるとはなにごとかとなじり、従者にその男を殺させる。「おまえの血は、おまえの頭上に降りかかれ。おまえ自身の口が、『私はヤハウェの油注がれた者を殺した』と自分に不利な証言をしたのだ」とダビデは言う(II 1: 1-16)。 サウル本人のことを思っての判断であろうか。ダビデ自身、サウルを見放したサムエルにすでに油を注がれている(I 16: 13)。サウルと異なり、ダビデは自身に対して疑いを抱いているようには見えない。しかし、いったん王となったとき、その地位を守る必要があることに変わりはない。サウルを殺害した(と自ら証言する)者をダビデが死刑に処すことは、ダビデ自身がサウルの死に関与していないことを宣言することであると同時に、将来のダビデ自身を守ることにもなる。自らのかつての主君であり、義理の父親であるサウルを心から悼んでのことなのか、それとも自身の潔白を世間に向かって示し、しかもこれから王位に就く自身を守るための演技なのか、解釈の分かれる点である(Halbertal and Holmes, op. cit., pp. 48-50)。そもそも、ペリシテ人の領主たちの反対がなければ、彼自身、サウルとヨナタンの軍勢と戦わざるを得なかったはずである。彼にサウル落命の責任がないのは(本当にないのか?)、たまたまの事情による。 バト・シェバの夫、ウリヤの死に関しては、ダビデの責任は明白である。王となったダビデはヨアブに全軍を率いさせ、アンモン人との戦いに送り出した。ダビデ自身は、エルサレムにとどまった。ある日、ダビデが王宮の屋上を散策していたところ、美しい女が水浴びをしているのが見えた。ヘテ(ヒッタイト)人ウリヤの妻、バト・シェバである。ダビデは使いの者を立てて彼女を召し入れ、共に寝た。帰宅したバト・シェバは、子を宿したと知らせてきた(II 11: 1-5)。 ダビデはもみ消しをはかる。彼はヨアブに、ウリヤをエルサレムに寄こすよう命ずる。帰還したウリヤにダビデは戦況を尋ねたのち、自宅に帰るよう命ずる。ところがウリヤは、王宮で家来たちと共に眠り、自宅に帰らない。なぜ帰らないかと訊くダビデに、ウリヤは、神の箱もイスラエルもユダも戦場で野営しているとき、自分だけが家に帰って飲み食いし、妻と寝ることはできないと答える(II 11: 6-11)。至極まっとうな(まっとうにすぎる)答えである。 ダビデはさらに邪悪な策を弄せざるを得なくなる。戦場に戻るウリヤに、彼はヨアブ宛ての書簡を持たせる。書簡には、ウリヤを前線に送り出した上で全軍を引き上げさせろ、そうすれば彼は死ぬであろう、と記されている(II 11: 15)。ウリヤは自身の死刑執行令状を持参したことになる。ダビデは自らウリヤに手をかけようとはしない。彼は戦場から遠く離れた、安全な王宮にいる。ウリヤを殺すのはアンモン人である。そうした状況を作るのはヨアブであり、彼の指揮に従う軍である。指令と事態の連鎖の中で因果は分散され、誰が何に責任を負うかは不分明となる。「私がウリヤを殺したこと、それは一切ないわけであります」というわけである。 ヨアブはダビデの命ずる通りにはしない。ウリヤ1人を前線に残し、全軍を引き上げさせれば、軍の長であるヨアブがウリヤ1人を意図的に見殺しにしたことが誰の目にも明らかとなる。ヨアブは自ら軍を率い、敵の城砦近くまで、それも守りの堅いことが分かっている場所へと軍を進める。城砦からの激しい応戦により、ダビデの兵は倒れ、ウリヤも死んだ。いかに忠実な部下にも、命令の執行にあたっては裁量の余地が残る(Halbertal and Holmes, op. cit., p. 89)。自らも前線に向かいリスクを背負うことで、ヨアブは軍の信頼を失うことなく、王の望む結果をもたらした。 ヨアブは使者を立ててダビデに戦況を報告させる(II 11: 19-21)。彼は使者に、報告を二段階に分けるよう指示する。まずわが軍が城砦に接近して戦い、その結果、味方の兵に死者が出たことを報告せよ。それを聞いて王が怒り、なぜそんな危険な戦術を選んだかと問い糺したら、つぎにあなたの家来、ヘト人ウリヤも死にましたと報告するように。 家来はしかし、王に一挙に結果を報告する。敵はわが軍より優勢であったが、それをわが軍は城壁まで押し返した。そのとき敵の射手が城壁から矢を射かけ、わが兵に死者が出て、ヘト人ウリヤも死んだと(II 11: 23)。ヨアブのように報告を二段階に分ければ、不必要にダビデの怒りを買う上に、ウリヤの死をダビデが望んだことに勘づいていることを暴露することになる。ここでも忠実な部下は、自分の身を守るため、命令の執行にあたって裁量を行使している(Halbertal and Holmes, op. cit., p. 93)。 これに対してダビデは、戦場では剣はどちらの側にも向かうものだ、心配しないようにとヨアブに伝えよと答える(II 11: 25)。ウリヤの死の責任は誰にもない。戦場では敵味方関係なく、誰かが死ぬものだ。ウリヤもたまたま死んだ。彼の巻き添えとなったイスラエルの兵の死も、誰の責任でもない。戦争のリアルな面を指摘することで、自身の悪事を隠蔽しようとしているのだろう。ダビデが何を考えているのか。悔やんでいるのか、ホッとしているのか、怒っているのか(誰を?)、恐れているのか、ここでも分からない。 バト・シェバの喪が明けたとき、ダビデは彼女を召し入れ妻とした。彼女は子を生んだ(II 11: 27)。ダビデの一連の行動は、王宮内部および一族の間でのダビデの道徳的権威を失墜させた。その後起こった、長子アムノンによる妹タマルの強姦、タマルの兄アブサロムによるアムノンの暗殺、さらにはアブサロムの叛乱と敗死は、ダビデの権威失墜と一族に対する統制力喪失の帰結である(Halbertal and Holmes, op. cit., p. 111)。 *『サムエル記』のテキストについては、旧約聖書翻訳委員会訳『サムエル記』(岩波書店、1998)およびRobert Alter, The Hebrew Bible, vol. 2, Prophets (W.W. Norton & Company, 2019)を参照しました。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

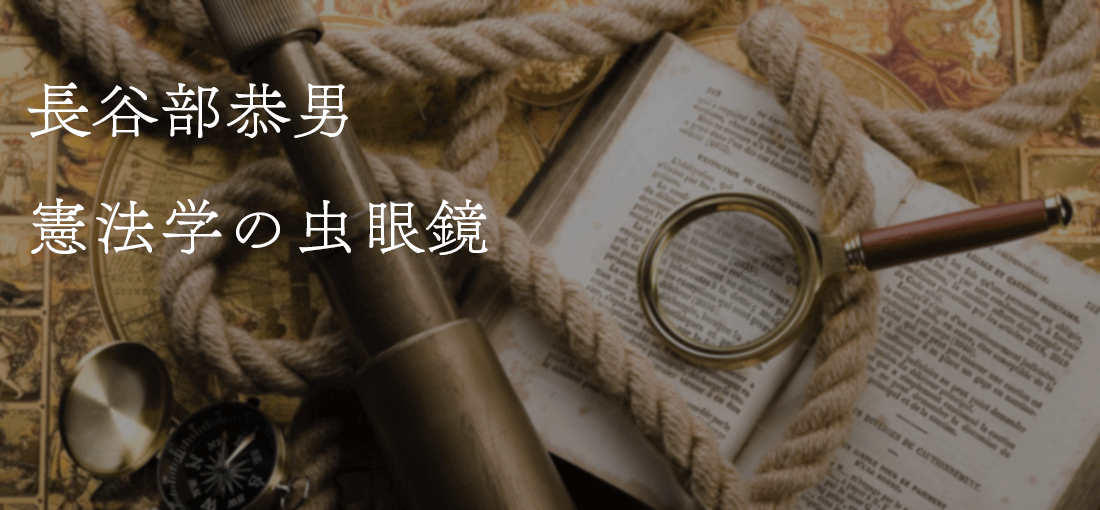
 RSSフィード
RSSフィード