|
日本国憲法73条1号は、内閣の職務として「法律を誠実に執行し、国務を総理すること」を挙げている。「国務を総理すること」が何を意味するかについて、近年では、それがいわゆる「統治」ないし「執政」を含むか否かについて論争がある。 ここで取り上げるのは、およそ論争が起こりそうもない「法律を誠実に執行し」の方である。行政権をつかさどる内閣が、法律を誠実に執行すべきことは、疑う余地のない明白なことのように思われる。しかし、そうであろうか。 教科書や注釈書の類で議論されているのは、内閣が違憲だと考える法律の執行を拒否できるかである。日本国憲法は、議院内閣制の仕組みを採用しており、法律として可決・成立する法案の大部分は、内閣提出法案(いわゆる「閣法」)である。また、議員提出の法案であっても、少なくとも衆議院の多数派を支配しているはずの政権・与党が違憲だと考える法案の成立を阻止することは、容易である。現実には、なかなか起こりそうもない設定ではあるが(政権交代が起こったときであろうか)、学説の多くは、内閣はたとえ違憲だと考える法律であっても、その法律の執行を拒否し得ないとする。 とすると、内閣は現に存在する(妥当している)法律は、すべて100パーセント執行する義務を負うのであろうか。少し考えてみれば分かるように、そんなことは不可能である。グリコ・森永事件を引き合いに出すまでもなく、明々白々たる犯罪であっても、その犯人を必ず検挙できるわけではない。また、犯罪を実行した容疑で逮捕されたとしても、必ず起訴されるわけでもない。さらに、軽犯罪法で明確に犯罪とされている行為であっても、日常的に放置されている行為も少なくない。 刑事法の領域でさらに話を進めると、内閣には恩赦を与える権限も認められている(憲法73条7号)。裁判による刑の言い渡しの効果を変更(減軽)し、特定の罪について公訴権を消滅させることができる。この罰条については、執行しませんと明示的に宣言することさえできるわけである。 となると、内閣を頂点とする行政は、違憲だとは考えない法律(とその適用結果である判決)であっても、行政独自の判断で、100パーセントの執行はしないことが、憲法上も許容されていることになりそうである。法の支配や権力分立原理は、一体どうなってしまうのだろうか。 一つの答え方は、利用可能な人的・物的資源の範囲内で可能な限り「誠実に法律を執行」することが求められているのであって、それ以上のおよそ実現不可能なことは求められていない。したがって、たとえ行政が法律の要求を100パーセント実現し得ないとしても、そこに故意・過失があるとは言えず、少なくとも国家賠償責任を問われることはない、というものであろう。また、恩赦は憲法自体が明示的に認める例外であり、例外にとどまり続けている限りは、さほど気にするにも及ばない(あなただって、そんなに気にしていなかったでしょう)。起訴便宜主義も、刑事訴訟法が明文で認めている話である(248条)。 ところ変わってアメリカの話である。アメリカ合衆国の大統領は、連邦議会が可決した法案に署名するにあたって、大統領が当該法律をいかに解釈し、行政各部にいかなる執行を指示するかについての大統領の見解を明らかにする声明(signing statement)を付加することがある。
ジョージ・ウォーカー・ブッシュ政権下で世論の強い批判を浴びた問題として、テロ容疑者を、ウォーター・ボーディング(水責め)等の拷問にかけていた事件があった。これに対して連邦議会は、2005年12月にマケイン上院議員の提案した拷問禁止法を圧倒的多数で可決したが、署名に際してブッシュ大統領が公表した声明は、軍の総指揮官および一元的な行政府の長(head of the unitary executive branch)である大統領の権限と整合するように同法を解釈・適用するよう公務員に求めている。要するに、安全保障上の必要性があると認めるときは、拷問──「強化された尋問enhanced interrogation」と言うべきか──を命ずる権限が大統領にあることを示唆している。 オバマ政権下でも、移民国籍法(Immigration and Nationality Act)の下で退去強制の対象となり得る若年者の中で、幼少期に来米し通常のアメリカ人と同様に生活しているなど、一定の条件を満たす者については退去強制措置を延期し、その間、就労許可を認める措置を大統領令(Deferred Action for Childhood Arrivals: DACA)によって施行した例が知られている。 アメリカの大統領は、連邦議会の制定した法律であっても、場合によってはその法律を適用しないと公然と宣言し、それを実践に移す。日本国憲法下での立法と行政の関係とは、異なる理解が妥当している。 アメリカ合衆国憲法上の諸観念は、イングランド法に遡ることのできるものが多い。一般的ルールの適用停止(dispensation)もその一つである。1688年の名誉革命をひき起こした要因の一つは、ジェームズⅡ世が、カトリックの公職就任を禁ずる審査法(the Test Act)の執行を一般的に停止したことである。王太子時代からカトリックであることを公にしていたジェームズは、審査法にもかかわらず、多くのカトリックを文官・武官の要職に採用して世論の反感を掻き立てた。 1688年の「7司教事件the Seven Bishops case」で問題とされたのは、カンタベリー大司教を含む7名の司教が、ジェームズⅡ世が1688年4月に布告した第2次寛容令(the Declaration of Indulgence)──カトリックの公職就任を禁止する審査法(the Test Act)の一般的な執行停止の宣言──を説教壇から読み上げることを拒否する旨の陳情を行ったことである。7名の司教はこの陳情を行ったことを理由に、文書煽動罪(seditious libel)に問われた。 事件の根本にあった対立点は、国会制定法の執行を免除する国王の権限(dispensing power)が宗教上の問題にも及ぶか、そして国王の執行免除権限が個別の事例を超えて法律の執行を全面的に停止する権限にまで及ぶかであった。訴訟の場では、司教らの陳情行為が文書の「出版publish」にあたるか、さらに当該陳情が政府の名誉を毀損したか、司教らに「故意malice」はあったか等の論点も争われた。審理にあたった複数の裁判官は、審理終結の際の陪審説示において法律上・事実上の争点について相互に見解を異にし、夜通しで評議した陪審は、司教らの行為は文書煽動罪には該当しないと判断して、全員が無罪となった。 1689年の権利章典(the Bill of Rights)はその前文で、「前王ジェームズⅡ世が、邪悪な顧問官、裁判官、廷臣の補佐により、プロテスタンティズムとこの王国の法と自由を覆し根絶しようとした」旨を述べている。悪行の筆頭に掲げられているのは、「国会の同意なく、法律および法律の執行を免除し、停止する(dispensing with and suspending)権限を僣称したこと」である。章典の本文は、「法律または法律の一部の執行を停止する国王の措置(non obstante)は無効である」旨を明らかにしている。ダイシーの『憲法序説』は、権利章典を根拠としつつ、法に従う義務を政府(the Crown)が免除することはできない、というルールをlaw of the constitutionの典型例として挙げている(An Introduction to the Study of the Constitution, 10th ed., p. 25)。 章典はさらなるジェームズの悪行として、「勾留された刑事被告人に過大な保釈金を要求したこと」、「過大な罰金を科したこと」並びに「法に反する残虐な刑罰を科したこと」を挙げる。ジェームズ治下での残虐な刑罰を象徴するのは、チャールズの没後、ジェームズの王位継承を阻止すべく1685年に武装蜂起したチャールズの非嫡出子、モンマス公の反乱に加担した者を裁いた「血の巡回裁判the Bloody Assize」である。この裁判では、200人以上の者が絞首された後、斬首の上、身体を四つ裂き(quartered)にされ、塩ゆでにされた挙げ句にタールを塗られて街灯や樹木にさらされた。 血の巡回裁判の最も著名な犠牲者は、老齢で耳が不自由であったレイディ・アリス・ライルで、彼女は反乱に加担し敗走した知人を匿った罪で起訴された。彼女は裁判で、自分は知人が反乱に参加したことを知らなかったし、その外見や振る舞いにも、戦いに加わったことを示すものはなかったと弁明したが、裁判長であったジョージ・ジェフリーズは陪審に対して、「この嘘つきでめそめそした哀れっぽい長老派の悪党は、いずれにせよこの前の陰謀と反乱に加わっていたのだ」と教示し、有罪の評決が出ると彼女を火あぶりの刑(stake)に処した。ジェームズは刑を減じて斬首とした。 過大な保釈金・罰金の禁止、残虐刑の禁止は、1791年に成立した合衆国憲法第8修正へと受け継がれた。そして、同修正は形を変えて、「残虐な刑罰」を絶対に禁ずる日本国憲法36条へと受け継がれている。 国王による法律の執行停止は、法律の規定する一般ルールを個別の場面で執行しない権限を国王に認めるものである。ジェームズが行ったように、法律自体の存在意義を掘り崩しかねない一般的な執行停止は、問題が深刻にすぎる。ただ、翻って考えると、そもそも行政権が法律を100パーセント、額面通りに誠実に執行するのであれば、立法と行政とを分立させる意味はどこにあるだろうか。具体の場面において、法律の文面通りには執行しないという行政の判断が可能であって、はじめて両者を区分することに意味があるとは考えられないだろうか。 一般的なルールの定立と個別の場面でのその執行とでは、別個の判断があり得るのではないかという問題は、奇蹟は起こり得るかという神学上の問題と関連している。神が完璧な一般法則に基づいてこの世を創造した以上、神は創造後のこの世の出来事に個別に介入するはずはないという立場(理神論)はあり得る。そうであれば、奇蹟は起こり得ない。神の創設した一般的ルールの内容に、なお人知の及ばない部分があるために、奇蹟であるかのように人には見えるだけの話である(マルブランシュやスピノザは、そう主張した)。 他方、神は個別具体に人事に介入するという主張も見られる。フランスをブルボン家という特定の家系が支配するに至ったのも、ハプスブルク家のマリー-テレーズとルイXIV世の間に婚姻が成立したのも、神の特殊摂理(providence particulière)によるとするボシュエの主張は、その典型である。一般秩序に安住しようとする哲学者たちへの軽蔑をボシュエは隠そうとしない(Oraison funèbre de Marie-Thérèse d’Autriche)。 特殊意思に基づく神のこの世への介入の余地を認めるとき、ある事象が一般意思の結果か、特殊意思の結果かを見分けることは難しくなる。死に至る決闘直前のハムレットが述懐するように、「雀一羽落ちるのも神の特殊摂理(special providence)」であり、「今でなくとも、来るものは来る」というわけである(『ハムレット』第5幕第2場。邦訳では普通、「特殊special」は省略されている)。一般意思も特殊意思も、同じ神の意思である。具体の事象をいくら観察・分析しても、一般か特殊かを見分けることはできない。 立法と行政とを分立させれば、一般意思と特殊意思とは区別できるように見える。しかし、行政が100パーセント法律を誠実に執行するだけであれば、そこに本当の意味での特殊意思はない。あるのは一般意思とその誠実な具体化だけである。 日本では行政権による法律の執行停止という論点が、そもそも意識されることがない。それを意識しないで済むことは、幸福なことなのであろう。法律が果たしてどこまで額面通り、誠実に執行されるべきなのかという問題が、この世から消えてなくなるわけではないのだが。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.
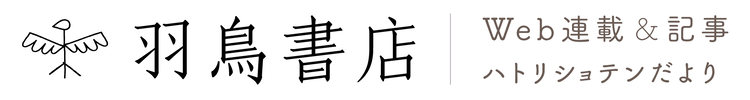

 RSSフィード
RSSフィード