|
カール・シュミット著『政治的ロマン主義Politische Romantik』*は、初版が第一次大戦直後の1919年に刊行された。同年6月にはヴェルサイユ条約が調印され、8月にはワイマール共和国憲法が制定されている。シュミットは、18年11月のストラスブール大学閉校のため、同大私講師の地位を失い、19年9月にミュンヘン商科大学講師の職を得た。その間、彼はミュンヘンで行われたマックス・ウェーバーの講演「職業としての政治」に出席している。 ロマン主義という概念の使用法は恐るべき混乱に陥っており、両立し難い多種多様な意味が込められているというのが、シュミットの診断である。彼によると、ロマン主義を特徴づけるのは、カスパー・ダーフィト・フリードリヒに代表される山岳風景や廃墟の描写でもなく、神秘主義や異国情緒や恋歌でも、ましてや革命思想でもなければカトリシズムに連なる保守主義でもない。合理主義でも古典主義でもないものをロマン主義とまとめて呼んだところで、意味のある理解にはつながらない。ロマン主義を特徴づけるのは、その形而上学的前提であり、そこから流出する個人観と世界に向き合う姿勢である。 ロマン主義の形而上学的前提はOkkasionalismus (英語で言うoccasionalism。シュミットはOccasionalismusと綴る)である。日本語では偶因論とか機会原因論等と訳されているようであるが、何のことだか今一つピンと来ない。occasio, occasionには、たしかに偶然事(Zufall, contingency)という意味も含まれるが、ここではあり得る批判を恐れずにあえて「事象主義」と訳すことにしよう。シュミットは事象主義の代表的論者として、マルブランシュの名をしばしば挙げる。 ことの起こりは、デカルトが始めた心身二元論にある。人は心と身体からなる。この2つはどのように相互作用するのか。それともしないのか。心が身体を支配しているのか、それとも心は幻ですべては身体の働きなのか。どちらでもないのか。 この疑問への回答(の1つ)が事象主義である。心に浮かぶ想念、身体の動き、それらはすべて何の原因でもなく何ももたらさない。つまり、心身は相互作用を起こすことはない。すべての原因は神であり、心や身体の動きはその単なる現れ(事象)に過ぎず、本質的な意義を持たない。特定の身体の動きという事象に対応して、神は適切な心理状態をもたらす。特定の心の動きという事象に対応して、神は適切な身体の動きをもたらす。それだけである。 そうなると、ことは心身の相互作用にはとどまらない。この世界で起こっている(かのように見える)すべては、唯一の真の原因である神の力の現れであり、それ自体は何の原因でもない。それらの間には何の一貫性も整合性も因果関係もない。バラバラの事象群に過ぎない。 時は近代に至り、神は退場した(多くの人々にとっては)。しかし代替物はある。歴史を突き動かす理性、生産力の発展段階、共同体の理念と命運等々である。いろいろな候補があり得るものの、ロマン主義者に共通するのは、この世の出来事、自身の経験のすべては、本質的な意義の欠けたかりそめの事象に過ぎないという姿勢である。本質的な原因は、諸事象の背後にあるすべてを支配する真の実在、別次元の高度な力に求められる。 この根本的な形而上学から──論理必然というわけではないのだが──この世界に対するさらなる態度と思考様式が導かれる。まず、この世のすべてはかりそめの事象に過ぎない以上、それに対する適切な態度は、美的な観点からの受け入れであり、鑑賞/ 感傷である。つまり受け身の姿勢である。この世の事象に積極的に関与する意味はない。しかし、審美的鑑賞/ 感傷の主体はあくまで「私1人」であり、そこから奇妙にも主観の絶対化が帰結する。こうして生まれた絶対的主観はこの世のすべてに対し、恋人であるはずの対象に対してさえ無責任でアイロニカルな態度をとる。崇拝の対象となるべき恋人の気高さは、ドン・キホーテにとってのドルネシア姫と同様、実は自身の美的インスピレーションの反映であり、恋人そのものは偶然の事象(Anlaß)に過ぎない。 しかし、こうしたアイロニーは絶対化された自身には妥当しない。そこに立ち現れるのは、自己に対する客観視を欠いた、つまりユーモアのセンスを欠いた大まじめでpatheticなアイロニーである。道徳も倫理もその意義を否定され、すべては個々人の情動と霊感へと解消される。つまり、ロマン主義とは、極端に主観化され、私化された事象主義である。 こうしたロマン主義の形而上学と姿勢とは、政治の世界にも当てはまる。政治的ロマン主義は、何か特定の主義主張と必然的に結びつくわけではない。フランス革命が起こればフランス革命と結びつき、王政復古となれば反動的復古主義と結びつき、7月革命が起これば、またまた革命と結びつく。
政治の世界で起こる革命、反動、戦争、クーデター、ゼネスト、集会、審議、選挙等々は、本質的な意義の欠けた、何事の原因でもない、かりそめの事象の連なりに過ぎない。それらは、個々の絶対的主観にとって、さまざまな情動をもたらし、批評と論争の対象とはなるものの、決断とコミットの対象となるものではない。政治の世界におけるロマン主義者たちは、そのため、あくなきオシャベリに明け暮れる。オシャベリが何事かを解決するわけでもなく、発言の結果として何かに責任をとるべきことにもならない。オシャベリは果てしなく続き、何事も解決されず、誰も何に対しても責任をとることはない。そもそも、政治的決断と行動は、ロマン主義者からすれば何の意味もない。彼らにとって意味を持ち得るのは、異次元に属する、美化され詩作の題材となり、偏愛の対象となり得る国家や王室、民族や階級ではあり得ても、現実の政策や法制度ではない。 シュミットは、こうした政治的ロマン主義者による果てしないオシャベリ政治──現在では上品にも「討議民主主義deliberative democracy」と呼ばれているが──を支える制度的前提があることを示唆する。公私を区分するリベラリズムの政治体制である。シュミットは、絶対的真理であることを要求するキリスト教に対して、リベラルな宗教的寛容を遂行しようとしたユリアヌス──「背教者」と呼ばれるユリアヌス帝──をロマン主義者として紹介する。 絶対的主観と化した個人を政治の「現実」、究極の力の行使から守り、多様な政治的・思想的立場の存立を私的領域において保障するリベラルな政治体制があってこそ、政治的ロマン主義は成り立つ。リベラリズムの下での議会主義が、喫緊の現実的課題に対して解決策を示すことも、敵と味方とを決然と判別することもなく、果てしないオシャベリに興ずることに、何の不思議もない。国民全体にとっての課題を解決すべき議会は主観的な情動と私的諸利害に占拠され、誰も何の責任もとろうとしない。1925年刊行の第2版序言でシュミットが描くように、あらゆる国家制度、法概念、さらには民主主義そのものも空虚な欺瞞であり、うわべだけの装飾、フェイクに過ぎないのだから。こうした観察が、議会主義を廃棄し、異質な諸要素を排除し、法や倫理の拘束から解き放たれて(absolved)行動する、民主制の絶対主義(absolutism)を唱導する後のシュミットを支えている。 それにしてもシュミットを読んでいると、何か見知らぬ異次元の力と直感に捉えられ、突き動かされて、最後はリベラリズムの根底的批判へと行き着いてしまう。何とも不思議なことである。 『政治的ロマン主義』からは、シュミットが、分析対象とされたさまざまな思想家に対して、何の共感も抱いていないことがよく分かる。本書の何とも言えない読みにくさは、そこから(も)生まれている。その場限りで雑多でとりとめもないことを言い繕う、うわべ限りの、自身の情動と感傷に酔い痴れる、オシャベリ好きの批評家として、アダム・ミュラーもシュレーゲル兄弟も描かれる。 万物の中に潜む鼓動し躍動する生を、生けるものの中で最も鋭敏な意識を備えた人間が、表面的な知覚を超えて感じ取り、その尽きせぬ意義を寓喩や象徴を通じて──ときには音楽を通じて──描き出そうとするからこそ深遠で価値ある芸術が生み出されるというシェリングの主張も、古典主義的な価値の斉一性・整合性・普遍性を否定し、共同体ごとに異なる多様な文化、人によって異なる相衝突する多元的価値をそれぞれ承認しようとするロマン主義の根底的前提も、シュミットからすれば、事象主義から流出する意味の奪われた、悪夢さながらの混迷を示すだけである。フェアな観察・分析とは到底思えない。 そもそもロマン主義の精神に形而上学的構造は存在するのか。この世界に所与の静態的構造などない。この世の理なるものを全否定し、すべては各自の意思と意識の力によって自律的に切り拓かれ、手の届き得ないものへ到達しようとする奔流であり、知的に分析され、書き留められた途端に死んでよどんだ水たまりになる。それがロマン主義を突き動かす精神であったはずである。19世紀のドイツでBildung、思考と直感と感性の総合を通じた自己形成があれほど強調された理由もそこにある。 ロマン主義者の言う「批評」も、現代のわれわれが想定する、外界の対象に対する審美的判断にとどまるものではない。それは批評者自身が他者の作品を通じて自身を省察する活動であり、異なる主体間のコミュニケーションであるとともに、批評者自身の内的なコミュニケーションでもある。サヴィニーの描く法学者が、法の認識者にとどまることなく、法の芸術家、制作者でもあるのは、そうした理由からである。法の認識と評価を峻別することはできない。法を理解し、保持し、蘇生させるのは、多様な主体間の自由なコミュニケーションを通じて構成され、形成される法学コミュニティの一員としての活動である。それは自己との対話であると同時に、同じ共同体に属する過去・現在・未来の他者との対話でもある(サヴィニーの法学観とロマン主義の連関については、Olivier Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), (PUF, 2005), première partie 参照)。 ロマン主義が明るみにした価値の多元性、多様な価値の比較不能性は、かりそめの表面的なものではない。それは我々が生きるこの世の現実のありようである。異なる価値、異なる文化を各主体が激情に突き動かされるままに真摯に貫こうとすれば、血みどろの殲滅戦がもたらされる。ロマン主義の後裔(の1つ)であるファシズムは、それを如実に示した。 価値の多元性を如実に示したロマン主義が今、われわれに示唆するのは、アイザィア・バーリンが指摘するように(Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism (Chatto & Windus, 1999))、人が人として生きる上での妥協が不可欠であること、多様な諸価値のフェアな共存を目指す政治体制を実現し維持すべきことではなかろうか。ロマン主義者の主張にもかかわらず、真摯に生きること(欺瞞を否定すること)は人生のすべてではない。リベラルな立憲主義は、たわいもないオシャベリを自己目的とするわけではない。それなしに、我々が生きていく(to be)ことはできない。絶対的とされる唯一の価値に隷従して生き長らえるか、あるいはそれに殉じて滅亡するかである。 『政治的ロマン主義』は、ロマン主義とは何であったかよりもはるかに、シュミットとは何者であったかを示しているように思われる。 *『政治的ロマン主義』の初版は1982年、未來社から橋川文三氏訳で、第2版は1970年、みすず書房から大久保和郎氏訳で、邦訳が刊行されている。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.

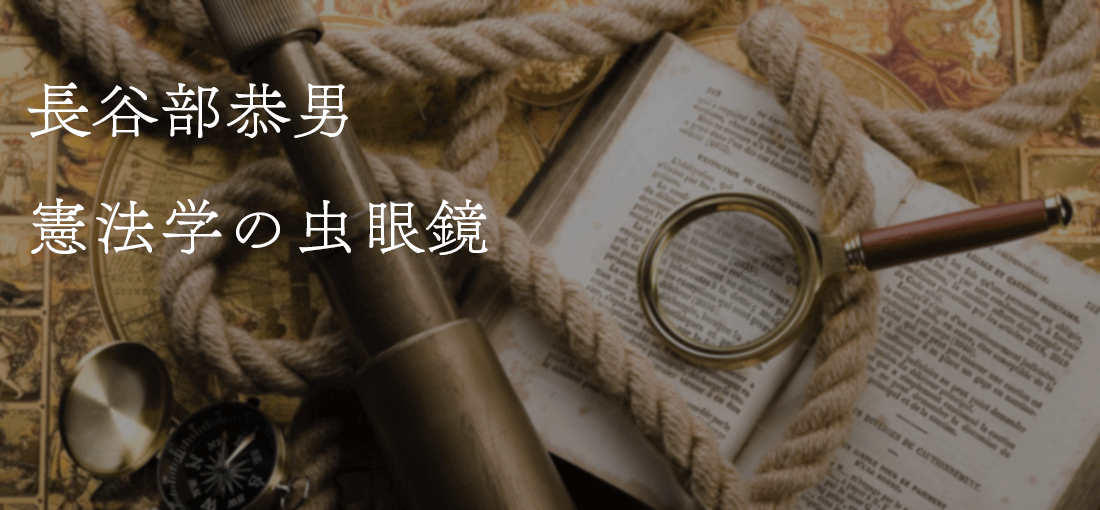
 RSSフィード
RSSフィード