|
藤田宙靖教授は、最近、「自衛隊76条1項2号の法意──いわゆる「集団的自衛権行使の限定的容認」とは何か」という論稿を著され(自治研究93巻6号(2017年6月号)、以下「法意」と略す。)、その中で、拙著『憲法の理性〔増補新装版〕』(東京大学出版会、2016)補論Ⅱで筆者が行った主張に対する応答をしておられる。筆者の主張は、藤田教授が以前に公表された論稿「覚え書き──集団的自衛権の行使容認を巡る違憲論議について」(自治研究92巻2号(2016年2月号)、以下「覚え書き」と略す。)への疑問を提示するものであった。 筆者が日頃から尊敬してやまない藤田教授から、拙論に対する応答をいただいたことは大変にありがたいことであり、また、藤田教授と筆者との間の対立点が奈辺にあるかを明らかにする上でも、大変に意義深いものであると筆者は理解している。結論を簡単に述べると、当初から懸念されたことではあるのだが、藤田教授には、実定法とその解釈に関する筆者の議論の意味内容が十分には伝わっていない。裏返して言うならば、藤田教授が理解するような法規範とその解釈との関係は、少なくとも実定法とその有権解釈との関係にかかわる限りでは、現代日本の法律家共同体の共通了解としては、およそ成り立ち得ないものであると、筆者は考えている。 藤田教授による法規範とその解釈に関する考え方の核心は、次のようなものである(法意14頁)。 「法律家共同体」の世界における法解釈論は、ある法律(ここでは憲法典をも含む)の規定が制定されることによって何らかの規範が生じたということを前提とし、その規範の内容はどのようなものか(何を定めているのか)あるいは、何が定められていると考えるのが最も妥当であるか、という問題を巡って、各論者がそれぞれに自分の考えを主張し競い合う、という思考枠組み・理論枠組み(法解釈論上の作法)の中で展開される。 この理論的な競い合いにおいては、「論者の平等が保たれている」。したがって、解釈を行う主体がたとえ内閣法制局であっても、「それ自体の性質はなお一つの「解釈」である」(法意15頁)。そうである以上、そうしたさまざまな解釈については、いずれかが「客観的に正しい唯一の解釈」であるということはあり得ない(法意11頁)。競い合う諸解釈は、あくまで「内容」の「適否」について同等の立場で競い合っている(法意15頁)。 こうしたスケッチから明らかになるのは、藤田教授は、現代日本の実定法は、あくまで制定法規であると考えているらしいことである。その解釈は実定法ではない。そして、実定法の諸解釈は、あくまで解釈であるという点ではすべて平等の地位にあり、いずれかが特権的地位に立つということはない。一学者の解釈論も、内閣法制局の解釈論も、そしておそらくは最高裁判所の解釈論も、すべては平等である。こうした理解からすれば、新たな解釈の方が「正しいと信ずる解釈」だというのであれば、「従前の解釈を変更することはいつでも許される」という立場を内閣法制局の「有権解釈」についてとることも、もちろん許されるのであって、それがなぜ筆者が主張するように「極めて不適切」であるのかは、「私 [藤田教授] には到底理解できない」(法意12頁)こととなるのも当然である。有権解釈とされる解釈と、学者の行う非有権解釈との間に差異はない。「通説・判例」にも何ら特別の地位が認められることはない(法意15頁)。 それにしても藤田教授は、単なる一法学者がその私的見解を改めるのと同様のことを2015年7月に内閣法制局は行ったに過ぎないと、そして、それにもかかわらずその結果として、安保法案に対するあれほどの広汎な国民の反対運動が起こり、数多くの著名な法律家が安保法案は違憲であるとの論陣を張ったのだと、本気で信じているのであろうか。また、その程度の見解の変更に過ぎないものの前提として行われた内閣法制局長官の人事が、あれほどの論議と批判を巻き起こしたことも、単なる一法学者の私的見解の変更と同等の帰結をもたらした、そのきっかけに過ぎないと、本気で信じているのであろうか。 さらにまた、藤田教授の覚え書きが公表されたとき、藁をも掴む思いでそれにすがりついた人々が手にしたのは、結局のところ、単なる一法学者が私的見解を改めるのと同等のことを内閣法制局が行っただけのことだから、あまり気に病むほどのことはないというアドバイスに過ぎないことになる。何より、すべての解釈論が同等なのだとすると、安保法案は違憲だと考える学者が口を揃えて違憲だと唱えたとしても、そのこと自体を非難したり疑問視したりする理由は藤田教授にはないということになるはずである。 さて、上述のような藤田教授の実定法とその解釈に関する理解が、なぜ受け入れがたいものであるのか、とりわけ実定法とその有権解釈と言われるものとの関係については、極めて不適切であるかを説明すると、以下のようになる(これはすでに、前掲拙著、補論Ⅱで行った説明の繰り返しとなる点が多い)。
実定法は制定法であれ、判例法であれ、社会の中で果たすべき役割があるからこそ存在し、人々から重視される。その役割とは何であろうか。当然のことではあるが、実定法は法学者が解釈ゲームを競い合う、その素材となるためにこの世に出現したわけではない。 人がいかに行動し、どう生きていくべきかは、各人がそれぞれに判断して決定する、それが少なくとも(魔術の解けた)近代以降の社会の常識である。しかし、実定法はそうした常識に反する主張をする。「各自が自分で判断しないで、私の言う通りにしなさい」と実定法は言う。実定法は自身が「権威authority」であると主張すると言われる事象である。なぜそうした主張をする資格があるか、その根拠は何かと言えば、それは「私の言う通りにした方が、あなたが本来すべきことをより良くすることができるからです」ということになる。 自動車を運行するとき、四つ角に差しかかる度に、止まろうか、進もうかと自分自身で判断し、行動するよりも、信号が青であれば進み、赤であれば止まる方が(つまり実定法の言う通りにする方が)、本来すべきこと、つまり自動車を安全にスムーズに運行することがより良くできる。世の中で実定法が果たしている核心的役割はここにある。つまり、自分で考えるのではなく、法の定める通りに行動するよう、人々の実践的判断を誘導し、変更する点にある。 実定法がこうした役割を果たすためには、実定法のテキストは読んで直ちにその意味が理解できるものでなければならない。テキストにはたしかにこう書いてあるが、これでは具体的場面でどう行動すればいいのか分からないというテキストでは、結局のところ、どう行動すべきかは各人がそれぞれ判断しなければならないことになる。法が法としての役割、権威としての役割を果たしていない。 しかし、そうした残念な実定法は少なからずある。テキストの意味内容が漠然としすぎているとか、複数のテキストが相互に矛盾・抵触しているとか、テキストの意味は明確なのだが、それが到底そのままでは実行できないような良識に反する内容だという場合が典型例である。 そうした場合は、実践理性の本来の姿に戻って、各人がそれぞれ自分で何が最善かを判断し、それに即して行動すればよいのだというのが、一つの割り切り方である。しかしそうしたとき、多くの社会では、本来の実定法であるはずのテキストに代わり「権威」として機能するものとして、「有権解釈 authoritative interpretation」が登場する。日本における典型は、最高裁判所が行う憲法の基本権条項に対する解釈である。 憲法の基本権条項のテキストは、それ自体は権威として機能するわけではない。表現の自由はすべて保障すると主張する憲法21条を何度読んでも、実際のところあらゆる表現活動が自由なのか、それとも実はいろいろな限界があるのかは、分からない。基本権条項の役割は、権威であることにはなく、むしろ、個別の実定法が具体的状況できわめて不適切な解決を指し示すかに見えるとき、あるいは何らかの解決を示すことにそもそも失敗しているとき、その実定法の主張する権威を「違憲無効」として解除する点にある。どのような場合に実定法の権威が違憲とされるのかは、憲法の条文をいくら読んでも多くの場合、分からない。その結論を決めるのは、最高裁の有権解釈である。最高裁の有権解釈に反する法案が提出されれば、それは「違憲」の法案だということになる。 法律の有権解釈についても同様である。判例に反する行動をとれば、違法とされ、サンクションを課される高度のリスクを背負うことになる。制定法の明確な文言に反したときにサンクションを課される蓋然性と、違いがあるとは限らない。判例の解釈も自身の解釈も同等だという前提で行動する人は、思慮の足りない人である。 こうした有権解釈は実定法と同様、人々の実践的判断に置き換わる。各自でそれぞれ何が違憲かを判断するのではなく、最高裁の有権解釈をそのまま受け入れるようにと、最高裁は主張している。もちろん、最高裁の今回の判断は怪しからん、と考える一般市民や学者はいるだろう。しかし、そうした私人の解釈と最高裁の解釈とは、同等の立場にあるわけではない。 憲法典というテキストのあるべき意味内容は何か、という内容の適否を争っている限りでは、私人の解釈も最高裁の解釈も同等かも知れないが、政府関係諸機関を含めて人々の判断に置き換わり、その行動を決める(と主張する)点で、有権解釈は有象無象の解釈とは異なっている。それは自身が「権威」であると少なくとも主張するし、その主張が受け入れられることもしばしばある。 有権解釈は、その内容において適切であることが少なくないであろう。少なくとも、きわめて不適切だと誰もが考えるようなものではないことが。しかし、有権解釈として通用していることと、その内容が適切であることの間には概念必然的なつながりはない。そもそも適切さの判断は人によって異なる。だからこそ、適切さに関する判断と切り離された権威が必要となる(適切さについてつねに客観的な判定が可能だとすれば、「客観的に正しい唯一の解釈」の存在可能性を原理的に否定することはできなくなる)。 そうである以上、現在の有権解釈よりも内容に関してよりましな解釈がありそうだと、その時々の最高裁の構成員が主観的に考えたからと言って、直ちにそれを新たな解釈に変更すべきだということにはならない(言うまでもないことながら、これは自身のした行政処分が誤っていると考えた行政機関が、それを撤回することとは全くレベルを異にする問題である)。先例の拘束性を遡及させるべきか否かについて、最高裁が慎重な考慮をせざるを得ないのも、最高裁の有権解釈が人々の判断に置き換わる権威として現に機能するからである。最高裁が先例を変更することはもちろんある。しかしその場合、なぜそうした変更をすべきかについては、種々の事情を勘案し慎重な衡量を経た上で、十分に説得的な理由が示されるべきことは、最高裁の多くの先例自体がそれを示している。 さて、日本の最高裁はあらゆる法律問題について有権解釈を下すかと言えば、そうではない。テキスト通りに行動するわけにはいかない憲法9条にかかわる問題については、最高裁はきわめて口数が少ない。そうなると、最高裁に代わって有権解釈、権威として機能する解釈を示す機関が必要となる。そうした機関として機能してきたのが、内閣法制局であった。内閣法制局が十分な理由も示すことなく、有権解釈を変更すべきでないのは、それが有権解釈だからである。藤田教授の理解とは異なり、有権解釈が有権解釈である以上、人々は解釈の内容の適否に立ち入ることなく、それを権威として受け入れるべきだと内閣法制局は主張してきたし、今後も主張するはずである。 したがって、藤田教授が今回の論稿の後半部分(三節、四節)で展開された、何が憲法9条の解釈として内容的に適切なのかという論点とそれに関する議論とは、内閣法制局が有権解釈をどのような場合に変更することができるのか、という論点とはレベルを異にしている。むしろレレバントなのは、法意33頁で指摘されている、内閣法制局による新たな解釈を必要とする事実の欠如や、新たな解釈の内容の不明確性により、それがそもそも「有権解釈」としての役割を果たし得ていないのではないかという諸論点である。有権解釈を変更する真っ当な理由が提示されておらず、かつ、新たな解釈が有権解釈としての役割を果たしていないのであれば、9条に関わる法案の合憲性は、変更以前の有権解釈に即して判断されるべきである。何の不思議もない。 藤田教授の考える「解釈」は、以上で描いてきたような、「権威」として機能する解釈とは全く異なっているようである。一見したところ、藤田教授は、あらゆる法規範はそれを理解する必要があり(それはその通り)、そして、およそ法規範のあらゆる理解は、「解釈」であり、したがって実定法の執行は、必ず当該実定法の解釈を前提としていると主張しておられるかのようである(これは間違っている。ハンス・ケルゼンは解釈について、そうした間違った理解をしていた。たとえば『純粋法学〔第二版〕』長尾龍一訳(岩波書店、2014)第45節)。 「解釈」という概念のこうした理解は、以上で描いてきたような法や解釈の役割に関する現代の法理論の標準的な立場と両立しない。現代の法理論の標準的な立場は、前掲拙著「補論Ⅱ」でも述べたように、ジョゼフ・ラズやアンドレイ・マルモア等、英米圏の法実証主義者によって展開され、広く受け入れられている。こうした現代の法実証主義陣営の理論は、現代の世界各国の法律家共同体において、実定法とその解釈とがどのような役割を果たしているかに関する事実認識に立脚している。そして、彼らが立脚する事実認識は、現代の日本社会においても妥当していると、筆者は考える。藤田教授が描くような、多様な解釈が平等に競い合う百家争鳴の状況は、実定法もその解釈も、社会から求められる核心的な役割を果たし得ていない、そして政府諸機関も一般市民も行動の指針を得ることのできない、病理的な状況である。 多くの法学者が自説こそが「適切な解釈」であると主張して競い合うことは、それ自体が目的であるわけではない(そのように見える法学者がときに存在することを否定するつもりはないが)。解釈学説の本来の役割は、実定法が権威として人々の行動を方向づける役割を果たし得ない状況において、実定法に代わって人々の行動を方向づける指針を提供することにある。それが解釈学説の果たすべき本来の役割であり、競い合うことが自己目的ではない。 第二に、これはより深刻な問題であるが、実定法に限らず、およそテキストのあらゆる理解は「解釈」として受けられるべきだという主張は、あらゆるテキストの理解を無限後退に陥らせ、その理解を不可能とする。解釈とは、あるテキストを別のテキストに置き換える作業である。あるテキストを理解するために、それを必ず別のテキストを置き換える必要があるとすると、その別のテキストを理解するためにも、それをさらに別のテキストに置き換える必要がある。この作業は無限に続く。法の解釈は、解釈抜きで成り立つ理解が存在する(それがむしろテキストの理解なるものの通常の姿である)ことを前提とする例外的な活動であり、そうした活動でしかあり得ない。 この点は、前掲拙著の第15章でも指摘している。つまり、藤田教授が受け入れているかに見える制定法とその解釈に関する理解は、およそ首尾一貫した理解として成立し得ない。かりに現代日本の法律家共同体の多くのメンバーが、藤田教授のような理解を共有しているのだとしても(筆者はそれを強く疑っているが)、それはそもそも筋の通ったものとして成り立ち得ない、誤った理解が共有されているだけのことである。誤った理解は、正されるべきである。解釈に関する誤った理解に基づいて、法の役割に関する適切な理解を得ることはできない。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
Categories |
Copyright © 羽鳥書店. All Rights Reserved.
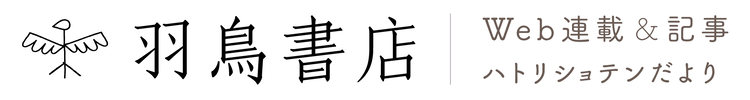

 RSSフィード
RSSフィード