|
2013年10月15日の朝。女川湾の北、尾浦(おうら)の浜で、カキむきの作業が始まりました。被災した共同処理場を建て直し、震災後初めてのカキむきです。 水揚げ後、半日殺菌したカキを手に、「むき子」と呼ばれる人たちが小刀を使って次々に殻をむき、真っ白な身を取り出します。その手元へ処理場の窓から朝の光がふりそそぎます。むき子たちが交わす声。殻が重なる音。小さな浜が活気づきます。 水揚げされたカキを見に行きました。 カキのまわりにいろいろな生き物がついています。無農薬の野菜についた虫を連想します。大地と同じく、大海も、生命の宝庫です。 ムール貝が多いですね、と声をかけましたら、漁師さんは「震災前は、このあたりでムール貝はそんなにつかなかったんだけどね」と話していました。 この後、私は、美智子さんの家を訪ねました。 ムール貝の話をしますと、「ここではシウリと呼ぶのよ」と教わりました。 「シウリは、お湯につけて退治するの」と妹の恵子さんは語り始めました。カキ養殖は家業でした。子どもの頃からよく手伝っていました。その頃の家でのシウリ退治の方法を解説してくれました。 シウリも食べられるとはいえ、それはカキが育つ場所を奪い、餌も同じプランクトンを食べてカキの成長を妨げるため、退治するのです。船上で、灯油缶に廃材をくべて火をたき、その上の釜で海水を沸かします。温度計で測りながら、70度になるまで待ちます。カキをつるしたロープを引き上げ、70度の湯にくぐらせ、ロープをまた海へ戻します。 恵子さん、そんなことをしたら、カキ料理が出来てしまうのでは? 「一瞬、お湯につけるだけだから、大丈夫なのよ」 なぜ、その一瞬にシウリだけ退治できて、カキは無事なのですか? 「そうねえ」。恵子さんも首をかしげます。「お母さんさ、聞いてみて」 すると、82歳のお母さんは、口を大きく開けて、ひと声「あっ」と発しました。あとは口をつぐんで満面の笑みを浮かべ、私を見つめます。その表情は「これがヒントよ。あててみなさい」と語っているのですが、いいえ、まったくわかりません。 お母さんは笑顔で説明を始めました。 「シウリは熱いと、『あっ』と口を開けてしまうの。開けた途端、熱湯が入るでしょ。カキは『あちっ』と口を閉じてしまうから、熱湯は入らないの」 次の日は台風26号の襲来です。荒波は海中の小さなカキを振り落としてしまいました。写真は、暴風雨がおさまった夕方の女川町中心部です。海から百数十メートルのこのあたりは大雨のたびに冠水を繰り返しています。 女川町からの帰り道、美智子さんの家へ寄りました。 牡鹿半島の付け根にある大きな入り江、万石浦(まんごくうら)のそばに家はあります。 震災の津波をかぶって全壊しましたが、改築しました。「おねえさんがいたら、街中に移っていたと思う」と妹たちは口をそろえます。街中でしたら、お母さんの通院にも便利だったでしょう。美智子さんもそう考えて引っ越したでしょう。けれども、妹たちは、姉の思い出が詰まった地に残ることにしました。 美智子さんの家でも、昔も今も、大雨が降れば冠水を警戒します。地震の時は津波情報に注意します。注意報が出れば、眠らずに解除の知らせを待ちます。 それが一家の習慣でした。 台風26号に備え、恵子さんはタケノコご飯をつくりました。「台風で停電になるかもしれないからね。炊き込みご飯だと、おかずが要らないでしょ。停電で暗い中では、おかずを並べても食べにくいからね」 それも一家の習慣でした。 その秋は、万石浦でも、共同処理場が再建され、カキむき作業が再開されました。恵子さんは「カキむき場を見に行くべ」とお母さんをドライブに誘いました。お母さんは歩くのに不自由があります。60歳まで養殖漁にいそしみました。海からロープを引き上げる時は、船端にひざをつけ、体重を支えました。その後遺症です。湿布を貼っていても、つねに、ひざが痛むのです。 お母さんは漁に精を出した昔を思い出しながら、車窓から処理場へ目を向けます。その視界に海が入ります。 今、お母さんにとって、海はどう映っているのでしょう。 「海があるから生活できるんだけど、テレビでも震災の様子を映すでしょ。あそこに巻き込まれたのかなとイライラしてくるの」 言葉がとがってきます。 「みんな見つかっていれば、仏様になったなと思えるけど、どこにいっぺなと思うもの」 美智子さんと一緒に流され、今も帰らない銀行員たちの行方も思うのです。 「海さ、嫌だね。出たくもないし、眺めたくもない。涙、出てくるもの」 そう話しながら、また涙があふれてきました。 コメントの受け付けは終了しました。
|
Author小野智美(おの さとみ) Archives
3月 2019
Categories
すべて
|
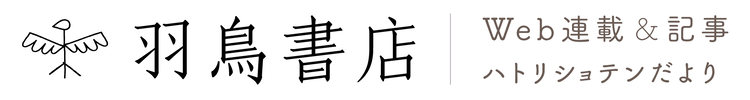





 RSSフィード
RSSフィード